脱炭素とSDGsの知恵袋、編集長の日野広大です。私たちは、政府のSDGs推進本部から「ジャパンSDGsアワード」 外務大臣賞を受賞した知見を活かし、企業のSDGs経営を支援しています。今回は、SDGsのみならず、株式会社FrankPRの事業の一つ、革製品ブランドRaffaelloの誕生の根幹に関わる重要なテーマ、「児童労働」に関する最新のニュースを専門家の視点から深く掘り下げます。
2025年までの撲滅が目標とされている児童労働。しかし、ユニセフと国際労働機関(ILO)から、その達成が「絶望的」であることを示唆する衝撃的な報告書が公表されました。このニュースが意味すること、そして日本に住む私たちや企業にとっての課題とは何でしょうか。
この記事のポイント
- ユニセフ・ILOの最新報告で明らかになった児童労働の現状
- なぜ児童労働は根絶できないのか?背景にある構造的な問題
- 日本企業も無関係ではない、サプライチェーンにおける人権リスク
- 「児童労働ゼロ」に向けて私たちができること
2025年目標達成は困難 – ユニセフ・ILO報告書の衝撃
今回ユニセフとILOが公表した報告書「児童労働:2024年の世界推計、傾向と今後の課題」は、私たちに厳しい現実を突きつけました。
- 世界の児童労働者数:約1億3800万人(2024年時点)
- うち、有害な労働に従事する子ども:約5400万人
1億3800万人という数字は、日本の総人口を上回る規模です。これだけ多くの子どもたちが、教育の機会を奪われ、心身の健全な成長を妨げられる環境で働かされているのです。
朗報として、児童労働者数は2020年以降に2000万人以上減少しており、改善の努力が実を結んでいる側面もあります。しかし、SDGs目標8.7が掲げる「2025年までにあらゆる形態の児童労働を撲滅する」というゴールから見れば、現状はあまりにも程遠いと言わざるを得ません。報告書が「達成されない見込み」と断言するのも無理はないでしょう。さらに、2030年までに撲滅を達成するには、現在の削減ペースを11倍に加速させる必要があると指摘されています。
なぜ児童労働はなくならないのか?3つの構造的要因
この根深い問題を解決するには、その背景にある構造的な要因を理解することが不可欠です。
1. 貧困と教育機会の欠如が生む負の連鎖
児童労働の最大の原因は、依然として「貧困」です。家計を支えるために子どもが働かざるを得ない状況があります。子どもが働けば、学校に通う時間はなくなり、教育を受けられないことで将来の職業選択の幅が狭まり、貧困から抜け出せなくなる、という負のサイクルが生まれます。
ユニセフのラッセル事務局長が「質の高い無償教育への投資」の重要性を訴えているのは、この悪循環を断ち切るためです。
私たちFrank PRの取り組み、Raffaelloにおけるシングルマザーの雇用促進は母親の貧しさのためにストリートチルドレンになったり、児童労働から逃れられない子供達を根本的に解決するため、彼らの身を案じての取り組みです。
2. 6割以上が集中する「農業」という現場
報告書によると、児童労働が最も多いのは農業部門で、全体の61%を占めています。私たちが日常的に消費するコーヒー、カカオ、コットン、パーム油などの生産現場で、多くの子どもたちが働いている可能性があります。
これは、生産地が途上国に集中しており、サプライチェーン(製品が消費者に届くまでの全工程)が複雑で、末端の労働環境が見えにくいことに起因します。
3. 紛争と脆弱な社会制度が影を落とすサハラ以南アフリカ
地域別に見ると、サハラ以南のアフリカに世界の児童労働人口の3分の2(約8700万人)が集中しています。この地域では、紛争や政治不安、極度の貧困、そして子どもたちを守るべき社会的保護制度の脆弱さが、問題をより深刻化させています。安定した社会基盤なくして、子どもの権利を守ることは困難です。
日本企業も無関係ではない。サプライチェーンに潜む人権リスク
「児童労働は海外の問題」と考えてはなりません。私たちが着る服、食べるチョコレート、使う電子機器の部品。その生産過程のどこかで、児童労働が関わっている可能性はゼロではないのです。
近年、欧米を中心に「人権デューデリジェンス」の法制化が進んでいます。これは、企業が自社の事業活動やサプライチェーン全体において、児童労働を含む人権侵害のリスクを特定し、防止・軽減する取り組みを求めるものです。日本政府も「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定し、企業に対応を促しています。
もはや、サプライチェーン上の人権問題は「知らなかった」では済まされない経営リスクです。自社の取引先に児童労働がないか、透明性をもって把握し、問題があれば是正に取り組む。こうした責任ある行動が、すべての企業に求められています。
私たちにできること – 「児童労働ゼロ」に向けた一歩
この大きな問題に対し、私たち一人ひとり、そして企業ができることは何でしょうか。
- 個人として
- 賢い消費を心がける: フェアトレード認証やレインフォレスト・アライアンス認証など、生産者の労働環境に配慮した製品を意識的に選ぶ。
- 関心を持ち、声を上げる: 好きなブランドや企業に対し、サプライチェーンの透明性について問い合わせるなど、消費者として関心を示す。
- 企業として
- 人権方針を策定し、公表する: 児童労働を認めないという断固たる姿勢を示す。
- サプライチェーンの透明化: 取引先まで遡って労働環境を調査し、リスクを評価する。
- 人権デューデリジェンスの実施: リスクの特定と防止、救済措置の仕組みを構築する。
ユニセフが指摘するように、成人の「ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」を確保することも、児童労働をなくすための重要な鍵です。弊社がRaffaello事業で実践しているように、親が安定した収入を得られれば、子どもを働かせる必要はなくなるからです。企業が従業員や取引先の労働者の権利を守ることは、巡り巡って未来の子どもたちを守ることにつながるのです。これは弊社のブランド事業が2014年に立ち上がった頃からの変わらぬ行動原理であると教えられています。
まとめ
SDGsが掲げた「2025年までの児童労働撲滅」という高い目標は、残念ながら達成が困難な状況です。しかし、この報告書は、諦めるためのものではなく、取り組みを11倍に加速させるための新たな出発点と捉えるべきです。
問題の根源にある貧困、教育、産業構造といった課題に目を向け、政府、企業、そして私たち市民一人ひとりが、それぞれの立場で行動を起こすことが求められています。あなたの今日の選択が、世界のどこかで働く子どもの明日を変えるかもしれません。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大 参考資料:
ユニセフ・ILO報告書「Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward」、オルタナ記事https://www.alterna.co.jp/156863/
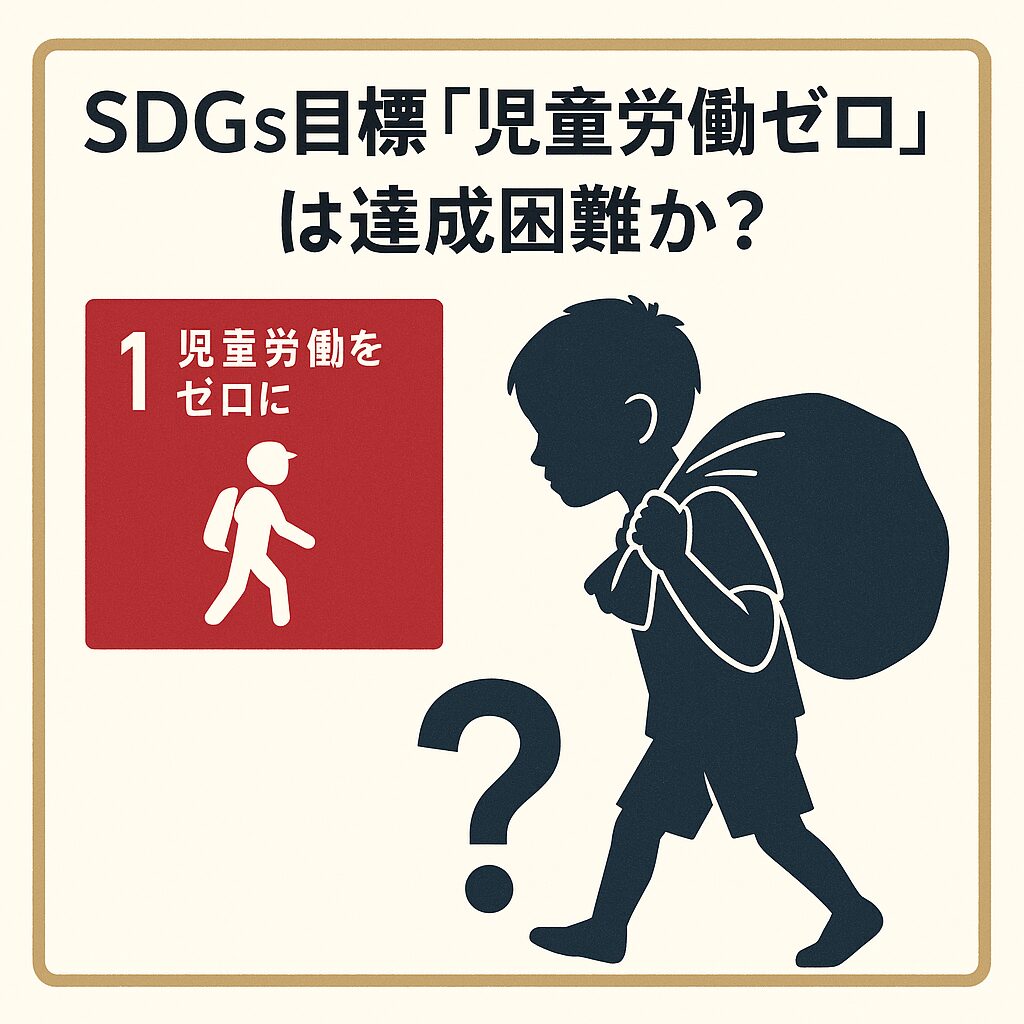
コメント