【SDGs】化石燃料依存は続く?脱炭素のリアルと未来へのエネルギー転換を考える
皆さん、こんにちは!「脱炭素とSDGsの知恵袋」、編集長の日野です。最近ニュースで「脱炭素」や「カーボンニュートラル」って言葉をよく耳にしますよね。でも、私たちの暮らしを支えるエネルギーの裏側って、実はまだまだ複雑なんです。今回は、エネルギー問題の「今」と、私たちが目指す「未来」について、一緒に考えてみませんか?
最新のSDGsニュース:
「トランプ米大統領の石油・ガス増産方針 「掘って掘って掘りまくれ」の背景を読む <潮流快読>現代社会は化石燃料に依存している」(産経新聞 2025/4/27)
https://www.sankei.com/article/20250427-DVTETXCHUNIYRJRGLOEGUXOH4A
SDGsニュースの要約
今回の記事は、トランプ前大統領の石油・ガス増産方針を切り口に、現代社会がいかに化石燃料に依存しているかを解説していますね。紹介されている3冊の本は、エネルギー問題が国際秩序や政治(いわゆる地政学、国の力関係ですね)にどう影響してきたか(『秩序崩壊』)、石油が国家の成り立ちにどう関わったか(『石油が国家を作るとき』)、そして電力以外の産業や農業における脱炭素の難しさ(『世界の本当の仕組み』)を指摘しています。再生可能エネルギーへの移行はSDGs達成に不可欠ですが、太陽光パネルなどに使うレアメタル確保の問題や、電気を貯めたり送ったりするための大規模なインフラ(蓄電・送電網)が必要という課題も明らかにしています。2050年のカーボンニュートラル実現には、社会システム全体での「空前の」エネルギー転換が求められる、という現実を教えてくれる内容です。
SDGsニュースのポイント
ここからは、ニュース記事のポイントを、私、日野が皆さんに分かりやすくお伝えしますね。
- トランプ前大統領は「掘って掘って掘りまくれ」と、石油や天然ガスの増産を進める方針を示しました。これは、エネルギーを使って国際的な影響力を強めようとした動きと見られています。
- エネルギー問題は、実は世界の政治や経済の混乱(例えば、イギリスのEU離脱やロシアのウクライナ侵攻など)の背景にある要因の一つだと考えられています。『秩序崩壊』という本で詳しく解説されていますね。
- 歴史的に見ても、1956年の「スエズ危機」のように、石油をめぐる出来事が国々の関係を大きく変えたこともありました。エネルギーは歴史を動かす力を持っているんですね。
- 石油や天然ガスは今後も重要ですが、再生エネに必要なレアメタル(特殊な金属のことです)は、中国が生産の大部分を握っている状況です。これが、再生可能エネルギーへの移行における新たな心配事(不安定要因)になっています。
- 私たちが今当たり前だと思っている国境線も、実は石油などの資源や、昔の植民地時代の政治の影響を受けて形作られてきた側面があるそうです(『石油が国家を作るとき』より)。つまり、絶対不変のものではないんですね。
- 驚くかもしれませんが、世界の半数以上の国は、できてからまだ70年未満。歴史的に見ると比較的新しい国が多いんです。国境も国家も変わりうる、という視点も大切かもしれません。
- 現代社会は、家庭で使う電気だけでなく、工場を動かす動力、飛行機の燃料、そして私たちが毎日食べる食料を作るための農業機械や化学肥料、ビニールハウスなど、あらゆる場面で化石燃料に深く頼っています。これって実は私たちの日常にも関わっているんです。
- 世界のエネルギー消費全体で見ると、電気(発電)が占める割合は約18%に過ぎません。残りの大部分、特に産業や輸送分野での脱炭素は、技術的にもコスト的にも、まだまだ難しい課題が多いのが現実です。
- 食料を作るためにも、トラクターを動かす軽油、化学肥料の原料となる天然ガス、野菜を育てるビニールハウスの材料など、多くの場面で化石燃料が使われています。エネルギー価格が上がると、食料品の値段にも影響が出るのはこのためです。
- 石油のような液体の化石燃料は、タンカーなどで遠くまで運びやすいという利点があります。一方、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを主力電源にするには、発電量が天候に左右されるため、電気を大量に貯めておく巨大なバッテリー(蓄電池)や、電気をロスなく遠くまで送るための送電網の整備が不可欠になります。
- 多くの国が目標に掲げる「2050年カーボンニュートラル」は、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという、とてつもなく大きな目標です。これを達成するには、これまでの歴史にないくらいのスピードと規模で、社会全体のエネルギーの使い方を根本から変える(エネルギー転換)必要がある、大変な挑戦なんです。
SDGsニュースを考察
さて、今回のニュース、皆さんはどう感じましたか?「脱炭素って言うけど、現実はまだまだ化石燃料なんだ…」「目標達成って、そんなに大変なの?」と、少し難しさを感じたかもしれませんね。まさにその通りで、ここがポイントです。**SDGsの目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」や目標13「気候変動に具体的な対策を」**を考える上で、この現実をしっかり見つめることが大切なんです。
紹介されていた『世界の本当の仕組み』にもあるように、私たちの社会は、コンセントから来る電気だけでなく、着ている服、使っているプラスチック製品、乗っている車、そして毎日の食事まで、本当に多くの場面で化石燃料の恩恵を受けています。身近な例で考えてみましょう。例えば、スマホやパソコンを作る工場を動かすエネルギー、それを運んでくる船やトラックの燃料、食料を作るための肥料や農薬、農業機械の燃料…。これら全てが脱炭素の対象となるわけですから、その大変さが想像できるのではないでしょうか。これは、エネルギー問題(SDG7, 13)が、経済(SDG8)や資源利用(SDG12)、食料(SDG2)とも、まるで糸のように複雑に絡み合っていることを示しています。
さらに、エネルギーをどう確保するかは、国の力関係(地政学)にも影響します。かつて石油を多く持つ国が力を持ったように、これからは再生可能エネルギーに欠かせないレアメタルの産出国や、その技術を持つ国の影響力が大きくなるかもしれません。また、レアメタルの採掘が環境破壊や人権問題を引き起こす可能性など、SDGsの目標間でのトレードオフ(あちらを立てればこちらが立たず、という状況)も考えなくてはなりません。エネルギー転換は、地球環境だけでなく、**SDGsの目標16「平和と公正をすべての人に」**で目指すような、安定した世界にも関わる大きなテーマなのです。
「じゃあ、私たちにできることなんてないの?」…いえいえ、そんなことは全くありません!むしろ、こういう複雑な現実を知るからこそ、私たち一人ひとりの日々の選択や行動が、未来を変えるための大切な一歩になるんです。
私たちにできること
大きな社会の仕組みを変えるには時間がかかりますが、日々の暮らしの中でできることは、実はたくさんあります。小さな一歩が大きな変化につながります。完璧じゃなくていいんです。できることから一つずつ、楽しみながら取り組むのが長続きのコツですよ。
- 「もったいない」を減らす: まずは基本の「省エネ」です。使わない電気は消す、エアコンの温度を適切に設定する、シャワーの時間を少し短くする。移動も、近場なら自転車や徒歩、少し遠くなら公共交通機関を使ってみる。無理のない範囲で「もったいない」を減らす意識が大切です。
- エネルギーの「選び方」を変える: もし可能なら、ご自宅の電気を再生可能エネルギーで作られた電気を選ぶプランに変えてみるのはどうでしょう?最近はいろんな電力会社がプランを出していますよ。家電を買い替える時も、省エネ性能(ラベルをチェック!)で選ぶのは、立派なアクションです。
- 「食」から考える: 意外かもしれませんが、食卓もエネルギーと繋がっています。地元で採れた旬の野菜を選ぶ「地産地消」は、遠くから運んでくるエネルギー(フードマイレージと言います)を減らせます。食べ残しを減らすことも、食材の生産や廃棄にかかるエネルギー削減につながりますね。
- 「知る」そして「伝える」: エネルギー問題やSDGsについて、少しアンテナを張ってみませんか?ニュースを見たり、関連する本を読んだり。「へぇ、そうなんだ!」と思ったことを、家族や友人と話してみるのもいいですね。関心を持つ人が増えることが、社会を動かす力になります。
- 「応援」という選択: 環境に配慮した製品作りや脱炭素に取り組んでいる企業の商品やサービスを選ぶ。これも、未来への投資です。「この会社、頑張ってるな」と思ったら、SNSでシェアしたりするのも、素敵な応援になります。
エネルギー転換という大きな課題を前にすると、少し圧倒されてしまうかもしれません。でも、この記事が示すように、現実を理解し、歴史から学び、そして未来への希望を持って、私たちができること、すべきことを見つけていくことが重要です。今日からできることから始めてみませんか? きっと、その一歩が、より良い未来につながっていくはずです。
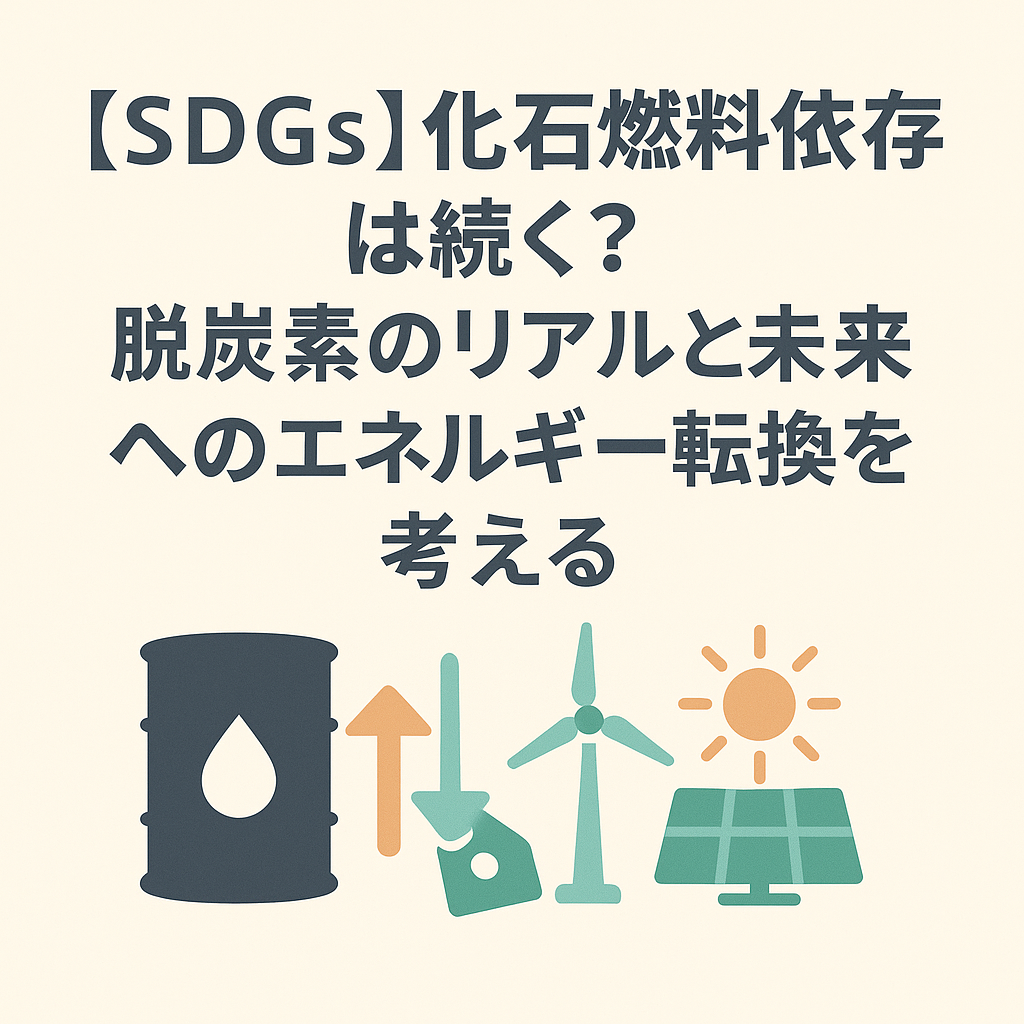
コメント