石破首相、洋上風力発電のEEZ展開加速へ – 日本の脱炭素戦略とSDGsへの影響は?
画像:日本の広大なEEZに展開される可能性のある洋上風力発電のイメージ
脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長の日野広大です。政府のSDGs推進本部からも評価いただいた知見を活かし、SDGsや脱炭素に関する重要なニュースを厳選し、その背景や意義を深掘り解説しています。今回は、日本のエネルギー政策の未来を左右する可能性のある、石破首相による「洋上風力発電のEEZ(排他的経済水域)展開」に向けた意欲表明について、専門的な視点から分かりやすく解説します。これは、日本の2050年カーボンニュートラル目標達成やSDGsの実現に向けた重要な一歩となるかもしれません。
- この記事のポイント
- 石破首相が洋上風力発電のEEZ展開に向けた制度整備加速を表明
- 日本の領海内だけでは洋上風力の適地が限られる背景
- EEZ展開の鍵となる技術(浮体式)と関連法案の重要性
- SDGs目標7、13、14、9との関連性と期待される効果
- 実現に向けた技術的・経済的・環境的課題と今後の展望
政府が目指す「海の上の発電所」EEZ展開の背景
2025年4月25日、石破茂首相は総理大臣官邸で開催された「総合海洋政策本部」の会合で、日本のエネルギー政策における新たな方針を示しました。日本経済新聞によると、首相は「洋上風力発電を最大限導入するため、排他的経済水域(EEZ)への展開に向けて制度整備を加速する」と述べ、今国会に提出されている関連法案の早期成立への強い意欲を表明しました。
脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化は世界の潮流であり、日本も例外ではありません。特に四方を海に囲まれた日本にとって、洋上風力発電は大きなポテンシャルを秘めたエネルギー源として期待されています。これまで、洋上風力は比較的風況の良い、水深の浅い領海内で開発が進められてきました。しかし、日本の領海は沖合に出ると急激に水深が深くなる場所が多く、風車を海底に固定する「着床式」の洋上風力発電に適した場所は限られているのが現状です。
そこで注目されるのが、領海の外側に広がる**EEZ(排तिहासिक水域)**です。EEZは沿岸から200海里(約370km)までの、天然資源の探査や開発、経済活動に関する主権的権利が認められた海域です。日本のEEZは世界有数の広さを誇り、ここを有効活用できれば、洋上風力の導入ポテンシャルは飛躍的に拡大します。石破首相の発言は、この広大な「海の上の発電所」候補地を本格的に活用するための法整備を進めるという、強い決意の表れと言えるでしょう。
参照:日本経済新聞「石破茂首相、洋上風力発電のEEZ展開に意欲 海洋政策本部」
なぜEEZ?領海内だけでは足りない日本の洋上風力
日本のエネルギー自給率は低く、その多くを化石燃料の輸入に頼っています。脱炭素化とエネルギー安全保障の両立は国家的な重要課題です。洋上風力は、大規模な発電が可能で、陸上風力に比べて風況が安定しているなどの利点があり、有力な解決策の一つとされています。
しかし、前述の通り、日本の地形的な制約から、領海内での着床式洋上風力の適地は限られています。政府は2040年までに30〜45GW(ギガワット)の洋上風力導入目標を掲げていますが、これを達成するためには、領海内だけでは不十分と考えられています。
深い海がもたらす課題と浮体式技術の可能性
EEZへの展開で鍵となるのが**「浮体式洋上風力発電」**技術です。これは、風車を海底に固定せず、海に浮かべた浮体構造物の上に設置し、係留チェーンなどで海底に繋ぎ止める方式です。水深が深い場所でも設置が可能になるため、日本のEEZのように沖合の深い海域での開発を可能にします。
図:浮体式洋上風力発電の構造イメージ(ダミー)
alt属性案:海上に浮かぶ風車とそれを支える浮体、海底への係留システムを示す図
この浮体式技術はまだ発展途上であり、着床式に比べてコストが高いなどの課題がありますが、世界的に技術開発と実証が進められています。日本がEEZでの洋上風力展開を成功させるためには、この浮体式技術の確立とコスト低減が不可欠となります。
関連法案の行方:実現へのハードル
EEZでの洋上風力開発を進めるには、新たな法整備が必要です。EEZは領海とは異なり、他国の船舶の航行などが認められているため、発電施設の設置や運用に関するルールを明確に定める必要があります。昨年(2024年)の通常国会にも関連法案が提出されましたが、成立には至らず廃案となりました。
石破首相が今回、改めて法案の早期成立に意欲を示したことは、政府としてEEZ展開を本格化させる強い意志を示したものです。この法案が成立すれば、事業者がEEZで洋上風力発電を行うための手続きや権利関係が明確になり、開発が加速することが期待されます。
洋上風力EEZ展開がSDGs達成にもたらすインパクト
洋上風力発電のEEZ展開は、複数のSDGs(持続可能な開発目標)達成に貢献する可能性を秘めています。
目標7・13(エネルギー・気候変動)への貢献
最も直接的な貢献は、**SDGs目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」と目標13「気候変動に具体的な対策を」**です。洋上風力は発電時にCO2を排出しないクリーンなエネルギー源であり、その導入拡大は日本の温室効果ガス排出削減目標、ひいてはカーボンニュートラル達成に大きく貢献します。広大なEEZを活用することで、エネルギー自給率の向上にも繋がり、エネルギーの安定供給確保にも寄与します。
目標14・9(海洋環境・産業革新)との両立は?
一方で、留意すべき点もあります。**SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」**との関連です。大規模な洋上風力発電施設の建設・運用が海洋生態系や漁業に与える影響については、慎重な評価と対策が必要です。適切な環境アセスメントの実施、漁業関係者との対話と共存策の模索が不可欠となります。
また、**SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」**の観点からは、EEZでの洋上風力開発は、浮体式技術を含む関連技術の開発を促進し、新たな産業と雇用を創出する大きなチャンスでもあります。部材製造から建設、メンテナンスに至るまで、広範なサプライチェーンの構築が期待されます。
専門家が注目するポイントと今後の課題
EEZへの洋上風力展開は大きな可能性を秘めていますが、実現にはいくつかの課題を乗り越える必要があります。
技術開発とコスト低減の必要性
前述の通り、特に浮体式洋上風力技術の確立とコスト競争力の向上が急務です。初期投資が大きい洋上風力発電において、いかにコストを抑え、他の電源と遜色のない価格で電力を供給できるかが普及の鍵を握ります。技術開発への継続的な投資と、量産効果によるコストダウンが求められます。
環境アセスメントと漁業との共存
広大な海域を利用するため、海洋環境への影響を最小限に抑えるための徹底した事前調査(環境アセスメント)が不可欠です。また、古くから漁業活動が行われてきた海域でもあるため、漁業関係者との丁寧な合意形成プロセスと、共存を図るための具体的な方策(漁業活動への影響が少ない区域選定、補償制度、新たな漁業との連携など)が重要になります。
私たちにできること:脱炭素社会への参加
政府の大きな方針転換は、遠い話のように聞こえるかもしれません。しかし、エネルギー問題は私たちの生活と密接に関わっています。
- 関心を持つ: まずは、こうしたエネルギー政策の動向に関心を持ち、情報を得ることが第一歩です。関連ニュースを追ったり、政府や自治体の発表を確認したりしてみましょう。
- 選択する: 個人のレベルでは、再生可能エネルギー由来の電力プランを選択することも、脱炭素社会への貢献になります。
- 対話に参加する: もしお住まいの地域で洋上風力開発計画などが持ち上がった際には、説明会に参加したり、意見を表明したりすることも重要です。
企業にとっては、サプライチェーンへの参画や、自社の事業活動における再生可能エネルギー利用の拡大などが具体的なアクションとして考えられます。
まとめ
石破首相による洋上風力発電のEEZ展開加速への意欲表明は、日本の脱炭素化とエネルギー政策における重要なマイルストーンとなる可能性があります。広大な日本のEEZを活用し、「海の上の発電所」を実現できれば、クリーンエネルギー供給の拡大、エネルギー自給率向上、そして新たな産業創出に繋がります。
しかし、その実現には、浮体式技術の開発・コストダウン、環境影響評価、漁業との共存といった課題を乗り越える必要があります。関連法案の整備はその第一歩であり、今後の具体的な制度設計と、官民を挙げた取り組みが注目されます。
この動きは、SDGs目標7(クリーンエネルギー)、13(気候変動対策)、14(海洋資源)、9(産業・技術革新)など、複数の目標達成に貢献しうる一方で、それぞれの目標間のバランスを取ることも求められます。広大なEEZを活かす日本の挑戦、私たちはどう向き合い、持続可能な未来に繋げていくべきでしょうか。
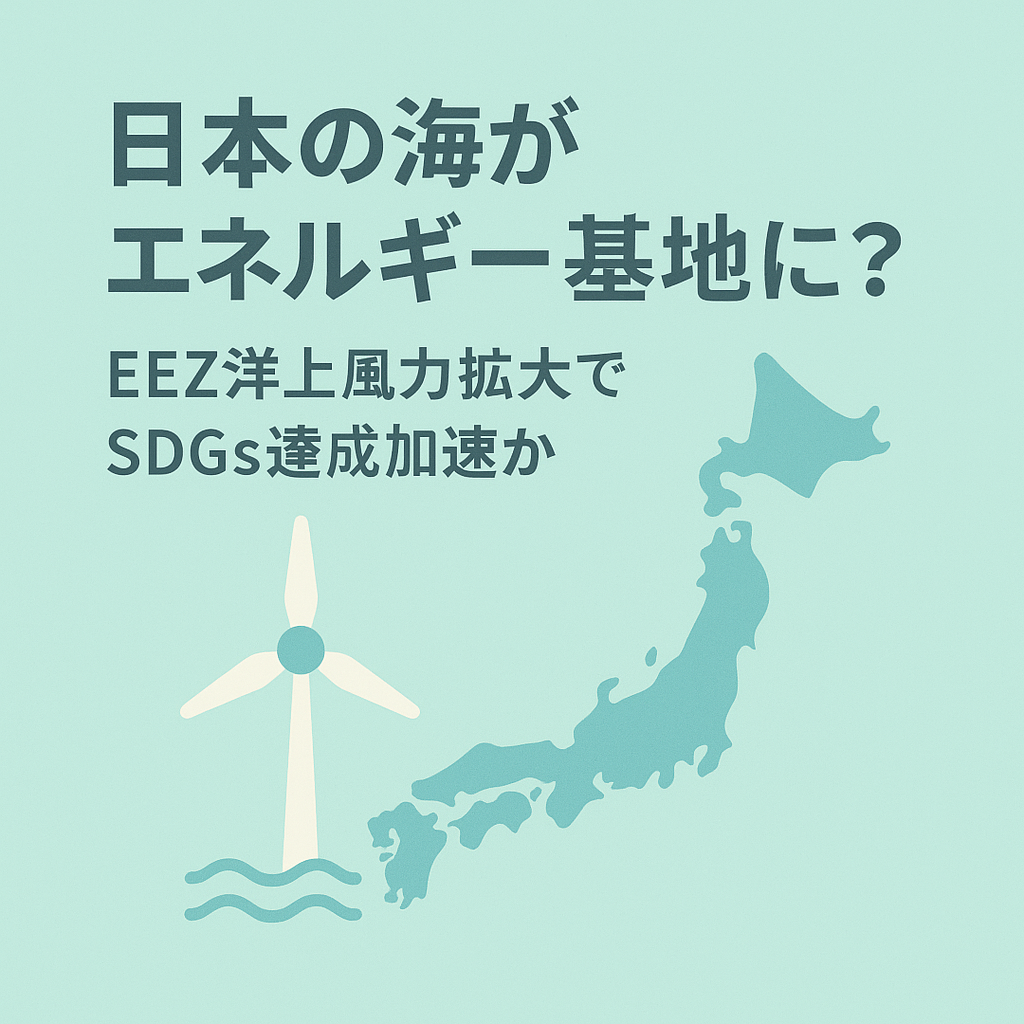
コメント