脱炭素とSDGsの知恵袋の編集長、日野広大です。「ごみは燃やすのが当たり前」――この長年の常識が、日本の大学発の革新的な技術によって覆されようとしています。名古屋大学発のスタートアップ「クロスイー」が開発する「燃やさない焼却場」は、CO2を排出せず、コストも大幅に削減できるという、まさにゲームチェンジャーとなりうる技術です。
私たちFrankPRは、政府SDGs推進本部よりジャパンSDGsアワード外務大臣賞をいただくなど、多くの企業のサステナブルな取り組みを見てきましたが、今回のニュースは、廃棄物処理という社会の根幹的な課題を解決し、サーキュラーエコノミーを加速させる大きな可能性を秘めていると感じています。本記事では、この革新的技術の仕組みとその重要性を、SDGsの視点から深掘りします。
この記事のポイント
- CO2を出さない「燃やさない焼却場」の驚くべき仕組み
- なぜ「焼却」よりコストが3〜4割も低いのか
- ごみが価値ある資源に変わる「アップサイクル」の具体例
- SDGs達成とサーキュラーエコノミーへの貢献
「燃やす」から「炭化する」へ。クロスイー社の革新的技術とは?
今回、日本経済新聞で報じられたのは、名古屋大学発スタートアップ「クロスイー」が開発する、全く新しいごみ処理プラントです。この技術の核心は、ごみを「燃やす(焼却)」のではなく、「炭にする(炭化)」という点にあります。
技術の心臓部:濃硫酸による「脱水炭化」
このプラントは、名古屋大学の小林敬幸准教授の研究成果を応用したもので、濃硫酸が持つ強力な脱水作用を利用します。
- プラント内に生ごみや下水汚泥などの有機性廃棄物を投入。
- ペレット状の触媒とともに180度で加熱・攪拌する。
- 濃硫酸の働きで廃棄物から水分だけが効率的に抜き取られ、燃焼させることなく炭素の塊(炭)が残る。
これは、理科の実験を思い出す方もいるかもしれませんが、その化学反応を極めて高度に制御し、実用化したものです。高温で燃やす必要がないため、化石燃料を使う必要も、CO2などの温暖化ガスを排出する必要もありません。
参考ニュース: 「燃やさない焼却場」CO2もコストも減 名大発新興、26年度にも (日本経済新聞)
なぜこの技術が重要なのか?サーキュラーエコノミーとSDGsの視点
この「燃やさない」という特徴は、環境面だけでなく、経済面、そして社会全体にとって計り知れない価値を持ちます。
課題だった「食品廃棄物」の新たな活路
日本の食品由来の産業廃棄物は、再利用率が4割程度に留まり、多くがコストをかけて焼却処分されています。これは、SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」における食品ロス削減の観点からも大きな課題でした。
クロスイーの技術は、これまで「処分すべき厄介者」だった食品廃棄物を、価値ある工業原料や製品へと転換(アップサイクル)する道を開きます。これは、廃棄物ゼロを目指すサーキュラーエコノミー(循環型経済)の理想的なモデルと言えるでしょう。
「バイオ炭」が生む無限の可能性
このプロセスで生まれる「炭」は、バイオ炭と呼ばれ、多様な使い道が期待されています。
- 高機能コンクリート: 大手ゼネコンと共同開発中で、コンクリートに混ぜることで水分を吸収し、建物の耐久性を下げる「ひび割れ」を防ぐ効果が期待されます。これはSDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」や目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献します。
- 半導体関連素材(グラファイト): 半導体製造に不可欠なグラファイト(黒鉛)材としての活用も視野に入れています。脱炭素な製法で作られた素材は、サプライチェーン全体の環境負荷を低減したい企業にとって大きな魅力となります。
- 土壌改良材: バイオ炭を土に混ぜると、土壌の保水性や通気性が向上し、農作物の生育を助けます。さらに、炭素を土壌に長期間閉じ込める(炭素貯留)効果があり、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」に直接的に貢献する技術として世界的に注目されています。
編集長解説:日本の廃棄物処理が抱える課題とゲームチェンジャーの役割
日本の廃棄物処理は、長年「焼却」に大きく依存してきました。その結果、衛生的な処理は実現できましたが、一方でCO2排出や最終処分場の問題は常に付きまといます。
焼却依存からの脱却とカーボンニュートラル
2050年カーボンニュートラルの実現を目指す日本にとって、廃棄物分野からのCO2排出削減は避けて通れない道です。クロスイーの技術は、廃棄物処理のあり方を根本から変え、CO2排出源を価値創造の源泉へと転換するポテンシャルを秘めています。これはまさに、社会インフラのGX(グリーン・トランスフォーメーション)そのものです。
「産学金連携」が生んだイノベーションモデル
この取り組みが素晴らしいのは、技術そのものだけではありません。名古屋大学の「知」(産)、クロスイーというスタートアップの「実行力」(学)、そして東邦ガスや日本特殊陶業といった事業会社の「支援・連携」(金)が一体となっています。これは、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を体現する、新しいイノベーションの形を示しています。
私たちの暮らしと企業の未来へのインパクト
この技術が社会に実装されれば、私たちの社会はどのように変わるのでしょうか。
自治体のごみ処理はどう変わる?
多くの自治体が、焼却施設の老朽化や運営コストの高騰に頭を悩ませています。CO2もコストも削減できる「燃やさない焼却場」は、財政を圧迫することなく、環境に配慮したまちづくりを実現する切り札になるかもしれません。
企業ができること:自社の廃棄物を「資源」として捉え直す
食品メーカーやその他有機性の廃棄物を出す企業にとって、これはコスト削減と環境貢献を両立する絶好の機会です。私たちFrankPRは、企業がサステナビリティ経営を推進する上で、自社の事業活動から出るものを「廃棄物(コスト)」ではなく「未利用資源(ポテンシャル)」と捉え直す視点が重要だと考えています。この技術は、その視点転換を強力に後押しする具体的なソリューションとなるでしょう。
まとめ:ごみが「資源」になる時代へ。サーキュラーエコノミー実現の鍵
名古屋大学発の「燃やさない焼却場」は、単なるごみ処理技術のニュースではありません。それは、気候変動、資源枯渇、食品ロスといった、私たちが直面する複数の社会的課題を同時に解決しうる、統合的なソリューションです。
これまで価値がないとされ、燃やされてきたものが、私たちの暮らしを支えるコンクリートや半導体、食料を育む土壌に生まれ変わる。そんな未来を、この技術は指し示しています。ごみが「コスト」から「資源」になる時代の到来は、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料: 日本経済新聞
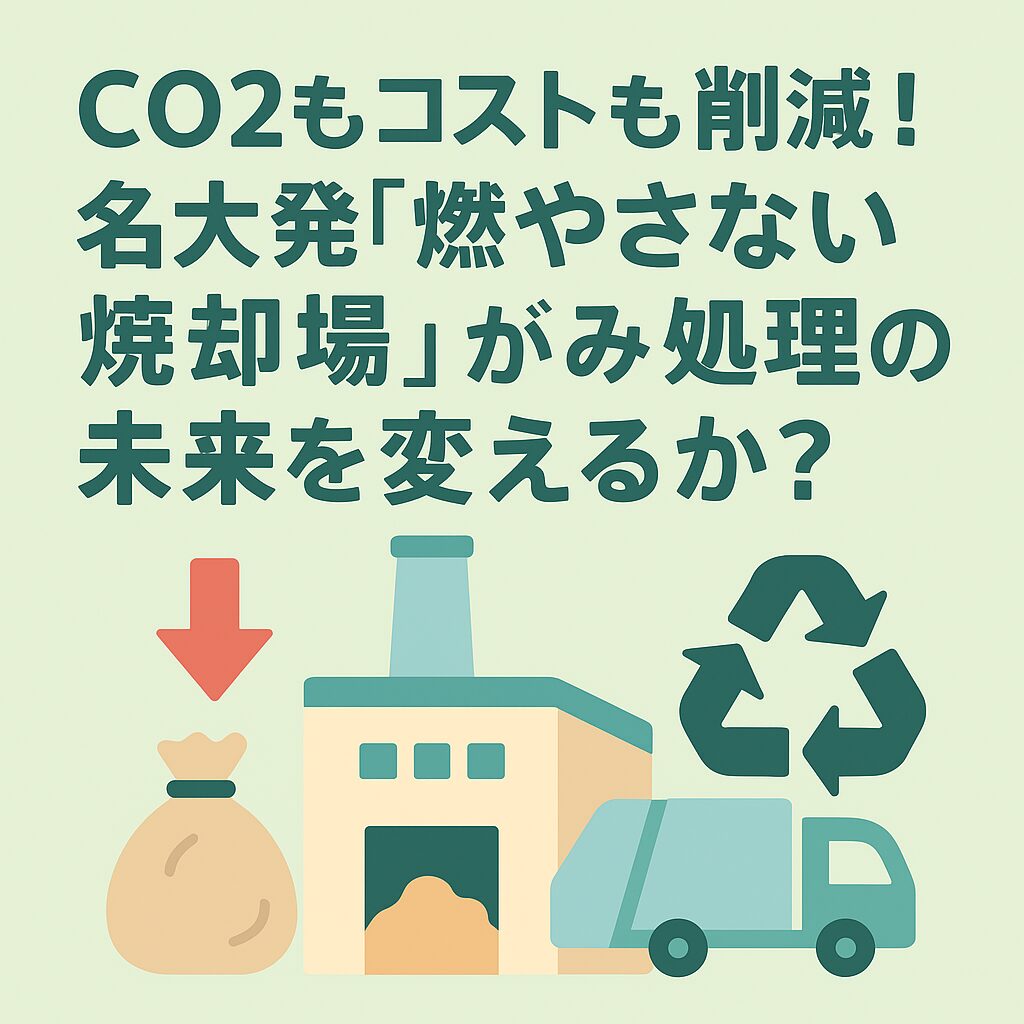
コメント