皆さん、こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディアは、SDGs達成に向けた企業の取り組みが評価され、政府SDGs推進本部からジャパンSDGsアワード(外務大臣賞)を受賞したFrankPR株式会社が運営しています。その専門性を活かし、今回は日本のエネルギー政策の根幹に関わる「石炭」について、世界的な逆風と、それがもたらす深刻なリスクを解説します。金融から保険、輸送まで、石炭包囲網は着実に狭まっており、日本のエネルギー安全保障とSDGs達成の両立が、いよいよ待ったなしの状況となっています。
この記事のポイント
- 世界の金融・保険業界で脱石炭の動きが加速。投融資や保険の引き受けが厳格化。
- これを受け、石炭の生産・貿易量は今後大幅に減少する見通し。
- 日本の主力電源である石炭火力だが、G7合意から遅れ、依存度が高いまま。
- 燃料用石炭の主要調達先であるオーストラリアで炭鉱閉鎖ラッシュが迫り、調達リスクが急上昇。
- 日本のエネルギー政策の課題と、求められるエネルギー転換の方向性とは?
世界で進む「脱石炭」:金融・保険業界の規制強化が石炭ビジネスを直撃
かつて産業の基盤を支えた石炭ですが、燃焼時のCO2排出量が天然ガスの約2倍と環境負荷が大きいことから、SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成に向け、世界的に利用削減の動きが加速しています。その大きな推進力となっているのが、金融・保険業界による「石炭包囲網」の強化です。
銀行の7割が投融資制限、保険も提供縮小へ
日本経済新聞の記事によると、驚くべきことに、世界の主要銀行上位60行のうち7割が、石炭関連事業への投融資を制限する方針を公表しています。さらに、BNPパリバなど約4割は、原則として2040年までに石炭関連事業から完全に撤退する目標を掲げています。
身近な例で考えてみましょう。私たちが家を買うときに住宅ローンを組むように、企業が新しい炭鉱を開発したり、発電所を建設したりするには、銀行からの巨額の融資が不可欠です。その資金調達が難しくなっているのです。
保険業界も同様で、大手約30社のうち7割が石炭関連のリスクに対する保険の引き受けを制限しています。再保険大手スイス・リーは、石炭の採掘や海上輸送への保険提供条件を厳格化しました。エネルギー経済社会研究所の松尾豪氏は、「すでに保険料率は上昇しており、30年以降は保険の提供自体が制限される可能性もある」と指摘しています。これは、石炭関連ビジネスのリスクが非常に高いと見なされている証拠であり、事業継続そのものを困難にする可能性があります。
資源メジャーも生産縮小、石炭貿易は10年で2割減予測
こうした金融・保険業界の動きを受け、スイスのグレンコアや豪BHPといった世界的な資源メジャーも石炭事業からの撤退や生産縮小を進めています。新規の炭鉱開発への投資は滞り、既存の炭鉱も寿命を迎えつつあります。
その結果、世界の石炭貿易量は今後大きく減少すると予測されています。日本郵船の調査によると、燃料として使われる石炭の海上輸送量(海上荷動き)は、今後10年間で年率3.1%のペースで減少し、2033年には2023年比で27%減となる見通しです。特に、世界最大の石炭輸出国であるインドネシアでは、環境基準を満たせない古い炭鉱の淘汰が進むと見られています。
日本の石炭火力依存のリスク:豪州炭鉱閉鎖で調達難が現実に?
世界が「脱石炭」へと舵を切る中、日本の状況はどうでしょうか?残念ながら、日本は石炭火力からの脱却で遅れをとっています。
主力電源なのに…G7合意から遅れる日本の脱石炭
日本の発電量に占める石炭火力の割合は28%(2023年度速報値)と、LNG(液化天然ガス)火力と並んで依然として高く、**SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」**で求められるクリーンエネルギーへの転換が進んでいません。
欧州では、英国が2024年に石炭火力を原則停止し、フランスやイタリアも2020年代中の全廃を目指しています。2024年春のG7(主要7カ国)環境相会合では、2035年までに排出削減対策が施されていない石炭火力発電所を原則廃止することで合意しましたが、日本には具体的な廃止年限の目標がありません。政府は次期エネルギー基本計画で、40年度に火力発電比率を3〜4割に減らす目標を示しましたが、その中で石炭火力をどうするのか、具体的な道筋は示されませんでした。
頼みの豪州炭が激減?2030年代からの供給不安シナリオ
日本の燃料用石炭は、その99%を輸入に頼っており、中でも品質が高いとされるオーストラリア産に約7割を依存しています。しかし、その頼みの綱である豪州で、2030年から炭鉱の閉山ラッシュが始まると予測されているのです。
(上記はイメージです。実際の画像に合わせてキャプションとクレジットを記載してください。) Alt属性例: オーストラリアの港で石炭を輸送船に積み込む様子。
特に、日本向けの輸出が多い南東部ニューサウスウェールズ(NSW)州では、現在稼働中の39炭鉱のうち、40年までに32カ所が閉鎖される見込みです。エネルギー経済社会研究所の松尾氏によると、「30年代初頭から日本の調達への影響が顕在化する」と指摘されており、同州の50年の石炭生産量は最大でも2700万トンと、23年のわずか1割の水準にとどまる可能性があるという衝撃的な予測も出ています。
エネルギー基本計画の曖昧さと求められる国の決断【専門家解説】
この豪州からの供給不安は、日本のエネルギー政策にとって極めて深刻な問題です。
50年でも必要量は豪州生産予測の2倍超?高まる調達リスク
日本エネルギー経済研究所(IEEJ)の試算では、現行のエネルギー政策が続いた場合、2050年時点でも、日本は2021年の約4割水準の燃料用石炭が必要になるとされています。これは、前述した豪NSW州の2050年の最大生産量予測(2700万トン)の2倍を超える規模です。他の国からの調達を増やすにしても、世界全体で石炭貿易が縮小する中で、安定的に、かつ経済的な価格で必要な量を確保できる保証はありません。調達リスクは非常に高まっていると言わざるを得ません。
水素・アンモニア転換は間に合うか?石炭の役割再考も必要
政府は、石炭火力に水素やアンモニアを混ぜて燃やす、あるいは完全に置き換える技術(混焼・専焼)に期待を寄せていますが、これらの技術はまだ開発途上であり、コストや安定供給、インフラ整備(輸送・貯蔵)など多くの課題を抱えています。50年までに石炭必要量を大幅に削減できるかは不透明です。
こうした状況を踏まえ、国際環境経済研究所の竹内純子主席研究員は、石炭火力を常時稼働させるベースロード電源としてではなく、燃料の貯蔵性の高さを活かし、電力需給の変動に対応する調整電源としての活用を検討すべきだと指摘しています。石炭火力の役割そのものを見直す時期に来ているのかもしれません。
私たちFrankPRも、企業のエネルギー転換戦略や、それに伴うリスク・機会の分析を支援していますが、国レベルでの明確な方針がなければ、企業も大胆な投資判断は難しいのが実情です。次期エネルギー基本計画で曖昧にされた石炭火力の削減計画は、いずれ具体化が避けられません。国が責任を持って石炭利用の将来展望を示し、エネルギー転換を加速させる必要があります。
企業・個人への影響と求められるアクション
この石炭包囲網の強化と調達リスクの高まりは、他人事ではありません。
企業への影響とアクション
- コスト増・供給不安: 電力料金の上昇や、エネルギー供給の不安定化リスクが高まります。特に電力多消費産業は影響が大きくなります。
- サプライチェーンリスク: 自社のCO2排出量だけでなく、サプライチェーン全体(Scope3)での排出削減圧力が強まります。石炭由来の電力を使っている取引先があれば、リスクとなります。
- 新たなビジネス機会: 再生可能エネルギー、省エネ技術、水素・アンモニア関連技術など、エネルギー転換に関連する分野での新たなビジネスチャンスも生まれます。
- 求められるアクション: エネルギー調達戦略の見直し、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギー導入の加速、サプライヤーエンゲージメントなどが急務です。
個人への影響とアクション
- 電気料金: 石炭火力から他の電源への転換コストや、燃料調達コストの上昇が電気料金に反映される可能性があります。
- 安定供給への関心: エネルギーの安定供給が将来も維持されるのか、関心を持つ必要があります。
- できること: 家庭での省エネ実践、再生可能エネルギー由来の電力プランへの切り替え検討、エネルギー政策に関する情報収集、自身の意見表明(パブリックコメントなど)などが考えられます。
政府もGX(グリーン・トランスフォーメーション)推進戦略に基づき、企業の省エネ・再エネ導入支援や、関連技術開発への投資を進めています。こうした制度を活用することも重要です(参考:経済産業省 GX実現に向けた基本方針)。
まとめ:待ったなしの石炭火力脱却、日本のエネルギー安全保障とSDGs達成の道
世界的な脱石炭の流れは、もはや止めることのできない大きな潮流となっています。金融・保険業界からの圧力、主要輸出国での生産減少により、日本が安価で安定的に石炭を調達できた時代は終わりを告げようとしています。
日本のエネルギー政策は、エネルギーの安定供給と脱炭素(SDGs目標7, 13達成)という二つの目標をいかに両立させるか、極めて難しい舵取りを迫られています。石炭火力からの段階的な、しかし着実なフェードアウト(段階的廃止)の道筋を具体的に示し、再生可能エネルギーの最大限の導入、そして水素・アンモニアなどの次世代エネルギー技術の開発・実装を加速させることが急務です。
これは国だけの課題ではありません。企業、そして私たち一人ひとりが、エネルギーの未来に関心を持ち、それぞれの立場でエネルギー転換に向けた行動を起こしていく必要があります。日本のエネルギー安全保障と持続可能な未来のために、今こそ大きな決断と行動が求められています。
参考記事:「狭まる石炭包囲網、輸送も金融規制 貿易量33年に2割減」
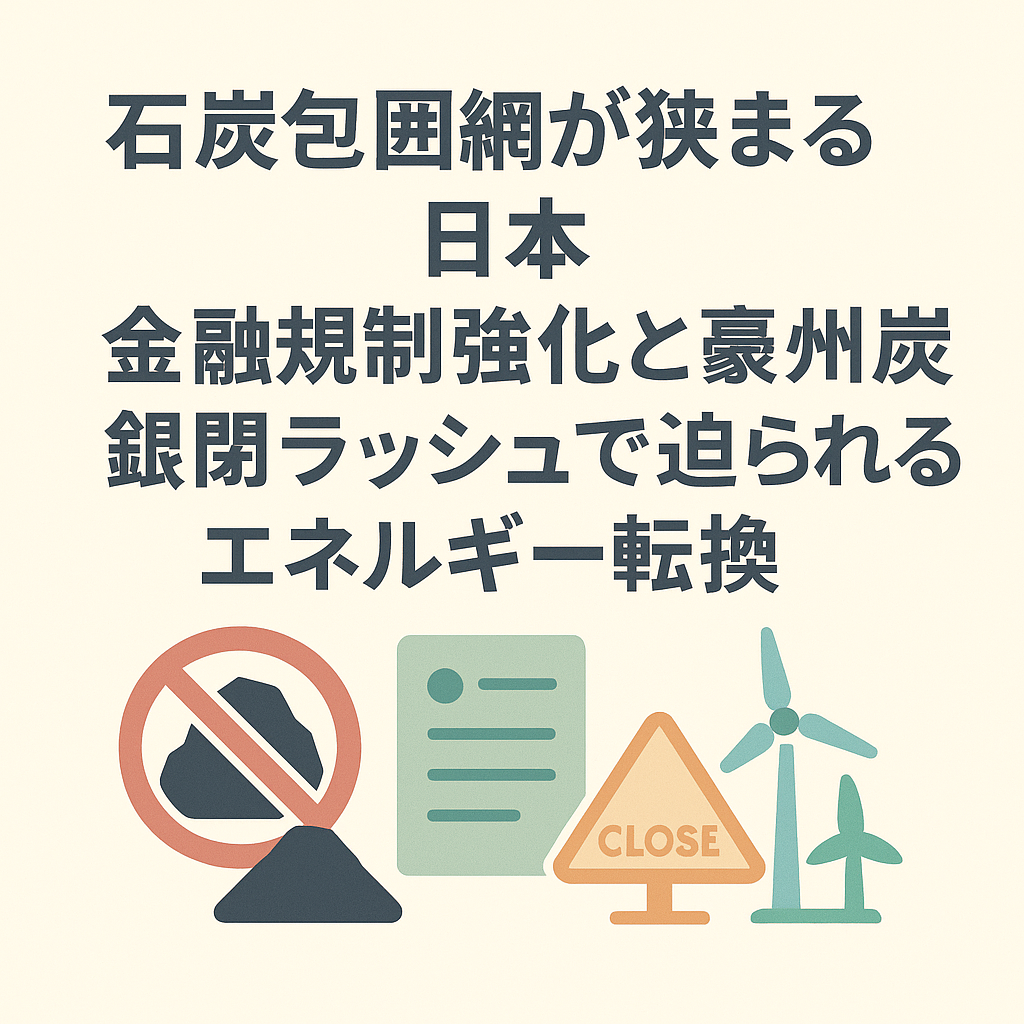
コメント