こんな人にオススメです
- 再生可能エネルギーの「良い面」と「課題」の両方を知りたい方
- 「メガソーラーがなぜ問題に?」と疑問に思っている方
- 地域の自然景観や防災に関心がある方
- 日本のエネルギー政策とSDGsの関係について知りたい方
環境に優しいはずの太陽光発電ですが、今「無秩序な開発が自然を壊している」として大きな問題になっています。高市新政権もこの問題に本腰を入れるようで、私たちのエネルギーと国土の未来について、改めて考えるタイミングが来ていますね。
最新のSDGsニュース:
無秩序メガソーラー 「猛反対」の高市首相が規制強化方針 外国製パネルが国土埋め尽くし
(出典:産経新聞、https://www.sankei.com/article/20251025-CQW54VB4NVKVBOHE5LVC6O6ELI/)
SDGsニュースの要約
高市新政権が、急速に増えた大規模太陽光発電所(メガソーラー)の規制強化に乗り出しました。2012年の固定価格買い取り制度(FIT)開始以降、太陽光発電は急増しましたが、同時に「景観が損なわれる」「土砂崩れのリスクがある」といった問題が全国で起きています。特に北海道の釧路湿原のような大切な自然の近くでも開発計画が進み、自治体が条例で対応していますが、国の法整備が追いついていないのが現状です。新政権は、再生可能エネルギーの推進と、自然破壊を防ぐ「悪い太陽光」の規制をどう両立させるか、難しい舵取りを迫られています。専門家は、事業者と地域住民の合意形成こそが重要だと指摘しています。
SDGsニュースのポイント
- 高市新政権が「無秩序なメガソーラー」の規制強化を明確に打ち出しました。
- 高市首相は「美しい国土を外国製パネルで埋め尽くすことに猛反対」と強い姿勢を見せています。
- 背景には、カーボンニュートラルを目指す一方で、景観破壊や土砂崩れなど「負の部分」が各地で問題になっていることがあります。
- 2012年のFIT制度開始から、太陽光発電は一気に増えましたが、ルール作りが追いついていませんでした。
- 大分県由布市など、自治体レベルでは景観を守るために独自の条例を作る動きが広がっています(全国で323自治体)。
- 特に問題になっているのが、北海道の釧路湿原。タンチョウの生息地近くでの開発に「待った」をかけるため、釧路市が規制条例を施行しました。
- 和歌山県では、知事の「認定」を必要とするなど、一歩進んだ規制を導入している例もあります。
- ただ、自治体だけでは限界があり、「国がしっかり法律でルールを決めてほしい」という声が現場から上がっています。
- 政府もようやく関係省庁での会議をスタートさせ、地域との共生策を探り始めました。
- 専門家は「メガソーラーだけを悪者にするのではなく、地域と事業者が早い段階で話し合う(ステークホルダー・エンゲージメント)仕組みが大事」と指摘しています。
- 今後は、地熱発電など他の再生可能エネルギーとのバランスも重要になってきそうです。
SDGsニュースを考察
今回のニュース、SDGsの視点で見るとすごく重要ですね。地球温暖化対策(SDGs 13)のために、カーボンニュートラルを目指す上で、再生可能エネルギー、特に太陽光発電(SDGs 7)は切り札の一つです。
でも、その「作り方」を間違えると、釧路湿原の例のように大切な生物多様性(SDGs 15)を脅かしたり、土砂災害のリスクを高めて「住み続けられるまち」(SDGs 11)を危うくしたりする…。まさにSDGsの目標同士がぶつかってしまう典型例です。
大切なのは、「環境に良いこと」が「地域にとって良いこと」にもなるようにバランスを取ること。専門家が言うように、計画の早い段階で地域住民と事業者がしっかり話し合うこと、つまりステークホルダー・エンゲージメントが不可欠です。
これからは、ただパネルを敷き詰めるだけでなく、例えば農地の上で発電と農業を両立する「ソーラーシェアリング」や、都市部の建物の屋根を最大限活用するなど、もっと賢い設置方法が求められますね。
私たちにできること
この大きな問題に対して、私たちにもできることがあります。
- 地域の計画に関心を持つ: もし家の近くで開発計画が持ち上がったら、まずは説明会に参加してみる、自治体の情報を見るなど、「知る」ことから始めましょう。私たちの声が、より良い計画につながるかもしれません。
- 自宅や職場でできる「省エネ」を徹底する: メガソーラーがたくさん必要なのは、私たちがそれだけ多くの電気を使っているからです。エネルギー効率の高い家電を選ぶ、こまめに電気を消すなど、日々の省エネが、結果的に無秩序な開発へのブレーキにもなります。
- 「賢い」エネルギーを選ぶ: もし電力会社を選べるなら、発電方法や環境への配慮を基準に選んでみるのも一つのアクションです。
- 「再エne」について正しく知る: 太陽光だけでなく、風力発電や水力発電など、色々な再エネにはそれぞれメリットと課題があります。まずは再生可能エネルギーの基本を知ることで、ニュースの見方も変わってくるはずです。
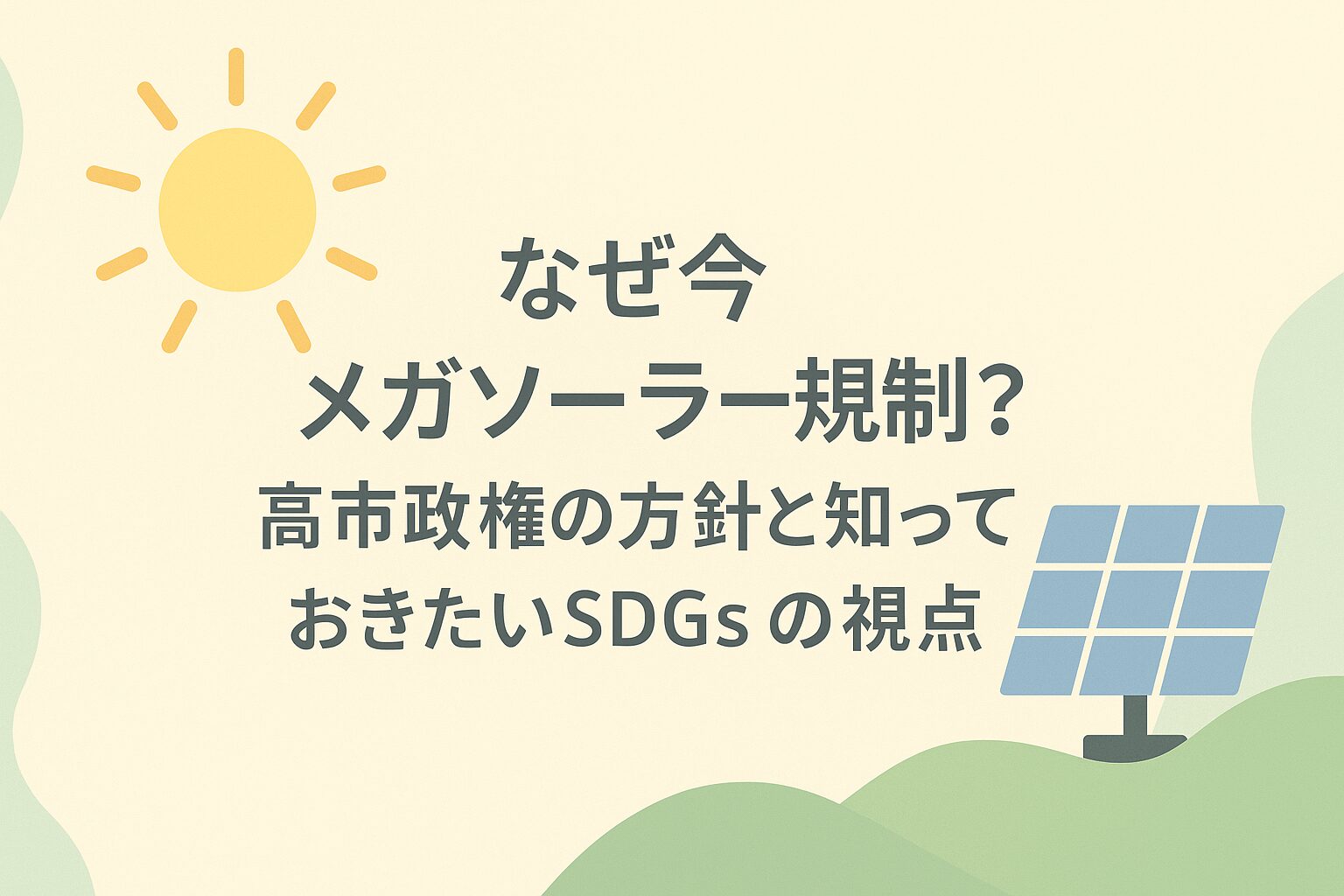
コメント