こんな人にオススメです
- 気候変動も大事だと思うけど、日々の生活や将来の年金がもっと心配…という方
- 「日本は環境意識が低い」と聞いて、本当のところどうなのか知りたい方
- [SDGsとは?(https://franksdgs.com/sdgs-sustainable-development-goals-explanation/)について、経済や社会保障とのバランスで考えたい方
- 政府や企業任せにせず、自分たちにできることを冷静に考えたい方
みなさん、こんにちは!「SDGsの知恵袋」編集長の日野です。ブラジルでCOP30(国連気候変動枠組み条約締約国会議)が開かれていますね。これは、気候変動対策の国際ルールである「パリ協定」の進捗を確認する大切な会議です。
そんな中、最新の国際調査で「日本は気候変動への意識が世界一低い」という、ちょっとショッキングな結果が出ました。でも、これは単に私たちが無関心というわけではなく、実は「生活や経済も大事」という、とても現実的な”冷めた良識”の表れかもしれないんです。この日本の「本音」を、SDGs達成のヒントとしてどう生かせるか、一緒に考えてみませんか?
最新のSDGsニュース:気候変動より社会保障? 日本の「冷めた良識」、世界で生かすには
(ソース:日本経済新聞 2025年11月16日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD113SJ0R11C25A1000000/
SDGsニュースの要約
最新の国際意識調査(イプソス)で、日本は「気候変動に今すぐ行動しないと次世代を裏切る」と考える人の割合が32カ国中最低の40%と、世界平均(64%)を大きく下回りました。これは2021年から19ポイントも減っており、最大の減少幅です。また、内閣府の世論調査でも、政府への要望は「物価対策」「医療・年金などの社会保障」「景気対策」が上位を占め、「環境保全」は28.5%と低い順位でした。しかし、記事は「日本人が無関心なわけではない」と指摘します。なぜなら、自国で起きている気候変動の影響は、日本人の約8割が気にしているからです。むしろ、日々の生活や将来の社会保障といった課題への不安が大きすぎて、気候変動問題を「棚上げ」する傾向が他国より強いのだろうと分析しています。政府が確かな解決策を示せないだろうという不信感や、気候変動を感情論ではなく「エネルギー・経済問題」として冷静に捉える「冷めた良識」が背景にあるようです。この記事は、この日本の冷静な視点が、感情的な対立を招きがちな国際議論に冷静さをもたらす可能性があるとし、日本政府に経済課題として気候変動対策を進めるリーダーシップを期待しています。
SDGsニュースのポイント
このニュース、ちょっとドキッとする内容ですが、日本の「今」を映し出していてとても重要です。ポイントを身近な視点で整理してみましょう。
- 「次世代を裏切る」に同意、日本は最下位: 「気候変動のために今すぐ行動しないと次世代に申し訳ない」という考えに「はい」と答えた日本人は40%(32カ国中最低)。世界平均は64%なので、かなり低いですね。
- 一番の関心事は「日々の暮らし」: 日本国内の調査では、政府に望むことのトップ3は「物価対策」「社会保障(医療・年金)」「景気対策」。私たちの切実な声が反映されています。
- 「環境保全」は優先順位が低い?: 同じ調査で「環境保全」を望んだ人は28.5%。暮らしの不安に比べると、優先順位が下がってしまっているのが現状です。
- でも、無関心じゃない!: ここが一番のポイントです。 「自国で起きている気候変動の影響」については、日本人の約8割が「気にしている」と回答しています。
- なぜ行動の優先順位が低いのか?: 記事の分析では、社会保障や経済など「目の前の課題」が大きすぎて、気候変動が「棚上げ」されている状態だと言います。「気候変動も大事だけど、それどころじゃない」という本音ですね。
- 政府への「諦め」も?: 「どうせ政府はちゃんとした解決策なんて示せないだろう」という諦めや不信感が、行動を鈍らせている可能性も指摘されています。
- 日本人の「冷めた良識」: 私たちは気候変動を「かわいそう」といった感情論だけで捉えるのではなく、「エネルギーをどうするか」「経済はどうなるか」という生活に直結する「経済問題」として冷静に見ている、という見方です。
- この「冷静さ」は武器になる?: 感情論で対立しがちな世界の気候変動の議論に、日本人の「経済とのバランスをどうとるか」という冷静な視点は、むしろ良い影響を与えるかもしれない、と記事は結んでいます。
SDGsニュースを考察
今回のニュース、「日本人は環境意識が低い」と一言で片付けてしまうのは、少し違うかもしれないと考えさせられました。
編集長として私が思うのは、日本人のこの「冷めた良識」は、実はSDGs(持続可能な開発目標)の本質を無意識に捉えているのではないか、ということです。
SDGsは、Goal 13「気候変動に具体的な対策を」だけを目指すものではありません。Goal 3「すべての人に健康と福祉を」(まさに社会保障ですね)や、Goal 8「働きがいも経済成長も」、Goal 1「貧困をなくそう」(物価高はここに直結します)など、17の目標すべてを「同時に」「バランスよく」達成しようというのが、SDGsの核心なんです。
つまり、「気候変動のために経済を犠牲にする」や「経済のために環境を諦める」のは、どちらもSDGs的にはNGです。日本人が「社会保障も経済も大事だ」と感じるのは、人間として当たり前の感覚であり、持続可能な社会を目指す上で絶対に無視できない視点です。
問題なのは、気候変動対策が「コストがかかる」「我慢を強いるもの」としてしか提示されず、「私たちの生活を豊かにし、経済を成長させるもの」というビジョンが見えてこないことではないでしょうか。
例えば、再生可能エネルギーへの転換は、新しい雇用を生み出し(Goal 8)、エネルギーの自給率を高め、結果的に物価の安定につながる可能性を秘めています。また、エネルギー効率の高い製品を選ぶことは、家計の節約(Goal 1)にもなります。
政府や企業が示すべきなのは、カーボンニュートラルへの道筋が、いかに私たちのウェルビーイング(Well-being)(=心身ともに良好な状態)や経済的な安定(SDGsがもたらす経済的メリット)につながっていくか、という具体的な青写真です。
日本人の「冷めた良識」は、「感情論じゃなく、ちゃんと生活が成り立つ解決策を見せてくれ」という、政府や企業に対する非常に高度な要求なんだと私は思います。
私たちにできること
では、この「冷めた良識」を持つ私たちは、何をすればいいのでしょうか。
- 「統合的」な視点を持つ
「環境か、経済か」の二択で考えるのをやめてみませんか? 例えば、家庭でエネルギー効率の高い家電に買い替えることは、電気代の節約(経済)とCO2削減(環境)の両方に貢献します。SDGsは、こうした「一石二鳥」を見つけるためのツールなんです。 - 「賢い消費者」として声を上げる
私たちが「経済も環境も大事」という視点で商品やサービスを選ぶことが、企業を変える一番の力になります。そして、「年金も不安だし、気候変動も不安。両方に効く政策を!」と声を上げることも、政治を動かす一歩になります。 - 自分の「ウェルビーイング」も大切にする
社会保障への不安は、将来のウェルビーイングへの不安です。まずは自分自身の健康や働き方を見直し、心身ともに持続可能でいることも、広い意味でのSDGsアクションです。
「気候変動に冷たい」のではなく、「生活全体に真剣」。それが日本の現在地なのだと思います。その真剣さを、持続可能な未来をつくるエネルギーに変えていきたいですね。
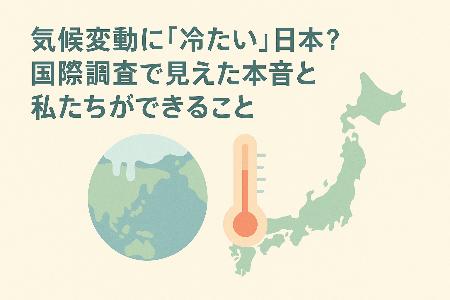
コメント