こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディアは、SDGs推進への貢献が認められ、政府SDGs推進本部よりジャパンSDGsアワード「外務大臣賞」をいただいた企業の知見を基に、信頼性の高い情報発信を心がけています。
「もう着ないけれど、捨てるのはもったいない…」。多くの家庭のクローゼットに眠る衣類。実は、その多くが最終的に焼却・埋め立て処分されていることをご存知でしょうか。この「ファッションロス」問題解決の鍵を、国や自治体がようやく見出そうとしています。
今回は、環境省が作成に乗り出した「衣類循環の事例集」のニュースを深掘りします。なぜ衣類リサイクルが進まないのか、その背景にある“50年前の法律の壁”、そして、その壁を乗り越えようとする自治体と企業の挑戦を、SDGsの視点から解説します。
この記事でわかること
- なぜ日本の服の7割は捨てられてしまうのか?
- 衣類リサイクルを阻む法律の壁「専ら物」とは?
- 壁を乗り越える自治体と企業の先進的なパートナーシップ
- 私たちが明日から参加できる「サーキュラーファッション」
なぜ日本の服の7割は捨てられるのか?廃棄衣類問題の現状
衝撃的な事実ですが、現在、日本国内で新たに供給される衣類のうち、実に7割が一度も再利用されることなく焼却・埋め立てされています。その量は、1日あたり大型トラック約130台分にもなると言われています。
国はこの状況を改善すべく、「2030年度までに家庭から出る廃棄衣類を25%削減する」という目標を掲げました。しかし、多くの自治体では予算や人手不足から衣類の分別収集まで手が回らず、市民にとっては「燃えるごみ」として出すのが最も簡単な処分方法になっているのが現実です。
この巨大な「もったいない」をなくし、貴重な資源を循環させるにはどうすればよいのでしょうか。
鍵は「専ら物」にあり!自治体の”勇気ある解釈”が循環を加速する
衣類リサイクルを阻む意外な壁、それが「専ら物(もっぱらぶつ)」という法律上の古い概念です。
「専ら物」とは?1971年のルールが抱える課題
「専ら物」とは、廃棄物処理法において、再生利用が容易であるため、廃棄物処理業の許可がない一般の事業者でも収集・運搬ができると定められた品目のことです。古紙や金属くずなどと共に「古繊維」がこれに含まれます。
問題は、このルールが定められたのが1971(昭和46)年だということ。当時は合成繊維のリサイクル技術が確立しておらず、「古繊維=天然繊維」と解釈するのが一般的でした。しかし現代では、衣類の主流はポリエステルなどの合成繊維です。この“50年前の常識”が、現代の衣類リサイクルを進める上での足かせとなり、自治体によって「合成繊維の服は専ら物ではない」と判断され、民間企業の柔軟な参入を妨げる一因となっていました。
名古屋市の挑戦:民間連携で実現する新しい衣類回収の形
この膠着状態に風穴を開けたのが、名古屋市の取り組みです。同市は、市民の利便性を高めるため、スタートアップ企業ECOMMIT(エコニット)との連携を決断。
市の担当者が環境省の見解も参考にし、「現代では合成繊維もリサイクル技術が確立している」と判断。再生ルートが確保されていることを確認した上で、合成繊維を含む衣類も「専ら物」と認定したのです。
これにより、ECOMMITは廃棄物処理業の許可がなくても、市内の商業施設などに回収ボックスを設置できるようになりました。市民は買い物ついでに気軽に衣類をリサイクルに出せるようになり、自治体はコストをかけずに回収拠点を増やすことができる。まさにWin-Winのパートナーシップです。
環境省が作成する「事例集」は、こうした名古屋市の“勇気ある一歩”を全国の自治体に共有し、衣類循環の取り組みを加速させることを目指しています。
SDGs視点で読み解く、衣類循環の重要性
この衣類循環の取り組みは、SDGsの複数の目標達成に貢献します。
- 目標12: つくる責任 つかう責任
大量生産・大量消費・大量廃棄からの脱却を目指す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の実現そのものです。衣類を資源として捉え直し、長く使い続ける社会への転換を示しています。 - 目標13: 気候変動に具体的な対策を
衣類の焼却を減らすことは、温室効果ガスであるCO2の排出削減に直結します。一着の服を大切に循環させることが、地球温暖化の防止に繋がるのです。 - 目標17: パートナーシップで目標を達成しよう
今回のケースは、国(環境省)が旗を振り、自治体(名古屋市)がルールを柔軟に解釈し、民間企業(ECOMMIT)が新しいサービスを担う、という理想的なパートナーシップの好例です。この連携なくして、社会課題の解決はあり得ません。
私たちにできること – 明日から始めるサーキュラーファッション
この大きな社会の変革は、私たち一人ひとりの行動から始まります。
- 賢く買う: 長く大切に着られる、質の良い服を選ぶ。
- 正しく手放す: 自治体のルールを確認し、資源ごみとして出す。近くに回収ボックスがあれば積極的に利用する。
- 循環させる: フリマアプリやリユースショップを活用し、次の使い手につなぐ。
- 企業の取り組みを応援する: 回収プログラムやリペアサービスを提供しているブランドを積極的に選ぶ。
まとめ:環境省の事例集が示す、”捨てない社会”へのロードマップ
一着の服を捨てるか、循環させるか。その選択の背景には、50年前の法律の壁と、それを乗り越えようとする人々の挑戦がありました。
環境省が示す新たな事例集は、全国の自治体にとって、”捨てない社会”を実現するための具体的なロードマップとなるでしょう。私たち消費者も、この大きなうねりの当事者として、自らの選択に責任を持ち、サーキュラーファッションを楽しみながら実践していくことが求められています。あなたのクローゼットから、サステナブルな未来を始めてみませんか。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
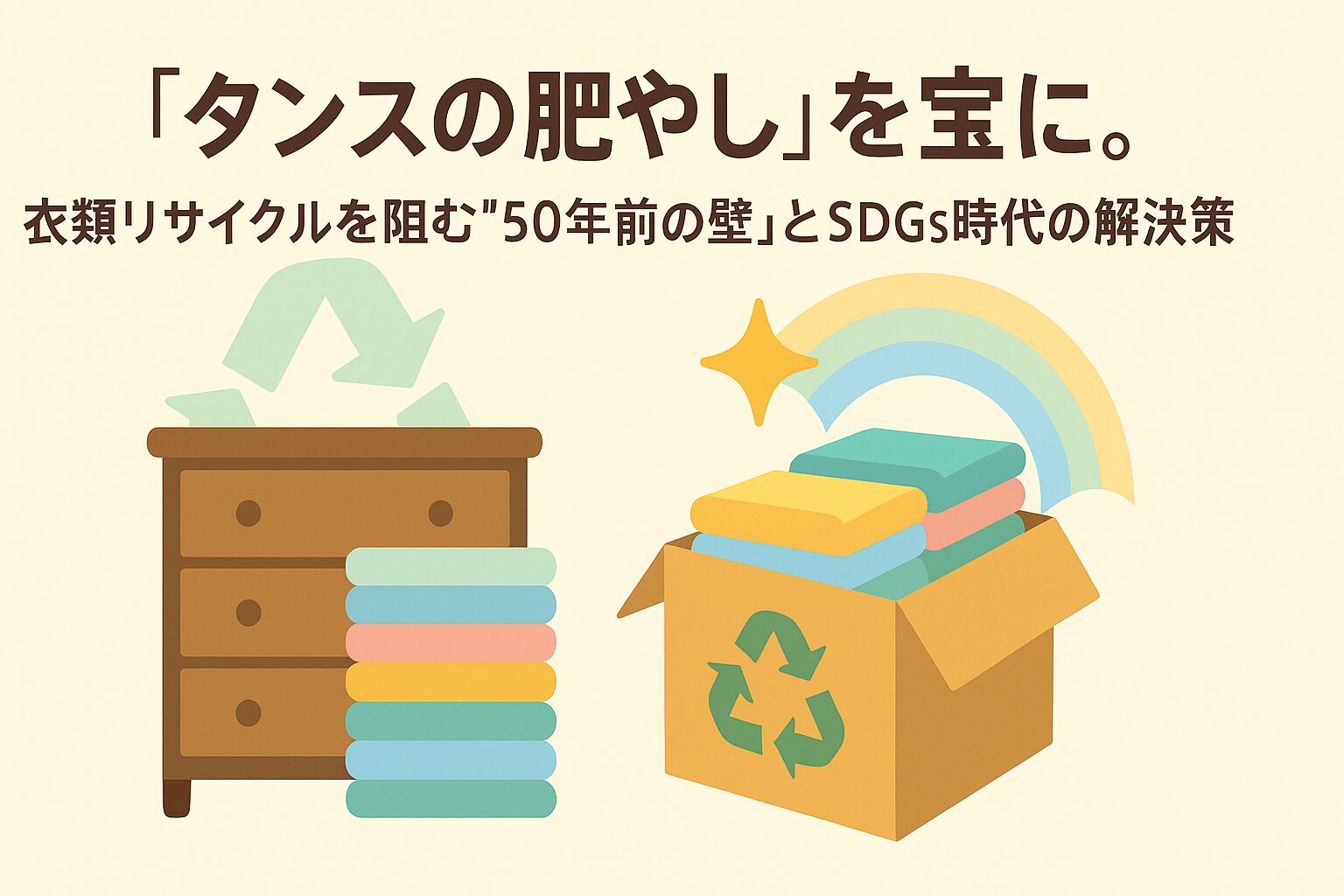
コメント