こんな人にオススメです
- 企業の経営者や人事、管理職の方
- 女性の健康課題と仕事の両立に関心がある方
- SDGs(持続可能な開発目標)、特にジェンダー平等や健康、働きがいについて考えたい方
- すべての人が働きやすい職場環境をどう作るか、ヒントを探している方
「もし、自分にも生理痛があったら…?」——考えたことはありますか?
10月19日の「国際生理デー」を前に、東京・渋谷でまさにその問いを体験できるイベントが開かれました。生理や更年期など、女性特有の健康課題は、長らく個人の問題として片付けられがちでした。しかし、今やそれは社会全体で向き合うべき大切なテーマです。今回はこのニュースをきっかけに、すべての人が輝ける職場づくりをSDGsの視点から考えてみましょう。
最新のSDGsニュース:女性の健康課題に向き合う職場づくりとは イベント開催
【出典】 日テレNEWS NNN:今月19日は「国際生理デー」 女性の健康課題に向き合う職場作りとは
SDGsニュースの要約
10月19日の「国際生理デー」を前に、15日に東京・渋谷で、企業の経営者や人事担当者ら約100人を対象にしたトークイベントが開催されました。このイベントは、生理や更年期障害などの健康課題を抱える女性が働きやすい職場環境について考えることを目的としています。登壇した産婦人科医の郡詩織医師は、特に管理職年代の女性を悩ませる更年期障害について言及。うつ病や関節痛など心身に大きな影響があるものの、治療によって改善が可能だとし、企業に対して「退職を促すのではなくサポートすることが大事だ」と訴えました。また、会場には生理痛を疑似体験できるブースも設置され、体験した男性からは「憂鬱になる。仕事は無理だ」といった声が上がりました。
SDGsニュースのポイント
このイベントから見えてきた、職場における重要なポイントを整理してみましょう。
- 管理職世代を襲う「更年期」という課題: 更年期障害は、うつ病や関節痛など心身に大きな影響を及ぼし、特に会社の重要な役割を担う年代の女性が直面する悩みです。
- 企業の役割は「退職勧奨」ではなく「サポート」: 郡医師は、更年期の症状は治療で改善できると指摘。経験豊富な人材を失わないためにも、企業には正しい知識を持ち、従業員を支える姿勢が求められます。
- 「知る」ことが支援の第一歩: 女性ホルモンの変化は避けられませんが、正しい知識を持つことで心身の健康を保つことは可能です。会社側が従業員の身体について理解しようとすることが、支えるきっかけになります。
- 「体験」がもたらすリアルな共感: 生理痛の疑似体験をした男性から「仕事は無理だ」という声が聞かれたように、知識だけでなく、痛みを想像してみることが、当事者への深い理解と共感に繋がります。
SDGsニュースを考察
この取り組みは、SDGsが目指す持続可能な社会の実現と、非常に深く結びついています。
SDGs 5「ジェンダー平等を実現しよう」
女性が健康課題を理由にキャリアを諦めたり、能力を十分に発揮できなかったりする状況は、まさにジェンダーギャップの一因です。特に、管理職世代が更年期によって離職を余儀なくされることは、組織の意思決定層における女性比率の向上(ターゲット5.5)を妨げます。企業が女性の健康をサポートすることは、単なる福利厚生ではなく、ジェンダー平等を達成するための経営戦略そのものなのです。
SDGs 3「すべての人に健康と福祉を」 & SDGs 8「働きがいも経済成長も」
従業員の心身の健康は、企業の生産性に直結します。今回のイベントで訴えられたように、正しい知識を提供し、必要な時に治療を受けやすい環境を整えることは、SDGs 3「すべての人に健康と福祉を」に貢献します。そして、健康で安心して働ける職場は、従業員のエンゲージメントを高め、SDGs 8「働きがいも経済成長も」に繋がります。経験豊富な女性管理職が健康問題で離職することは、企業にとって大きな損失です。彼女たちをサポートすることは、健康経営の観点からも極めて重要です。
このイベントは、女性の健康課題が「個人の我慢」ではなく「組織の課題」であり、その解決がより良い社会と企業の成長に繋がることを明確に示してくれました。
私たちにできること
このニュースを受けて、明日から職場でできることを考えてみましょう。
- まずは「知る」ことから始めよう: 性別に関わらず、生理や更年期について正しい知識を学ぶ機会を持ちましょう。会社としてセミナーを開催したり、情報提供を行うことが第一歩です。
- 話せる雰囲気をつくる: 体調が悪い時に「言い出しにくい」という空気が、問題を深刻にします。日頃からお互いの健康を気遣い、必要なときには気兼ねなく相談できるオープンな職場文化を育むことが大切です。
- 制度を整え、活用しやすくする: フレックスタイムや休暇制度など、体調に合わせて働き方を調整できる制度を整えましょう。そして、誰もが気兼ねなくその制度を使えるよう、管理職が積極的に利用を促すことも重要です。
- 想像力を働かせる: 生理痛体験ブースのように、直接体験できなくても「もし自分がその立場だったら」と想像することが、思いやりのある行動に繋がります。「大変そうだね」の一言が、当事者の心の支えになるかもしれません。
一人ひとりの意識と会社の仕組み、その両輪が揃って初めて、誰もが健康で自分らしく働き続けられる社会が実現します。このイベントをきっかけに、あなたの職場でも話し合ってみませんか?
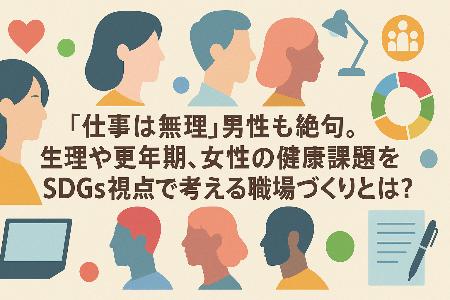
コメント