こんな人にオススメです
- 地域のメガソーラー開発に不安を感じている方
- 再生可能エネルギーが抱える課題や問題点について知りたい方
- 住民が主体となった環境保護活動の成功事例に興味がある方
- SDGsにおける「エネルギー」と「環境保全」の両立について考えたい方
クリーンなエネルギーとして注目される太陽光発電。でも、その裏で進む山林の乱開発が、私たちの暮らしや安全を脅かすとしたら…? 静岡県函南町で、東京ドーム約13個分もの巨大なメガソーラー計画を住民の力で阻止した、というニュースが話題です。感情論だけではない、冷静な戦略で大きな計画を止めた『戦い方』から、私たちが地域と自然を守るために何ができるのか、そのヒントを探ってみましょう。
最新のSDGsニュース:静岡県函南町「東京ドーム13個分のメガソーラー」を事業中止に追い込んだ元警視が語る、計画阻止への戦い方
(ソース:JBpress 2025年10月15日)
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/91101
SDGsニュースの要約
静岡県函南町で計画されていた、東京ドーム約13個分にもなる巨大な太陽光発電(メガソーラー)事業が、住民たちの活動によって正式に中止に追い込まれました。中心となったのは、元大阪府警警視の山口雅之氏。山口氏らは、ただ感情的に反対するのではなく、情報公開請求などを通じて事業の許可申請書類を徹底的に調査。その結果、土砂災害や水害を防ぐために不可欠な行政手続きである「河川協議」が適切に行われていないという『重大な問題』を発見しました。この法的な不備を指摘したことが決定打となり、県議会も動いて事業者は撤退を決定。全国的にも珍しい、住民側が計画を阻止した成功事例として注目されています。
SDGsニュースのポイント
この「函南町の勝利」は、決して奇跡ではありませんでした。そこには緻密な戦略と、私たちの生活にも応用できる大切なポイントが詰まっています。
- 住民の力で巨大計画をストップ!:静岡県函南町で、約65ha(東京ドーム約13個分)のメガソーラー計画が住民の反対運動で中止に追い込まれました。
- 成功のカギは「感情論より法律」:「景観が悪い」「自然が心配」という想いも大切ですが、それだけでは巨大事業は止まりません。中心人物の山口氏は、行政手続きの法的な不備を徹底的に調べ上げました。
- 見つけた「重大な問題」:計画の許可手続きの中で、土砂災害や洪水を防ぐための最も重要な事前協議(河川協議)が、実質的に行われていなかったことを突き止めました。
- 情報公開が武器になる:住民側は、県や町に情報公開請求を行い、事業者が提出した申請書類を入手。法律と照らし合わせることで、この決定的な不備を発見しました。
- 全国的なうねりを起こす:この問題を函南町だけのものとせず、全国の仲間と連携。メディアや国会議員にも働きかけ、再エネ政策全体の問題として提起したことも大きな力になりました。
- 今後の対策①「地域のルール(条例)を作る」:山口氏は対策として、太陽光事業に「市町村長の同意」を義務付ける条例作りを提案しています。同意がなければ国の売電許可が下りなくなり、事業者は無視できません。
- 今後の対策②「法律の矛盾を正す」:土砂災害を防ぐ法律(砂防法)で危険とされる「砂防指定地」の中でも、森林法では開発が許可できてしまうという、法律間の矛盾の改正も訴えています。
- 「一人で戦わない」心構え:反対運動には嫌がらせなども伴う危険性があります。山口氏は、事業者とのやり取りは全て録音し、仲間と共有し、早めに警察に相談することの重要性を説いています。
SDGsニュースを考察
今回のニュースは、SDGsを考える上で非常に重要な視点を与えてくれます。それは、各目標間の「トレードオフ(一方を立てれば他方が立たない関係)」と、住民が主体となることの重要性です。
この問題は、目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の推進が、目標11「住み続けられるまちづくりを」(安全な暮らし)や目標15「陸の豊かさも守ろう」(生物多様性の保全)を脅かしかねない、という典型的な事例です。クリーンであるはずの再生可能エネルギー開発も、やり方を間違えれば地域の持続可能性を破壊してしまう危険性をはらんでいます。
SDGsの達成は、単に一つの目標だけを追いかければ良いというものではありません。エネルギー、環境、安全な暮らし、これら全てのバランスをどう取るか。函南町の事例は、その答えを「地域住民自身が考え、行動すること」の中に見出しました。
彼らは、感情論に流されず、法律や制度という共通のルールの上で行政や事業者と向き合いました。これは、目標16「平和と公正をすべての人に」の実践とも言えるでしょう。行政手続きの誤りを正し、住民の安全な暮らしを守ったこの活動は、全国で同様の問題に悩む人々にとって大きな希望となります。
私たちにできること
「自分の町にもし同じ計画が持ち上がったら…?」決して他人事ではありません。このニュースから、私たちが学べる具体的なアクションはたくさんあります。
- 自分の住む地域の開発計画に関心を持つ:まずは、自分の町で何が起きているかを知ることから。自治体の広報誌やウェブサイトをチェックし、大規模な開発計画がないかアンテナを張っておきましょう。「いつの間にか決まっていた」を防ぐことが第一歩です。
- 「なぜ?」と問い、調べてみる:もし疑問に思う計画があれば、役場の担当課に電話で質問したり、情報公開請求をしてみましょう。情報公開請求は、誰でも使える強力な権利です。
- 地域の議員に声を届ける:議会は住民の代表です。地域の課題について、地元の町議会議員や県議会議員に「こんな計画があるが、安全性は大丈夫でしょうか?」と意見を伝え、相談することも非常に有効な手段です。
- 再生可能エネルギーの「光と影」を学ぶ:再エネは脱炭素に不可欠ですが、様々な課題も抱えています。一つの側面だけでなく、多角的に情報を集め、自分なりの考えを持つことが、より良い未来の選択につながります。
- 地域の活動に参加・応援する:もし地域の環境を守るために活動している団体があれば、会合に参加してみたり、SNSで情報をシェアしたり、寄付をしたり…。自分のできる範囲で応援することも、私たちにできる具体的なアクションです。
地域と自然の未来は、誰かが与えてくれるものではなく、私たち自身の手で守り、作っていくもの。函南町の事例は、そのことを力強く教えてくれています。
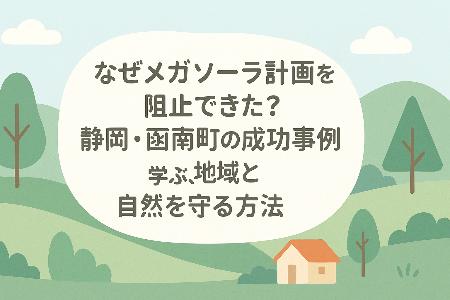
コメント