皆さん、こんにちは!脱炭素とSDGsの知恵袋、日野広大です。もうすぐ母の日ですね。感謝の気持ちを込めてカーネーションを贈る方も多いのではないでしょうか?しかし、そのカーネーションが今、ちょっとしたピンチを迎えているというニュース、ご存知でしたか?昨年の夏の猛暑が、今年のカーネーション栽培に大きな影を落としているんです。これは、SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」や目標12「つくる責任つかう責任」にも深く関わる、私たち自身の生活にもつながるお話です。
最新のSDGsニュース:
昨夏の猛暑の影響がいまだに…母の日を前にカーネーションに異変 出荷が最盛期を迎えるもつぼみが目立ち生産者も嘆き (出典: テレビ静岡 – 2025年4月23日 / URL: https://www.fnn.jp/articles/-/861236)
SDGsニュースの要約
静岡県河津町と東伊豆町は、県内カーネーション生産量の約9割を占める一大産地です。しかし、母の日を前に出荷最盛期を迎える中、昨夏の記録的な猛暑の影響がいまだに残り、生産者を悩ませています。猛暑によって植えた苗が弱り、成長が大幅に遅れているため、例年なら開花している時期にも関わらず、つぼみの状態の株が目立つのだとか。さらに、夏場に根が傷んだことで病気にかかりやすくなり、枯れてしまうケースも増えているそうです。追い打ちをかけるように、原油高や物価高騰でハウス栽培に必要な燃料費や肥料、農薬などのコストも急上昇。半世紀以上カーネーションを育てるベテラン生産者も「本当に大変」と嘆いています。県の研究機関も、暑さに強い品種開発や遮光技術など、気候変動に対応する新たな栽培技術の開発に取り組んでいますが、生産者にとっては厳しい状況が続いています。
SDGsニュースのポイント
このニュース、私たちの生活にどう関わってくるのでしょうか?ポイントをまとめてみました。
- 異常気象の爪痕: 昨夏の猛暑の影響で、カーネーションの苗がダメージを受け、成長が大幅に遅れています。「かわづカーネーション見本園」では、例年12月〜1月に咲く花がまだ咲いていないという異常事態。これは栽培管理者も「初めて」と語るほどです。
- 開花遅れと収量減: 出荷最盛期にも関わらず、つぼみが目立ちます。これは見た目の問題だけでなく、収穫量の減少に直結します。生産者の山田さんも「夏場に根がやられた」と語っています。
- 病気の増加: 暑さで弱った株は病気にもかかりやすくなります。ベテラン生産者の吉田さんのハウスでも、ここ1ヶ月ほどの暖かさで枯れる株が増えてしまったそうです。これも収量減の大きな要因ですね。
- コスト増のダブルパンチ: 異常気象に加えて、原油価格の高騰が経営を直撃。吉田さんが栽培を始めた53年前、1リットル25円だったA重油は今や118円と4倍以上に。暖房を一晩使うだけで500〜600リットルも消費するため、大きな負担となっています。
- 資材費も高騰: 燃料だけでなく、ビニールハウスの資材、肥料、農薬なども軒並み値上がりしており、生産コスト全体が上昇しています。
- 産地の苦悩: 河津町と東伊豆町は、静岡県内カーネーション生産量の約9割を占める重要な産地。多い日には首都圏へ4〜5万本を出荷するだけに、この影響は小さくありません。
- 品種改良への期待: 生産者は、夏の暑さや病気に強い品種を選ぶことが今後ますます重要になると考えています。まさに**気候変動への「適応」**が求められている状況ですね。
- 技術開発の必要性: 静岡県伊豆農業研究センターでは、夏の暑さを和らげる遮光技術や、猛暑の時期を避ける新たな栽培スケジュール(作型)の開発など、具体的な対策に取り組んでいます。
- すぐには解決しない問題: 異常気象が「日常」になりつつある中、即効性のある解決策はまだ見つかっていません。生産者にとっては我慢の時が続きそうです。
- 母の日への影響: この状況は、私たちが母の日に贈るカーネーションの価格や供給量にも影響を与える可能性があります。
SDGsニュースを考察
今回のニュースは、**気候変動(SDGs 13)**の影響が、食料だけでなく、私たちの心に彩りを与えてくれる「花」の生産にも深刻なダメージを与えていることを示していますね。昨年の猛暑という「異常」が、今年の収穫にまで影響を及ぼしている。まさに「異常気象が異常でなくなる」時代の現実を突きつけられた形です。
カーネーション農家の方々が直面しているのは、単なる天候不順ではありません。気温上昇という地球規模の課題に加え、**エネルギー価格の高騰(SDGs 7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに)や物価上昇(SDGs 8 働きがいも経済成長も)**という経済的な問題が複合的に絡み合っています。ハウス栽培は温度管理が重要ですが、そのための燃料費が経営を圧迫する…これは、化石燃料に依存した社会構造の脆弱性を示しているとも言えるでしょう。
生産者の方々や研究機関が、暑さに強い品種を選んだり、新しい栽培技術を開発したりと努力されているのは素晴らしいことです。これは気候変動に対する「適応策」として非常に重要です。しかし、同時に、気候変動そのものを食い止める「緩和策」、つまり温室効果ガスの排出削減に向けた社会全体の取り組みも加速させなければ、根本的な解決にはなりません。
また、**SDGs 12「つくる責任 つかう責任」**の観点も重要です。私たちは、美しい花がどのように育てられ、どんな苦労を経て届けられているのかを知る必要があります。そして、購入した花を大切に扱い、「フラワーロス」を減らすことも、生産者の方々への間接的な支援になります。
私たちにできること
「じゃあ、私たちに何ができるの?」と思いますよね。難しく考える必要はありません。身近なところからできることがあります。
- 地元の花や旬の花を選ぶ: 輸送エネルギーが少なく、環境負荷が比較的小さい地元の花や、その時期に自然な形で咲く花を選ぶのも一つの方法です。母の日のカーネーションも、できるだけ国産や近隣県産のものを選ぶと、国内の生産者さんの応援につながります。
- 花を大切に、長く楽しむ: 購入した花は、水替えをこまめにするなど、少しでも長く楽しめるように工夫しましょう。枯れてしまった後も、ドライフラワーにするなど、最後まで楽しむ方法を探してみるのも良いですね。
- 気候変動に関心を持つ: なぜ異常気象が起こるのか、私たちの生活とどう繋がっているのか、少しで良いので関心を持ってみませんか?省エネを心がける、再生可能エネルギーに関心を持つなど、日々の小さな選択が未来を変える力になります。
- 生産者の声を知る: 今回のようなニュースを通じて、食料や花の生産現場が抱える課題を知ることも大切です。背景を知ることで、モノへの感謝の気持ちも深まるのではないでしょうか。
母の日に贈るカーネーション。その一輪一輪に、生産者の方々の苦労と努力、そして気候変動という大きな課題が込められています。感謝の気持ちを伝えるとともに、その背景にあるストーリーにも少しだけ思いを馳せてみませんか? 私たち一人ひとりの小さな意識の変化が、美しい花を守り、持続可能な社会をつくるための一歩になるはずです。
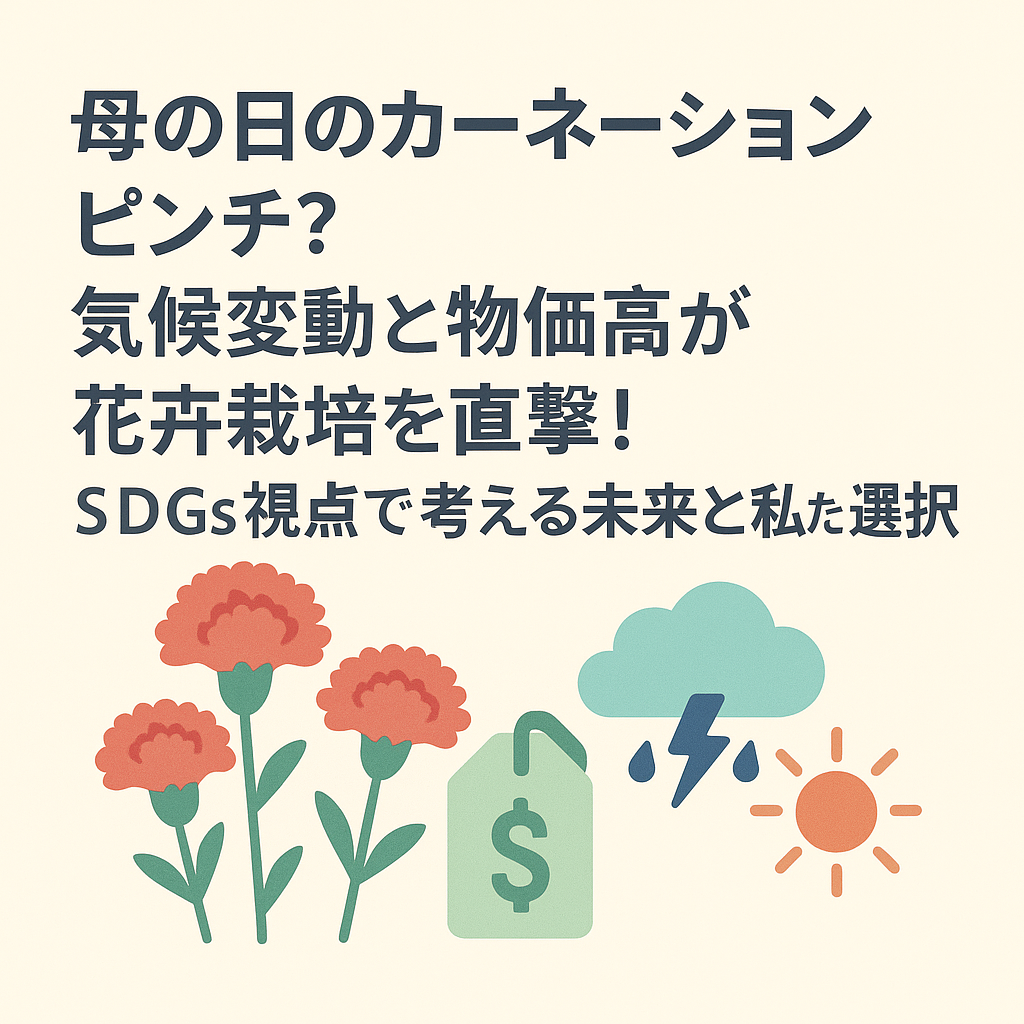
コメント