私たちの身の回り、特に海や飲料水、食塩などに微細なプラスチック粒子「マイクロプラスチック」が存在し、環境や健康への影響が懸念されています。この深刻化する問題に対し、ノースカロライナ州立大学の研究グループが画期的な解決策を発表しました(2025年3月25日付、Advanced Functional Materials)。
それは、水に入れるだけでマイクロプラスチックを捕獲し、最終的には水面に浮かんで回収できる「マイクロクリーナー」と呼ばれる新技術です。この記事では、この注目のマイクロクリーナーの仕組みと、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献について解説します。
マイクロプラスチック問題とは?
まずは、問題の背景となるマイクロプラスチックについて確認しましょう。
マイクロプラスチック (Microplastics) とは、一般的に5mm以下の微細なプラスチック粒子のことを指します。ペットボトルやレジ袋などが紫外線や波の力で劣化して細かくなったもの(二次マイクロプラスチック)や、洗顔料のスクラブ剤や歯磨き粉などに意図的に添加された粒子(一次マイクロプラスチック)があります。これらは自然界で分解されにくく、海洋生物が誤食するなど生態系への影響が懸念されています。
新技術「マイクロクリーナー」の概要
今回開発された「マイクロクリーナー」は、この厄介なマイクロプラスチック問題を解決する可能性を秘めた技術です。
- 簡単な使用法: 水にポンと入れるだけ。
- 自動的な拡散: クリーナー自体が水面を動き回り、水中に有効成分を散布。
- 効率的な吸着: 特殊な構造と性質でマイクロプラスチックを捕獲。
- 容易な回収: 最終的にマイクロプラスチックごと水面に浮上。
まさに「入れて、待って、すくい取る」だけで、水中のマイクロプラスチックを除去できるという画期的なものです。
マイクロクリーナーの主役:キチン由来の「SDC」
このマイクロクリーナーの”核”となっているのは、自然由来の素材から作られた特殊な粒子です。
軟質樹枝状コロイド (Soft Dendritic Colloid, SDC) と呼ばれる、細かく枝分かれした構造を持つ粒子です。これは、カニやエビの殻、貝殻などに含まれる天然の生分解性ポリマーである「キチン (Chitin)」を加工して作られる「キトサン (Chitosan)」を原料としています。
- 原料の持続可能性: 貝類の加工廃棄物など、未利用資源を有効活用できる可能性があります。
- 環境安全性: キトサンは生分解性があり、環境に優しい素材です。
どうやってマイクロプラスチックを捕まえる? – 2つの力
SDCがマイクロプラスチックを捕まえる仕組みには、主に2つの力が関わっています。
- ファンデルワールス力 (Van der Waals force):
分子と分子の間に働く、非常に弱い引き合う力のことです。SDCの細かく分岐した構造は表面積が大きく、ヤモリが壁に貼り付くのと同じように、この力でマイクロプラスチックを物理的に吸着(かき集める)ことができます。
- 静電気力:
キチン(キトサン)はわずかにプラス(+)に帯電しています。一方、多くのマイクロプラスチックは水中でマイナス(-)に帯電する傾向があります。そのため、磁石のようにプラスとマイナスが引き合い、静電気力によってマイクロプラスチックを効果的に吸着します。
どうやって水中に散布し、回収する? – 賢い仕組み
マイクロクリーナーは、ただマイクロプラスチックを吸着するだけではありません。効率的に散布し、容易に回収するための工夫が凝らされています。
- 自己分散機能(マランゴニ効果):
- マイクロクリーナーは、乾燥させて小さなペレット状になっています。
- ペレットの一部に植物由来のオイル(オイゲノール)が塗布されています。
- これが水に触れると、オイルが溶け出してペレット周辺の水の表面張力を低下させます。
- 表面張力の差によってペレットが水面を自走し(マランゴニ効果、または樟脳船効果)、移動しながら水中にSDCを効果的に散布します。
マランゴニ効果 (Marangoni effect) とは、液体の表面張力が場所によって異なる場合に、表面張力が高い方から低い方へ液体が流れる現象です。樟脳(しょうのう)の粒を水に浮かべると動き回る「樟脳船」と同じ原理です。
- 自己浮上機能:
- SDCには、ゼラチンでコーティングされたマグネシウムの粒子が混ぜられています。
- マイクロプラスチックを吸着したSDCは、いったん水底に沈みます。
- 時間が経つとゼラチンがゆっくり溶け、内部のマグネシウムが水と反応して水素の微細な気泡を発生させます。
- この気泡が浮力となり、マイクロプラスチックを吸着したSDCを水面まで押し上げるのです。
これにより、利用者は特別な装置なしに、浮かんできたマイクロクリーナーの塊を回収するだけで済みます。
実証と今後の展望
研究チームは、ハワイのカミロビーチ(プラスチックごみが大量に漂着することで知られる)で採取した実際の海水を用いて、このマイクロクリーナーが様々な種類のマイクロプラスチックを効果的に除去できることを実証しました。
さらに、回収したマイクロクリーナー(キトサンとマイクロプラスチックの混合物)を処理して再びキトサンを抽出し、新たなマイクロクリーナーを生産するという、リサイクル・ループの構想も持っています。これが実現すれば、より持続可能な除去システムとなります。
SDGsへの貢献 – 特に目標14「海の豊かさを守ろう」
マイクロプラスチックによる海洋汚染は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも特に**目標14「海の豊かさを守ろう」**に対する深刻な脅威です。
- 目標14.1: 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
マイクロクリーナー技術は、この目標達成に直接的に貢献する可能性を秘めています。自然由来で生分解性の素材を用い、効率的にマイクロプラスチックを除去・回収するこの技術は、海洋環境の保全に貢献する革新的なアプローチと言えるでしょう。
まとめ:未来の海を守る新技術への期待
水に入れるだけでマイクロプラスチックを自動的に除去し、簡単に回収できる「マイクロクリーナー」。この技術は、キチン・キトサンという自然由来の素材と、ファンデルワールス力やマランゴニ効果といった科学の原理を巧みに組み合わせることで実現されました。
まだ研究開発段階ではありますが、海洋プラスチック問題という地球規模の課題に対する有望な解決策の一つとして、大きな期待が寄せられます。今後の実用化と普及、そしてリサイクル技術の確立により、豊かな海を未来世代に引き継ぐための強力なツールとなることが望まれます。
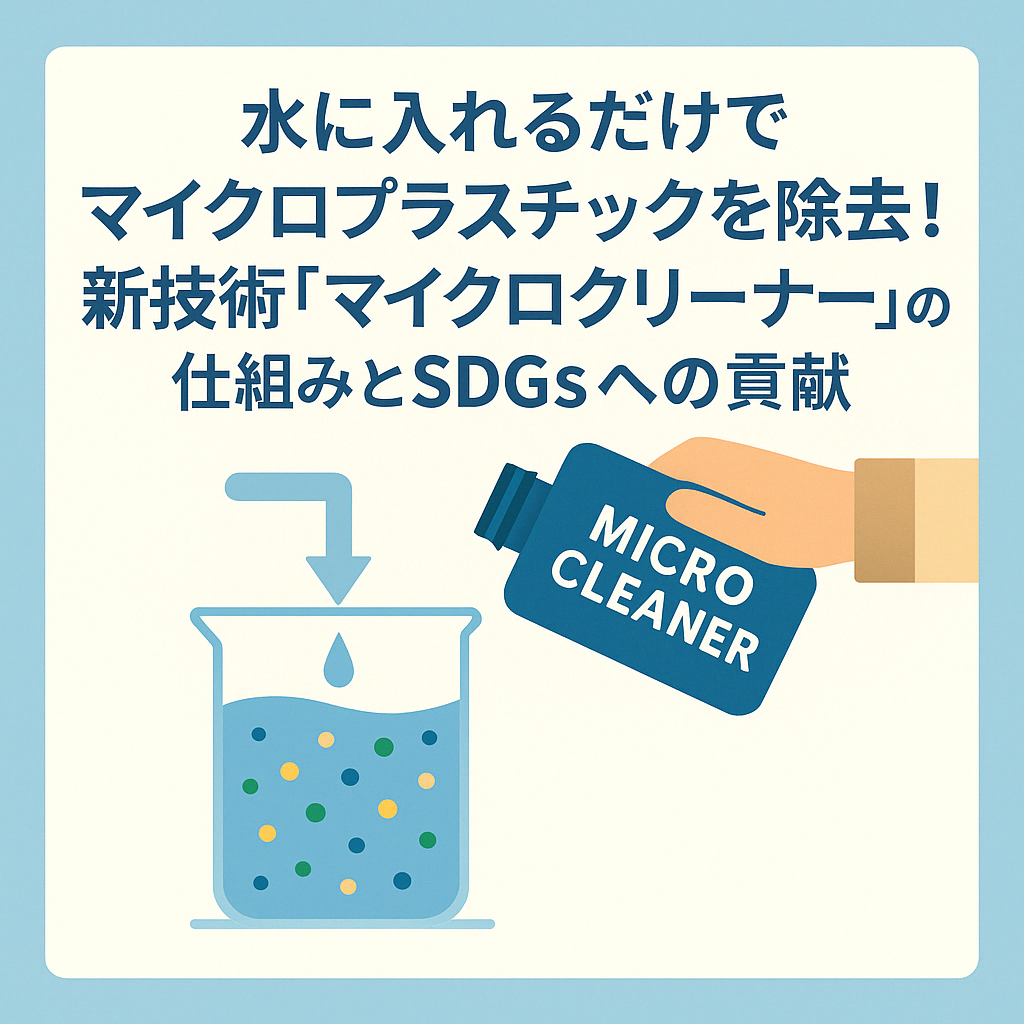
コメント