こんにちは、「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。
今日取り上げるのは、シリコンバレーの著名な投資家であり、「資本主義のアイコン」とも言えるピーター・ティール氏による、非常に衝撃的な発言です。
彼は「資本主義は若者のために機能していない」と断言し、このままでは「若者が共産主義者になっても驚くべきではない」 とまで警告しています。
これは単なる経済評論ではなく、【用語解説】SDGsとは?17のゴールと169のターゲットを徹底解説! が目指す「持続可能な社会」の根幹である「世代間の公平性」が、まさに脅かされているというサインです。
こんな人におすすめです
- 奨学金(学生ローン)の返済に負担を感じている方
- 住宅価格が高すぎて、将来マイホームを持てる気がしない方
- 「世代間格差」という言葉にモヤモヤしている方
- SDGsと経済システムの「不平等」の関係を知りたい方
なぜ若者は「共産主義者」になるのか?
ティール氏が指摘する「世代間対立」 の要因は、主に2つあります。
1. 学生ローンという「負債」
ティール氏は、1970年に借金ゼロで大学を卒業できた世代と、現代のミレニアル世代を比較します。現代では、あまりにも多くの人が大学に行き、「何も学ばず」、「信じられないほど大きな借金」を背負わされている と指摘します。
これは SDGs 4(質の高い教育をみんなに) の歪みです。教育が機会の平等を生むどころか、スタートラインで「負債」という名の格差を生み出しているのです。
2. 住宅という「資産」
さらに深刻なのが不動産問題です。ティール氏は、経済問題の80%は不動産問題だ と述べます。
「非常に厳格なゾーニング法(建築規制)があれば、それはブーマー世代にとっては良いことだ。彼らの資産価値は上がり続けるから。しかし、ミレニアル世代にとっては最悪だ」
これは SDGs 11(住み続けられるまちづくりを) の課題です。サステナビリティの都市計画: 11-3. 包摂的かつ持続可能な都市化の促進 が目指す「包摂的(誰も排除しない)」な都市とは逆行し、既存の資産を持つ世代が、ルール(規制)によって若者世代の参入を阻んでいる構図です。
はい、前の会話で出た「ゾーニング法」ですね。これは【用語解説】SDGsとは?17のゴールと169のターゲットを徹底解説! の中でも、特に**目標11「住み続けられるまちづくりを」**に深く関わる都市計画のルールです。
アメリカと日本では、その考え方や運用に大きな違いがあります。
🇺🇸 アメリカのゾーニング法:厳格な「用途分離」
アメリカのゾーニング法は、「ユーグリッド・ゾーニング」と呼ばれる、土地の用途(使い方)を厳格に分ける方法が主流です。
- R (Residential): 住宅地
- C (Commercial): 商業地
- M (Manufacturing): 工業地
このように明確に分類し、例えば「R1(一戸建て住宅専用地域)」と指定された場所には、基本的に一戸建て住宅しか建てられません。スーパーマーケットはもちろん、小さなコンビニやアパート(集合住宅)すら建てられないことが多いのです。
🏡 ピーター・ティール氏の指摘との関連
この厳格さが、ピーター・ティール氏が指摘した問題につながっています。
問題点: 郊外の広大な土地が「敷地規模の大きな一戸建て住宅のみ」に制限される と、新しい住宅(特に手頃な価格のアパートや複合住宅)の供給が物理的に難しくなります。
結果: 住宅の供給が絞られるため、需要が供給を上回り、既存の住宅価格(資産価値)が高騰しやすくなるのです。
🇯🇵 日本のゾーニング法:比較的緩やかな「混在」
一方、日本の場合は、都市計画法に基づいて全国で統一された「用途地域」というルールを使います。
こちらは全部で13種類あり、アメリカと比べて「用途の混在」に比較的寛容なのが大きな特徴です。
13種類の用途地域
大きく分けて以下の3系統ですが、その中が細かく分かれています。
- 住居系 (8種類):
- 例:「第一種低層住居専用地域」
- 最も規制が厳しい閑静な住宅街ですが、小規模な(自宅兼)店舗や診療所は建てられます。
- 例:「第二種低層住居専用地域」
- 「第一種」と似ていますが、床面積150㎡までのコンビニなどが建てられます。
- 例:「第二種住居地域」
- 住宅地ですが、ショッピングセンターやボーリング場、パチンコ店なども(一定の規模まで)建てることが可能です。
- 例:「第一種低層住居専用地域」
- 商業系 (2種類):
- 例:「近隣商業地域」「商業地域」
- 工業系 (3種類):
- 例:「工業地域」「工業専用地域」
建物もセットで規制
日本では用途(使い方)だけでなく、建物の形態(大きさや高さ)も同時に規制します。
- 建ぺい率: 敷地面積に対する建築面積(上から見た広さ)の割合。
- 容積率: 敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合。
このため、日本はアメリカの都市に比べて、住宅地の近くにコンビニやスーパーがあったり、商業地の中にマンションが建っていたりする「職住近接」が実現しやすい側面があります。
SDGsの視点:「世代間公平性」の崩壊
ティール氏の分析は、SDGsの根幹にある「世代間公平性(Intergenerational Equity)」が崩壊していることを示しています。
サステナビリティ(持続可能性)とは、「未来の世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと」です。
しかし、今のシステムはどうでしょうか。
- 教育(SDGs 4): 未来の世代に「スキル」ではなく「借金」を渡している。
- 都市(SDGs 11): 未来の世代に「住む場所」ではなく「高騰した資産」を見せつけている。
これらはすべて、SDGs 10(人や国の不平等をなくそう) で解決すべき「不平等」です。SDGs「10-3. 機会均等の確保、成果の不平等の是正」 が言う「機会均等」は、世代間においても担保されなければなりません。
ティール氏の「若者を労働者階級化(proletarianize)する」 という強い言葉は、資産を持つ世代と持たざる世代への固定化・分断を意味しており、まさにSDGs 10が警鐘を鳴らす事態そのものです。
日野広大の視点:社会契約が破綻する時
私がこのニュースで最も重要だと感じるのは、ティール氏の「共産主義者になっても驚かない」 という最後の警告です。
これはイデオロギーの話ではなく、「社会契約(Social Contract)」の話です。
人々(特に若者)が、「真面目に働いても、教育を受けても、借金まみれになり、家一つ買えない」と感じた時、彼らはその「資本主義」や「民主主義」というシステム自体を信頼しなくなります。
「世代間の約束(compact)」が破られた と感じた時、人々はより過激な思想(それが共産主義であれ何であれ)に惹かれてしまう。これは、SDGs 16(平和と公正をすべての人に) が目指す「公正で強靭な制度」が、内側から崩壊していくプロセスです。
私たちにできること:ルールの見直しを
ティール氏の警告 は、資本主義そのものを否定するものではなく、「現在のルール設定が歪んでいる」という指摘です。
- 知ること: まず、学生ローンの問題や、都市の建築規制が、単なる「市場原理」ではなく「政治的なルール選択」の結果であることを知るのが第一歩です。
- スキルへの投資: 企業も、【用語解説】サステナビリティ経営とは?持続可能な社会に向けた企業の取り組み の一環として、若者世代の技術的・職業的スキル強化(借金を負わせない形での教育)にもっと投資すべきです。
- 議論すること: 私たちの社会は、未来の世代の「住む権利」や「学ぶ権利」を犠t牲にしてまで、現在の資産価値を守るべきなのでしょうか。
この「世代間の公平性」こそ、脱炭素問題と並ぶ、最も重要なSDGsのテーマの一つだと、私は考えます。
どちら国の制度も、SDGs 11が目指す「包摂的(誰も排除せず)かつ持続可能な都市化」 の観点から見直しが議論されています。
アメリカでは厳しすぎる規制を緩和する動きがあり、日本では人口減少社会に合わせて、より効率的な都市機能を持つスマートシティへの転換が求められています。
さらに詳しい都市計画の考え方については、こちらの記事も参考になるかと思います。
これらの都市ルールが、私たちの生活や経済格差に直結しているというのが、ピーター・ティール氏の指摘の核心ですね。
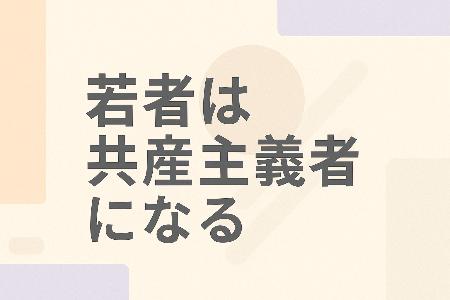
コメント