「オカン、今見てんのか?俺やったぞ!」
2025年の夏、多くの国民が見守った「SUPER EIGHT」横山裕さんの105キロマラソン。そのゴールの瞬間の言葉に、彼の壮絶な人生を知り、涙した人は少なくないでしょう。私もその一人です。しかし、その涙が乾いた後、私たちは思考を止めてはいけません。
この物語を、一個人の類まれな精神力と兄弟愛の「美談」として感動だけで終わらせてしまうことは、あまりにもったいなく、そして少し無責任でさえあるかもしれない。なぜなら、彼の道のりは、この日本社会が抱える構造的な課題——「見えない貧困」「ヤングケアラー」「子どもの権利の軽視」——を、あまりにも鮮烈に映し出しているからです。
今回は、彼の走りが私たちに突きつけたこの重い問いを、SDGs(持続可能な開発目標)という羅針盤を手に、深く掘り下げていきたいと思います。
こんな人のための記事です
- 横山さんのマラソンを見て、感動の先にある社会課題について考えたい方
- 「ヤングケアラー」や「子どもの貧困」がなぜ生まれるのか、その構造を知りたい方
- 社会を変えるために、具体的で本質的なアクションを知りたい方
「美談」の裏側にある、ヤングケアラーという現実
横山さんは、中学卒業と同時に就職し、病気の母と幼い弟たちを支えました。これは、近年社会問題として認識され始めた「ヤングケアラー」そのものです。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。彼らは、教育を受ける時間や友人との交流、子どもらしい時間を奪われ、心身に大きな負担を抱えがちです。
横山さんの強靭な精神力は計り知れません。しかし、私たちは問うべきです。なぜ、一人の少年の肩に、これほどまでの重荷が託されなければならなかったのか。彼が享受するはずだった「子どもとしての時間」は、誰が保障するべきだったのでしょうか。
これは、SDGs目標1「貧困をなくそう」と目標10「人や国の不平等をなくそう」に直結する課題です。日本の子どもの相対的貧困率(2021年時点で11.5%)は、先進国の中でも依然として高い水準です。貧困は、子どもから学びや経験の機会を奪い、将来の可能性にまで影響を及ぼす「機会の不平等」を生み出します。
守られるべきだった「子どもの権利」
日本も批准している「子どもの権利条約」は、すべての子どもに「生存し、発達し、保護され、参加する権利」を保障しています。経済的な理由で弟たちが児童養護施設に入らざるを得なかった状況は、まさにこの「保護される権利」を行使した結果です。
しかし、その一方で、SNSで「父親の責任」を問う声が多く上がったように、養育費の不払い問題など、子どもを保護するための社会的、法的なセーフティネットが十分に機能していない現実も浮き彫りになりました。
これは、SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」が目指す、「実効的な司法へのアクセス」の課題です。親の離婚や経済状況に関わらず、すべての子どもが健やかに育つ権利を守るための公正な仕組みが、今の日本にはまだ足りていないのです。「個人の頑張り」に依存する社会は、あまりにも脆く、そして時に残酷です。
感動を、社会を変える「力」に変えるために
では、この構造的な問題を前に、私たちは何ができるのでしょうか。
1. 「知る」から「声を上げる」ステージへ
まず、この問題を「特別な誰かの話」ではなく「社会構造の問題」として認識すること。そして、ヤングケアラー支援や子どもの貧困対策について、国や自治体がどのような政策を打ち出しているかに関心を持ちましょう。選挙で投票する際の重要な判断基準になりますし、パブリックコメントなどを通じて市民の声を届けることもできます。
2. 「支える」ことの多様性を知る
子ども食堂や学習支援NPOへの寄付・ボランティアは、直接的な支援として非常に重要です。それに加え、ひとり親家庭を支援する団体の活動に目を向けたり、自らの職場で子育て中の社員が働きやすい制度(時短勤務、急な休みの許容など)を推進したりすることも、間接的に子どもたちを支えることに繋がります。
3. 「助けて」と言いやすい社会文化をつくる
横山さんは「重圧は、一人で背負わない方がいい」と語っています。この言葉が、ただの慰めではなく、現実になる社会を築く必要があります。困難を個人の責任に帰するのではなく、「困ったときはお互い様」と手を差し伸べ、公的な支援に気兼ねなくアクセスできる。そんな文化を、日々のコミュニケーションから育んでいくことが求められます。
まとめ:彼の宿題を、私たちの宿題に
横山裕さんの105キロは、私たちに感動を与えただけでなく、この社会が長年見て見ぬふりをしてきた課題を、真正面から突きつけました。
彼の物語は、私たち社会が彼に、そして彼と同じような境遇にいる多くの子どもたちに負わせた「宿題」でもあります。
この宿題を、「個人の美談」という箱にしまい込み、忘れ去ってしまうのか。それとも、社会全体の課題として受け止め、解答を探し始めるのか。その選択は、今を生きる私たち一人ひとりに委ねられています。「誰一人取り残さない」というSDGsの誓いは、そのための道しるべとなるはずです。
【出典】
- J-CASTニュース「横山裕の『24時間』マラソン、義父の存在に疑問の声『病気の妻と幼い子供置いて』…番組でほぼ触れられず」(2025年9月1日)
- 読売新聞オンライン「横山裕さん、焦り・苦しさあったけど『一人で背負わない方がいい』…STOP自殺 #しんどい君へ」(2021年8月13日)
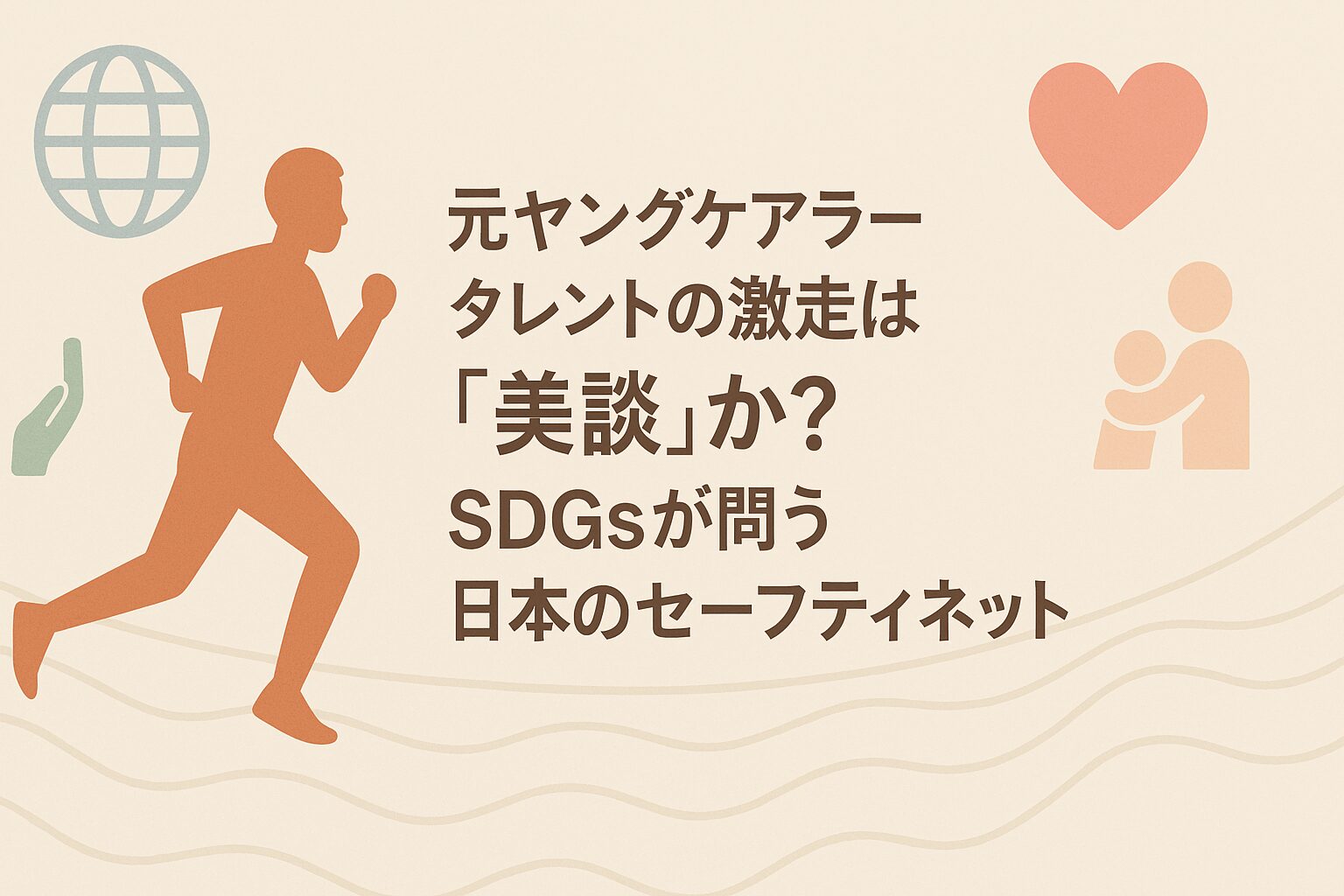
コメント