脱炭素とSDGsの知恵袋、編集長の日野広大です。私たちのメディアは、ジャパンSDGsアワードで外副大臣賞を受賞したFrankPRが運営しており、その知見を基にSDGsに関する信頼性の高い情報を発信しています。
「災害級」とも言われる酷暑が続く日本。この猛烈な暑さは、屋外作業者だけでなく、オフィスで働く人々の健康と生産性をも脅かす深刻な経営課題となっています。そして、「電気代削減のため」といった理由でエアコンの使用を控えた「暑すぎる職場」は、企業の法的責任を問われかねない重大な問題です。
今回は、企業の法的義務と、気候変動時代に適応する先進的な取り組みを、SDGsの視点から徹底的に解説します。
- 法的根拠: なぜ「暑すぎる職場」は法令違反になるのか?
- 客観的指標: 「暑さ指数(WBGT)」の重要性とは?
- 先進事例: 猛暑日に「出社しなくてよい」という新しい働き方
- 具体的対策: 企業が今すぐ取り組むべきこと
「暑すぎる職場」が法令違反になる法的根拠
「従業員の健康より、会社の経費削減が優先」という考えは、もはや通用しません。従業員が安全で健康に働ける環境を整えることは、法律で定められた企業の義務です。
企業の「安全配慮義務」とは
最も重要なのが、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」です。これは、企業が従業員の生命や身体の安全を確保するために、必要な配慮をしなければならないという義務です。
もし、暑すぎる職場環境が原因で従業員が熱中症になった場合、この安全配慮義務に違反したとして、企業が損害賠償責任を負う可能性があります。
具体的な基準を定める法律
さらに、以下の法律や規則が、快適で安全な職場環境の基準を具体的に定めています。
- 労働安全衛生法: 労災を防止し、快適な職場環境を形成するための措置を定めています。
- 事務所衛生基準規則: エアコンなどの空調設備がある場合、室温を18℃以上28℃以下に保つよう努めることが定められています。
つまり、エアコンがあるにも関わらず適切に稼働させず、室温が28℃を大幅に超えるような状態は、これらの法令に違反していると見なされる可能性が高いのです。
客観的な指標「暑さ指数(WBGT)」とは?
では、「暑すぎる」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。その客観的な判断基準となるのが「暑さ指数(WBGT)」です。
WBGTは、気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱などを取り入れた総合的な指標で、熱中症リスクをより正確に評価できます。近年、職場の熱中症による死傷者数は増加傾向にあり、2021年からは3年連続で増加しています。こうした事態を防ぐためにも、WBGT値の計測と管理が推奨されています。
ある企業では、当初は予想最高「気温」を基準にしていましたが、より実態に合った対策とするため、この「暑さ指数」を基準に変更したという事例もあります。これは、科学的根拠に基づいたリスク管理への移行を示す、非常に重要な動きです。
企業の「適応策」:先進事例に学ぶ、新しい働き方
法的義務を果たすことは最低限のラインです。先進的な企業は、この課題を気候変動への「適応策」と捉え、従業員の健康と生産性を両立させる、より積極的な取り組みを始めています。
猛暑日は「出社しなくてOK」という選択肢
スマートフォングッズを開発するある企業では、「熱中症対策リモートワーク推奨デー」を導入しています。これは、暑さ指数が一定の基準に達した場合に、従業員にリモートワークを促すという画期的な制度です。
この取り組みのきっかけは、経営陣が目の前で高齢者が熱中症で倒れるのを目撃し、さらに自社の社員も出勤途中に体調を崩したことでした。従業員からは、「疲れた状態で仕事を始めなくて済む」「効率が上がる」と好評で、実際に制度導入後は熱中症の症状を訴える社員は出ていないといいます。
これは、従業員の健康を守ること(SDGs目標3)が、結果的に企業の生産性を高め、働きがいのある職場環境(SDGs目標8)に繋がることを示す好事例です。
テクノロジーの活用
他にも、動物園で屋外各所の暑さ指数をセンサーで一元管理するシステムや、耳にかける計測機器で熱中症リスクを本人や管理者に通知するサービスなど、テクノロジーを活用して働く人を守る動きも広がっています。
企業が今すぐ取り組むべき具体的な熱中症対策
安全配慮義務違反を避け、従業員を守るために、厚生労働省は具体的な対策を推奨しています。自社の状況と照らし合わせ、すぐに実践しましょう。
作業環境管理
- WBGT値の低減: 冷房や除湿設備の適切な稼働、日よけの設置、送風機の活用など。
- 休憩場所の整備: 冷房が効いた部屋や日陰の涼しい場所を確保し、氷や冷たいおしぼり、シャワー設備などを設ける。
作業管理
- 作業時間の短縮: 高温多湿な場所での作業時間を減らし、こまめな休憩を確保する。
- 水分・塩分の摂取: 作業前後や作業中に、定期的な水分・塩分補給を義務付け、管理者が巡視などで確認する。
- 適切な服装: 通気性の良い服装を推奨し、必要に応じてクールジャケットなどを支給する。
健康管理と教育
- 日常の健康管理: 睡眠不足や体調不良が熱中症リスクを高めることを指導し、健康相談を実施する。
- 作業前の体調確認: 朝礼時や作業中の巡視で、従業員の健康状態を確認する。
- 労働衛生教育: 熱中症の症状や予防法、緊急時の救急措置について、管理者と従業員双方に教育を行う。
まとめ:気候変動時代の「安全配慮」とは
「災害級」の暑さが常態化する現代において、「暑すぎる職場」を放置することは、従業員の命と健康を危険にさらし、企業の法的・社会的信用を失墜させる重大なリスクです。
もはや、暑さ対策は個人の問題ではなく、企業の危機管理能力と、従業員への配慮、すなわち人権への姿勢が問われる経営課題です。気候変動という大きな脅威に対し、科学的根拠に基づいて「適応」していくことこそが、SDGs時代の持続可能な企業経営と言えるでしょう。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
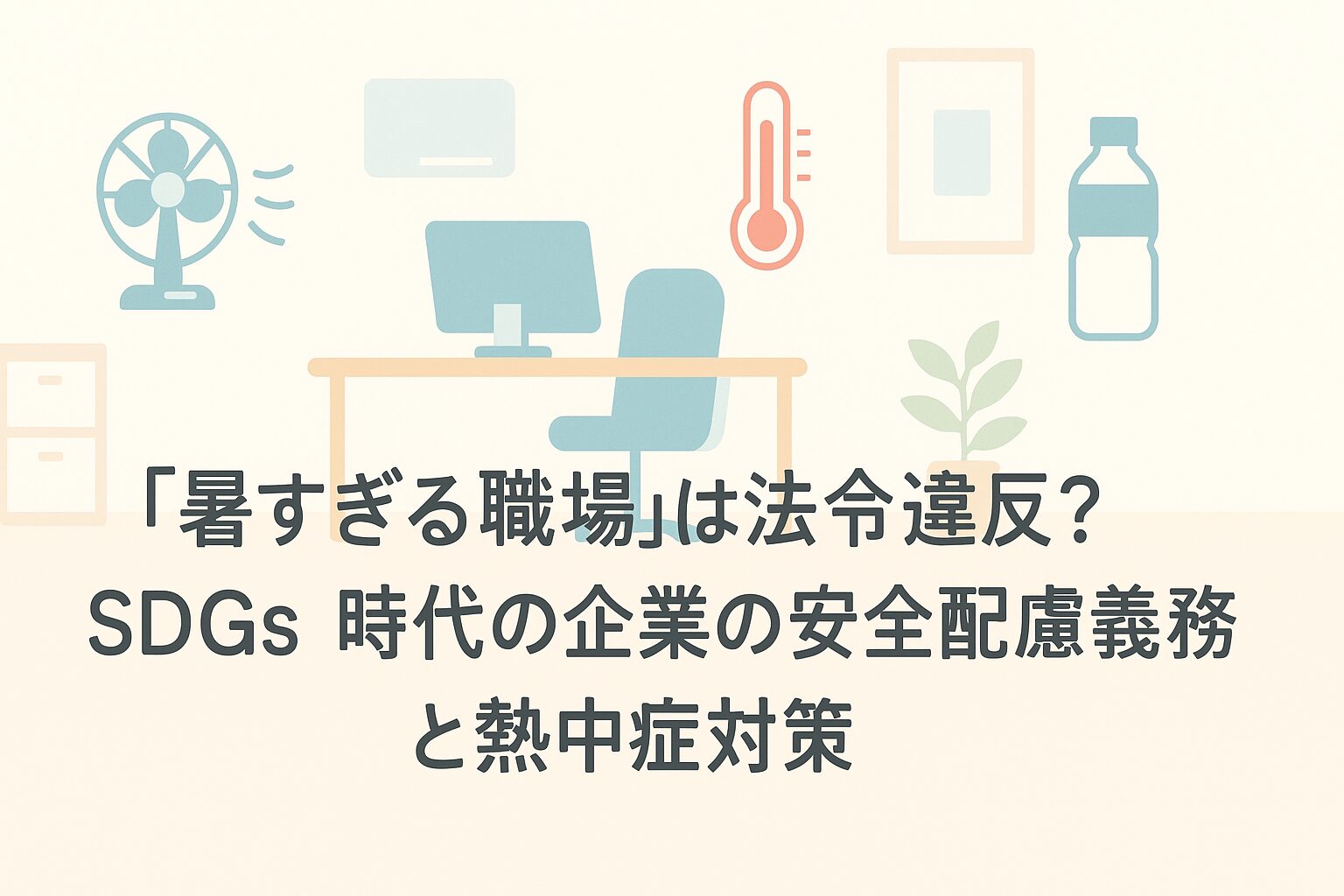
コメント