こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。当メディアは、ジャパンSDGsアワードで外務大臣賞を受賞した企業の知見を活かし、国内外の最新動向を厳選してお届けしています。
2025年8月、世界の脱炭素をリードする二大国、中国とアメリカから、太陽光発電に関する対照的なニュースが報じられました。
- 中国:上半期のCO2排出量が前年比1%減少し、太陽光発電の急増が主な要因と発表。
- アメリカ:トランプ政権の農務長官が「農地に中国のソーラーパネルは要らない」と表明し、農地への設置補助金を廃止。
一方は「脱炭素の切り札」として太陽光発電を推進し、もう一方は「農地とエネルギー主権の敵」として規制を強める。この正反対の動きは何を意味するのでしょうか?今回は、この米中の動向から、脱炭素、食料安全保障、そして経済安全保障が複雑に絡み合うSDGsのジレンマを読み解いていきます。
この記事のポイント
- 中国のCO2排出量減少と太陽光発電の驚異的な伸び
- アメリカが「待った」をかける理由:農地とエネルギー主権
- 専門家が指摘する「SDGsのトレードオフ(二律背反)」
- 日本がとるべき道と企業の対策
ニュースの概要:太陽光を巡る米中のコントラスト
まず、2つのニュースの要点を整理しましょう。
中国:太陽光発電が牽引する「脱炭素」の加速
ヘルシンキを拠点とする研究機関CREAの調査によると、2025年上半期の中国のCO2排出量は、前年同期比で1%減少しました。特に電力部門では3%の減少が見られ、その最大の要因が太陽光発電の記録的な導入です。
不動産不況によりセメントや鉄鋼などの排出量が減った一方、太陽光発電の導入量は驚異的なペースで増加しており、このままいけば年間を通じても排出量が減少すると予測されています。これは、世界最大の排出国である中国が、2060年のカーボンニュートラル目標に向け、再生可能エネルギーへのシフトを本気で進めている証左と言えます。
アメリカ:「食料とエネルギーの安全保障」を優先
一方、アメリカでは全く逆の動きが見られます。トランプ政権で農務長官を務めるブルック・L・ローリンズ氏は、農地に設置される外国製(特に中国製)ソーラーパネルへの補助金を廃止すると発表しました。
その理由は大きく2つです。
- 農地の保護:ソーラーファームの拡大により農地の価格が高騰し、次世代の農家が土地を確保できなくなっている。
- エネルギー主権の確保:補助金の多くが中国製の安価なパネルに流れ、アメリカのエネルギー供給が海外のサプライチェーンに依存する状況を問題視している。
ローリンズ氏はこれを「農家とエネルギー主権を守るための決断」と位置づけています。
専門的視点:SDGsの目標間に潜む「トレードオフ」
この米中の動きは、SDGsが抱える「トレードオフ」、つまり一つの目標を追求すると、別の目標との間に矛盾が生じるという深刻なジレンマを浮き彫りにしています。
1. 「クリーンエネルギー」 vs 「飢餓をゼロに」
alt属性: SDGsの目標7(クリーンエネルギー)と目標2(飢餓をゼロに)のアイコン
今回の問題は、以下の2つの目標の衝突と捉えることができます。
- SDGs 7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに
- SDGs 2:飢餓をゼロに
中国は目標7を強力に推進していますが、その裏で農地がどれだけ転用されているかは不透明な部分があります。一方、アメリカは目標2の基盤である農地を守るため、目標7の手段である太陽光発電の拡大にブレーキをかけています。
これは、「環境か、食料か」という究極の選択にも見えますが、本質は土地利用の競合です。限られた土地をエネルギー生産に使うのか、食料生産に使うのか。この問題は、日本のように国土が限られている国にとっては、さらに深刻です。
2. 「気候変動対策」 vs 「経済安全保障」
もう一つの対立軸は、気候変動対策と経済安全保障です。
- SDGs 13:気候変動に具体的な対策を
- SDGs 8:働きがいも経済成長も(自国産業の保護を含む)
脱炭素を急ぐあまり、安価な中国製パネルに市場を席巻されると、自国の製造業が衰退し、エネルギー供給網という国家の根幹を他国に握られてしまう。アメリカの政策転換は、このリスクに対する強い危機感の表れです。
これは、単なる貿易摩擦ではありません。脱炭素というグローバルな目標と、自国の産業と安全を守るというナショナルな目標が衝突する、新しい地政学リスクの始まりなのです。
日本が直面する課題と企業に求められる対応
この米中のジレンマは、決して対岸の火事ではありません。日本も同様の課題に直面しています。
日本の課題
- 食料自給率の低さ:これ以上農地を減らすことは、食料安全保障上の大きなリスクです。
- エネルギー自給率の低さ:再生可能エネルギーの導入は急務ですが、その多くを輸入に頼っています。
- ソーラーパネルの廃棄問題:今後、大量のパネルが寿命を迎え、その処理が大きな社会問題になると予測されています。
このような状況で、企業や私たちは何をすべきでしょうか。
- ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の推進
農地の上部にパネルを設置し、農業と発電を両立させる「ソーラーシェアリング」は、土地利用の競合を解決する有力な選択肢です。企業は、地域社会や農家と連携し、こうした持続可能なモデルへの投資を検討すべきです。 - サプライチェーンの国内回帰・強靭化
アメリカの動きが示すように、これからは「どこで」「誰が」作ったエネルギー機器なのかが問われる時代になります。国内での生産体制を強化し、リサイクル技術を高めることで、経済安全保障とサーキュラーエコノミーを同時に実現する必要があります。 - エネルギー効率の向上と需要抑制
供給側だけでなく、需要側、つまり私たちのエネルギーの使い方を見直すことも不可欠です。省エネ技術への投資や、ライフスタイルの転換が、根本的な解決につながります。
まとめ:対立から統合へ。日本の知恵が試されるとき
米中の太陽光発電を巡る動きは、脱炭素社会への道筋が一つではないことを示しています。環境、食料、経済という、どれも欠かすことのできない価値を、私たちはどうすれば鼎立させることができるのか。
この複雑なパズルを解く鍵は、対立する目標を統合するイノベーションにあります。ソーラーシェアリングのような技術的解決策や、地域社会との丁寧な合意形成といった社会的解決策を組み合わせ、日本ならではの持続可能なモデルを世界に示すこと。今、私たちの知恵と実行力が試されています。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
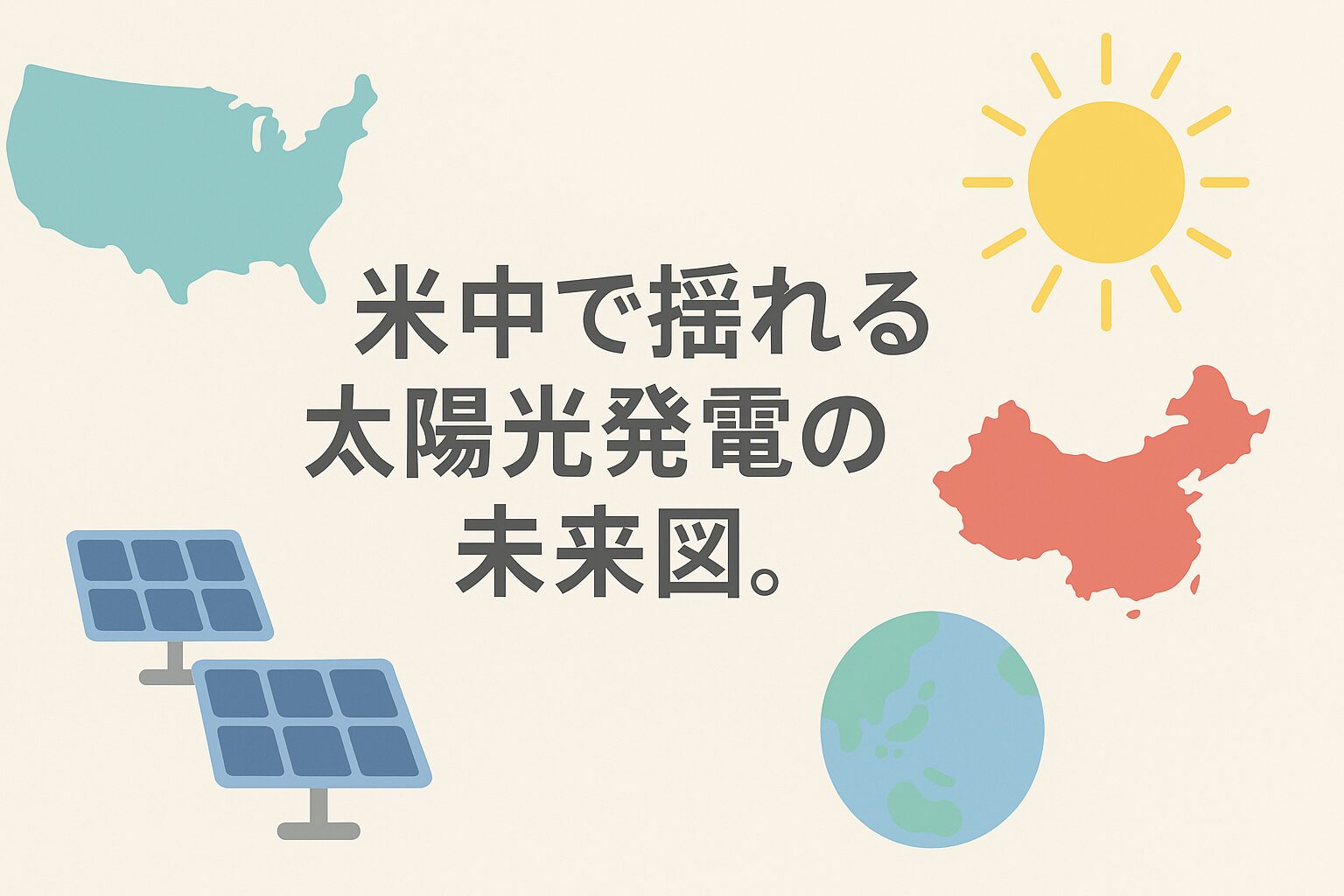
コメント