こんにちは、「SDGsの知恵袋」編集長の日野です。
先日、トランプ前米大統領が国連で行った演説が、世界中で大きな話題となりましたね。「気候変動は史上最大の詐欺」「このグリーン詐欺から脱却しなければ国は破滅する」といった強い言葉に、驚いた方も多いのではないでしょうか。国際社会が一体となって気候変動対策を進めようとしている中で、このような発言が出てくるのはなぜなのでしょうか。
今回はこのニュースを、SDGsが目指す未来と照らし合わせながら、少し深く掘り下げてみたいと思います。
まずは事実を確認しよう:「温暖化は詐欺」の根拠は?
まず、ここがポイントですが、トランプ氏の発言は科学的な事実に基づいているのでしょうか。日経新聞の記事が詳しく検証しています。
- 主張1:「国連の予測はどれも間違っていた」
- 事実:トランプ氏は「1989年に国連高官が『10年以内に国がなくなる』と言ったが起きていない」と主張しました。しかし、元のAP通信の記事では「2000年までに傾向が反転しなければ」という条件がついており、発言を改変して引用していることがわかります。実際には、過去の気候シミュレーションは、現実の観測結果とほぼ一致しているという研究論文が多数発表されています。
- 主張2:「再生可能エネルギーは高価で機能しない」
- 事実:国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、2024年に始まった新しい再生可能エネルギープロジェクトの91%が、化石燃料よりも発電コストが安かったと報告されています。技術の進歩で、太陽光や風力はどんどん安価で効率的になっているんです。
- 主張3:「温暖化はでっち上げ」
- 事実:国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、「人間の影響が地球を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と結論付けています。これは世界中の何千人もの科学者の研究成果をまとめたもので、科学的な総意と言えるものです。
このように、トランプ氏の主張は、残念ながら科学的なデータや事実とは異なっている点が多いようです。
なぜ彼はそう主張するのか?発言の裏にある「世界観」
では、なぜ事実と異なる主張を繰り返すのでしょうか。そのヒントは、The Guardian紙のコラムが指摘する、演説の背景にある「思想」にありそうです。
この記事によると、トランプ氏の言葉は単なる思いつきの暴言ではなく、「勝者と敗者」「排除」といった思想に基づいていると分析されています。これは、世界を「自分たちの利益になるか、ならないか」だけで判断し、協力よりも対立を、包摂よりも排除を選ぶ世界観です。
実は、トランプ政権は以前から、SDGs(持続可能な開発目標)そのものを「米国の主権と相容れない」として拒否する姿勢を見せていました。
身近な例で考えてみましょう。SDGsが「クラス全員がそれぞれの個性を活かし、助け合って一緒に卒業しよう」という考え方だとすれば、トランプ氏の思想は「自分と仲の良い数人だけが良い成績を取ればよく、他の生徒のことは気にしない」という考え方に近いのかもしれません。
気候変動という地球全体の問題を「詐欺」と断じ、国際的な協力の枠組みである「パリ協定」を批判するのも、この「自分たちさえ良ければいい」という思想の現れと見ることができるのです。
SDGsの核心「誰一人取り残さない」への挑戦
この考え方は、SDGsが最も大切にしている「誰一人取り残さない(Leave No One Behind)」という理念とは、全く逆の方向を向いています。
気候変動の影響は、真っ先に貧しい国や地域、立場の弱い人々に及びます。海面上昇で住む場所を失ったり、干ばつで食料がなくなったりと、まさに命の問題に直結するのです。だからこそ、世界が一致団結して、豊かな国が途上国を支援しながら、この危機を乗り越えようとしているわけです。
トランプ氏の演説は、この「協調」と「包摂」への挑戦状とも言えます。それは気候変動対策(SDGs13)だけの話ではありません。貧困(SDGs1)やジェンダー平等(SDGs5)、平和(SDGs16)といった、全ての目標の根底にある「みんなでより良い未来を作ろう」という想いを否定しかねない、とても不穏なメッセージなのです。
私たちにできること
このような大きなニュースを前にすると、無力感を感じてしまうかもしれません。でも、決してそんなことはありません。私たち一人ひとりにできることがあります。
- 情報を見極める習慣を:一つの強い言葉を鵜呑みにせず、「本当かな?」と立ち止まって、信頼できる情報源で事実を確認する習慣が、これまで以上に大切になっています。
- 対話と共感を大切にする:私たちの周りから、「分断」ではなく「つながり」を大切にしてみませんか。多様な意見に耳を傾け、異なる立場の人を理解しようとすることが、排他的な考え方への一番の対抗策になります。
- 未来を選ぶ行動を:私たちがどんな商品を選び、どんな企業を応援し、社会にどう関わっていくか。その一つひとつの選択が、協調的な未来を支持する一票になります。
今回の演説は、私たちがどんな未来を選びたいのかを改めて問いかけています。恐怖や不信ではなく、希望と信頼に基づいた社会を。そんな未来を選ぶための小さな一歩を、今日から始めてみませんか。
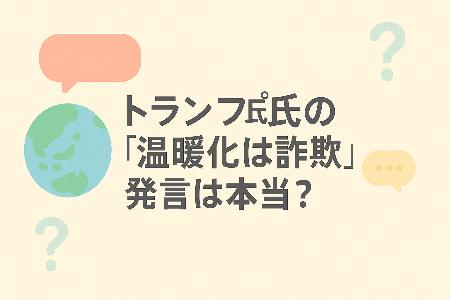
コメント