脱炭素とSDGsの知恵袋の編集長、日野広大です。私たちのメディアは、ジャパンSDGsアワードで外務大臣賞を受賞した企業の知見を活かし、信頼性の高い情報発信を心がけています。今回は、平時の今だからこそ考えたい「防災」とSDGsの関係について、内閣府が初めて公開した衝撃的なシミュレーション映像をもとに解説します。
今日は防災の日です。「もし富士山が大規模噴火したら…」。その時、100km離れた東京・新宿の街がどうなるのか。内閣府が8月25日に初公開したCG映像は、その甚大な被害をリアルに描き出し、大きな反響を呼んでいます。風向きによっては、噴火からわずか2日後に新宿で火山灰が5cm以上積もり、首都機能が麻痺する可能性があるというのです。
これは遠い未来のSF映画の話ではありません。このシミュレーションは、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」で掲げられる「災害に強く、レジリエントな都市」の実現がいかに重要であるかを、私たちに突きつけています。
- 内閣府が公開したCG映像の衝撃的な内容とは?
- なぜ火山噴火への備えがSDGsの重要なテーマなのか?
- 私たち一人ひとりが今すぐできる具体的な備えとは?
本記事では、この最新の被害想定をSDGsの視点から深掘りし、持続可能な社会における防災の役割を考えます。
内閣府が初公開した「富士山噴火CG」の衝撃
今回公開されたCG映像は、富士山で大規模な噴火が発生した場合の被害を具体的に示しています。
- 首都圏への降灰: 風向き次第で、噴火から2日後には東京・新宿でも火山灰が5cm以上積もる。15日目には、その影響が首都圏全域に及ぶと想定されています。
- 建物の倒壊リスク: 降った灰が雨水を吸うと非常に重くなり、木造家屋が倒壊する恐れがあります。
- インフラの麻痺: 道路は通行不能になり、鉄道は運行を停止。さらに、断水や停電といったライフラインの寸断も予測されています。
- その他の被害: 噴火口の近くでは、巨大な噴石や溶岩流、時速100kmを超える火砕流が発生するとされています。
このシミュレーションは、一つの自然災害が、私たちの社会システム全体をいかに脆弱にするかを明確に示しています。
なぜこれがSDGsの課題なのか?災害と持続可能性
自然災害への備えは、持続可能な社会を築く上で避けては通れない中心的な課題です。今回の富士山噴火の想定は、特に以下のSDGs目標と深く関わっています。
SDG 11「住み続けられるまちづくりを」:レジリエンスの核心
SDGs目標11のターゲット5には、「2030年までに、貧困層や脆弱な立場にある人々に焦点をあて、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に削減する」と明記されています。
今回の内閣府のシミュレーションや、それに基づき3月に公表された「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」は、まさにこの目標を達成するための科学的根拠と行動計画を示すものです。災害のリスクを正しく理解し、事前に対策を講じることこそが、住み続けられるまちの「レジリエンス(強靭性)」を高めるのです。
連鎖するリスク:インフラ、健康、食料への影響
富士山噴火の影響は、建物や交通網といった物理的なインフラ(SDGs 9)を破壊するだけではありません。
- 健康(SDGs 3): 細かな火山灰は呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があります。また、断水による衛生環境の悪化も懸念されます。
- 食料(SDGs 2): 物流の停滞は、食料や生活必需品の供給をストップさせます。
- エネルギー(SDGs 7): 火力発電所のフィルターが詰まることによる大規模な停電も指摘されています。
このように、一つの災害が社会の様々な側面に連鎖的な影響を及ぼし、私たちの暮らしの持続可能性を根底から揺るがすのです。
私たちに求められる備えとは?「自分ごと」として考える防災
では、このシミュレーション結果を受けて、私たちは何をすべきでしょうか。内閣府は「噴火での物流の停滞に備えて、普段から食料品などを備蓄してほしい」と明確に呼びかけています。
- 最低3日分、推奨1週間の備蓄: 飲料水、食料、常備薬などを準備しましょう。特に降灰を想定し、防塵マスクやゴーグルは必須です。
- ハザードマップの確認: 自宅や職場がどのようなリスクのある場所かを確認し、避難経路を家族と話し合っておきましょう。
- 最新情報の入手方法の確保: 停電に備え、スマートフォンのモバイルバッテリーや手回し充電ラジオなどを準備しておくことが重要です。
こうした一人ひとりの「自分ごと」としての備えが、社会全体の被害を軽減し、災害からの迅速な復旧を可能にする力となります。
まとめ
内閣府が公開した富士山噴火のシミュレーションは、私たちに恐怖を与えるためではなく、科学的根拠に基づいた「賢い備え」を促すためのものです。そして、その備えは、SDGsが目指す「誰一人取り残さない、持続可能でレジリエントな社会」を築くための、極めて重要なアクションの一つです。
「防災の日」を機に、ぜひご家庭や職場でもう一度防災対策を見直し、必要な備蓄を確認してみてはいかがでしょうか。平時の備えこそが、未来のいのちと暮らしを守る最も確実な投資なのです。
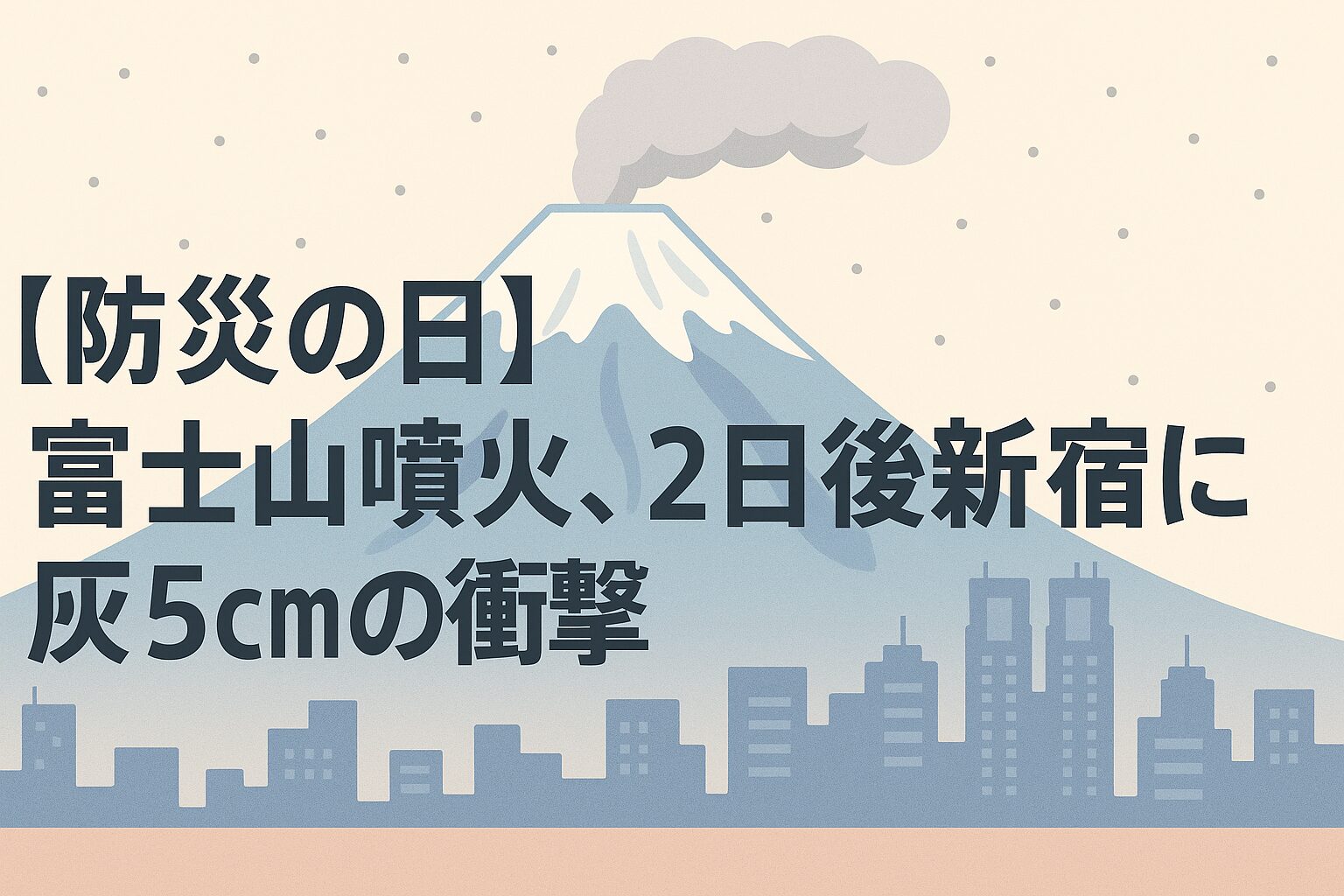
コメント