🙋♀️ こんな人にオススメです
- 「サステナブルな選択をしたいけど、革製品は避けるべき…?」と悩んでいる方。
- 革製品の環境負荷や動物福祉について、専門家の見解を知りたい方。
- 国際認証制度(LWGなど)の実情と課題を知りたい、ビジネスに関わる方。
- 日本の「ものづくり」が、世界基準に対しどのような答えを出したのか知りたい方。
🗣️ 対談:前編
「革=不都合な真実」の前に知ってほしい、もう一つの真実
まず、最も大きな誤解を解くことから始めましょう。
「革のために、動物が殺されている」というのは、現代においてはほぼ事実ではありません。
JLIA ロビンソン氏: 世界で流通している革のほとんどは、私たちが食べる牛肉や豚肉などの副産物です。もし革として利用しなければ、その皮は廃棄されるしかありません。食肉文化がある限り、皮は発生し続けます。それをゴミにせず、価値ある製品として長く使い続けることこそ、命を無駄にしないサステナブルな行為だと考えています。
FrankPR 松尾: 私たちがバングラデシュで扱う革も、イスラム教の宗教儀式「犠牲祭」で神様に捧げられた牛の皮を再利用しています。本来捨てられていたものをアップサイクルすることで、CO2排出量を削減し、現地の文化も尊重できる。この「背景」を知るだけで、革への見方が大きく変わりますよね。
近年、「ヴィーガンレザー」という言葉が広まりましたが、その多くは石油由来の合成皮革です。JLIAの長年の働きかけもあり、大手アパレルなどでは誤解を招く「レザー」という表現を使わない動きが広がっています。天然素材である革は、正しく使えば土に還る、本来、循環するものなのです。
世界基準のジレンマ。なぜ「日本独自の認証」が必要だったのか?
サステナビリティが世界の共通言語となる中、皮革業界にも国際的な認証制度が存在します。その代表格が「レザーワーキンググループ(LWG)」です。しかし、そこには大きな課題がありました。
FrankPR 松尾: 新しい認証制度を始められた背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?
JLIA 吉村事務局長: LWGのような国際認証は、有名ブランドも採用しており非常に重要です。しかし、監査には多額の費用がかかり、書類はすべて英語。コンサルタントを雇い、監査に対応していくためには、数千万円にのぼることもあります。これは、日本の皮革産業を支える多くの中小企業にとっては、あまりにも高いハードルです。
FrankPR 松尾: 私たちもバングラデシュで提携しているなめし工場がLWG認証を取得していますが、その大変さは身をもって感じています。特に途上国や中小企業にとっては、認証の取得や維持コストが、サステナビリティ推進の障壁になりかねません。
JLIA 吉村事務局長: まさにその通りです。私たちは国際認証ほどの手間やお金がかからず、透明性が高く、日本の実情に合った仕組みが必要だと考えました。
元々、日本の事業者は、世界に誇れる高いレベルで環境対策や労働環境の整備に真面目に取り組んできました。そうした現場の実直な努力を、もっと分かりやすく、正当に評価できる仕組みを作りたい。
それが、日本独自の認証制度「JLIAサステナブル企業認証」を立ち上げた一番の想いです。大企業だけでなく、日本の皮革産業全体で、世界に誇れるサステナビリティを目指すための基準なのです。
日本のものづくりを、未来へつなぐために。
世界的な潮流に応えつつも、それを鵜呑みにするのではない。自らの足で立ち、自分たちのものづくりの在り方を、自らの言葉で証明していく。
JLIAの挑戦は、単なる認証制度の創設に留まりません。それは、日本の皮革産業が、その誇りと未来をかけて世界に示す、一つの「意思表示」なのです。
では、その新しい認証制度「JLIAサステナブル企業認証」は、具体的にどのようなもので、私たちの選択をどう変えてくれるのでしょうか。そして、そこにはどんな未来が描かれているのでしょうか。後編では、認証制度の具体的な中身と、それが消費者や企業にもたらすメリット、そして革製品との新しい付き合い方について、さらに詳しく掘り下げていきます。
(後編へ続く)
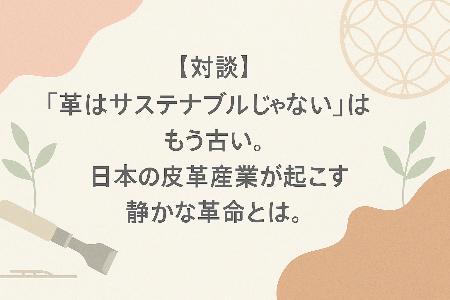
コメント