脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長の日野広大です。政府の「ジャパンSDGsアワード」で表彰された知見を活かし、企業の皆様や社会の持続可能性に関心を持つ方々へ、信頼できる情報をお届けしています。今回は、日本の脱炭素政策の根幹をなし、多くの企業活動に影響を与える「排出量取引制度(GX-ETS)」について、経済産業省の最新資料を基に、その仕組みから今後の展望まで、どこよりも分かりやすく解説します。
「排出量取引」と聞くと、「規制」「コスト増」といったネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、これは日本が2050年カーボンニュートラルを実現し、グリーンな市場で世界と戦うための重要な「ルールメイキング」です。正しく理解すれば、リスクではなく大きなビジネスチャンスになり得ます。
この記事のポイント
- そもそも「排出量取引制度」とは何か、基本をわかりやすく解説。
- 2026年度から本格稼働する日本の制度「GX-ETS」の具体的なスケジュールと対象。
- 企業の排出枠(キャップ)の決まり方や、コストを抑える仕組み。
- この制度がSDGs達成、特に気候変動対策(SDG 13)にどう貢献するのか。
ついに日本も本格導入へ!「排出量取引制度」とは?
排出量取引制度(ETS: Emissions Trading Scheme)は、CO2などの温室効果ガス排出に価格をつけ、経済的なインセンティブによって削減を促す「カーボンプライシング」の代表的な手法です。
簡単に言えば、「CO2排出のダイエット競争」のようなものです。
- 目標設定(キャップ): まず政府が、国全体で排出してよいCO2の総量の上限(キャップ)を定めます。
- 排出枠の割当: 次に、その上限の範囲内で、対象となる企業ごとに排出できる枠(排出枠)を割り当てます。
- 過不足の取引(トレード):
- 目標以上に排出削減を達成し、排出枠が余った企業は、その余剰分を市場で売ることができます。
- 一方、目標達成が難しく、排出枠が足りなくなった企業は、市場から枠を買い足さなければなりません。
この「トレード」の仕組みがあるため、社会全体として最も効率的(低コスト)にCO2削減が進むとされています。削減が得意な企業がより多く削減し、その努力が報われることで、イノベーションも促進されるのです。
GX-ETSの全体像:日本の制度、3つの柱
日本の排出量取引制度は、単体で存在するわけではありません。「成長志向型カーボンプライシング構想」という大きな枠組みの中に位置づけられています。その中心となるのが、以下の3つの柱です。
- GX-ETS(排出量取引制度): 今回の主役。企業の排出削減を促す市場メカニズム。
- 化石燃料賦課金: 2028年度から導入予定。化石燃料の輸入事業者等に対し、CO2排出量に応じて課金される仕組み。炭素に対する明示的な価格付けです。
- GX経済移行債: 上記の賦課金収入などを償還財源として、今後10年間で20兆円規模を発行。脱炭素に向けた企業の先行投資を支援します。
つまり、「支援(GX経済移行債)」と「負担(賦課金・ETS)」を組み合わせることで、社会全体のGX(グリーントランスフォーメメーション)を加速させるのが日本の戦略です。
【いつから?】GX-ETSの導入スケジュールを徹底解説
GX-ETSは段階的に導入されます。自社の事業がいつから対象になるのか、正確に把握することが重要です。
- 第1フェーズ(2023年度~2025年度): 試行期間
- 「GXリーグ」に参加する企業による自主的な目標設定と排出量取引が既に始まっています。これは本格稼働に向けた助走期間です。
- 第2フェーズ(2026年度~): 本格稼働(産業部門)
- 2026年度から、CO2排出量の多い一部事業者から参加が義務化される見通しです。
- 当初は準備のできた事業者からの参加となり、段階的に対象が拡大されます。
- 第3フェーズ(2033年度~): 本格稼働(発電部門)
- 電力会社など発電部門が対象となります。
- 大きな特徴は、排出枠の一部が「有償オークション」、つまり入札形式で販売されることです。これにより、発電コストを通じて電力料金にも影響が及ぶ可能性があります。
- (横に流れる時間軸をイメージ)
[2023年度]────────────────►[2026年度]────────────────►[2028年度]────────────────►[2033年度]
【フェーズ 1】 🗓️ 2023年度〜2025年度
試行期間フェーズ 🚀
GXリーグ参加企業による自主的な排出量取引がスタート。本格稼働に向けたルール作りや知見を蓄積する助走期間。
対象: GXリーグ参加企業(任意)
キーワード:自主的取引試行知見の蓄積
【フェーズ 2】 🗓️ 2026年度〜
本格稼働フェーズ(産業部門)🏭
産業部門(製造業など)を対象とした排出量取引が本格的に開始。CO2排出量の多い事業者から段階的に参加が義務化される見込み。
対象: 産業部門(多排出事業者から)
キーワード:本格稼働段階的義務化ベンチマーク
【新制度導入】 🗓️ 2028年度〜
化石燃料賦課金 導入 ⛽️
排出量取引制度とは別に、化石燃料(石油、天然ガス、石炭)の輸入事業者などに対して、CO2排出量に応じた「賦課金」が課される制度がスタート。
対象: 化石燃料の輸入事業者など
キーワード:カーボンプライシング負担金GX投資財源
【フェーズ 3】 🗓️ 2033年度〜
本格稼働フェーズ(発電部門)⚡️
電力会社などの発電部門が排出量取引の対象に。最大の特徴は、排出枠の一部が「有償オークション(入札制)」で割り当てられること。
対象: 発電部門
キーワード:有償オークション電力市場エネルギー転換
企業のギモンに答える:排出枠(キャップ)はどう決まる?
企業にとって最大の関心事は、「自社にどれだけの排出枠が割り当てられるのか?」でしょう。経済産業省の資料によると、以下の方式が基本となります。
- ベンチマーク方式: 同じ業種の製品(例:鉄鋼1トン)を造る際の、CO2排出量がトップレベルの企業の値を基準(ベンチマーク)とします。その基準達成を目標として各社に枠が割り当てられるため、優れた技術を持つ企業ほど有利になります。
- 過去実績方式(グランドファザリング): 過去の排出実績を基に枠を割り当てる方法も、当面は併用される見込みです。
また、排出枠は基本的に「無償」で割り当てられます。これは、急激なコスト負担増による国際競争力の低下(炭素リーケージ ※)を防ぐための配慮です。
※炭素リーケージ: 国内の排出規制が厳しいがために、企業が規制の緩い海外へ生産拠点を移してしまい、結果的に地球全体のCO2排出量が減らない現象。
専門家が読み解くGX-ETSの課題とSDGsへの貢献
この制度は、日本の「SDG 13: 気候変動に具体的な対策を」を達成するための切り札です。さらに、省エネ技術や再エネへの投資を促すことで「SDG 9: 産業と技術革新の基盤をつくろう」「SDG 7: エネルギーをみんなにそしてクリーンに」にも貢献します。
しかし、専門家の視点からはいくつかの論点が見えてきます。
- キャップの野心度: 制度が有効に機能するかは、国全体の排出上限(キャップ)をどれだけ厳しい水準に設定できるかにかかっています。当初は緩やかな設定が予想されますが、2030年目標や2050年カーボンニュートラルの達成には、段階的な引き締めが不可欠です。
- 無償割当から有償化へ: 国際的な潮流は、企業努力をより促す「有償オークション」が主流です。日本の制度も、産業界の状況を見ながら、将来的に有償割当の比率を高めていくかが焦点となります。
- クレジットの質の担保: 排出削減の埋め合わせ(オフセット)に使えるJ-クレジットなどの質をいかに高く保つか。これも制度の信頼性を左右する重要なポイントです。
私たちが企業のSDGs推進をお手伝いする中で感じるのは、こうした政策動向をいち早く察知し、自社の排出量を把握(Scope1,2,3の算定)し、削減計画を立てている企業こそが、GX時代を生き抜く競争力を得ているということです。
まとめ:排出量取引は「罰金」ではなく「未来への投資」
日本の排出量取引制度(GX-ETS)は、2026年度の本格始動に向けて着実に動き出しています。
対象となる企業にとっては、新たな管理コストや削減義務が生じる一方、削減努力が「価値」として売買できるビジネスチャンスも生まれます。これは「罰金」ではなく、脱炭素技術やイノベーションへの「投資」を促す仕組みなのです。
私たち市民にとっても、この制度は将来の電気料金や製品価格に影響を与えうる、決して無関係ではない話です。企業の脱炭素への取り組みを応援する消費行動(エシカル消費)も、この大きなルールチェンジを後押しする力になります。
まずは自社、そして自身の生活にどう関わるのか。この機会にぜひ考えてみてください。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
- 経済産業省 産業構造審議会「排出量取引制度(国内)の導入について」(2025年)
- 経済産業省「成長志向型カーボンプライシング構想」
パーマリンク:
https://example.com/sdgs-blog/japan-gx-ets-emission-trading-scheme
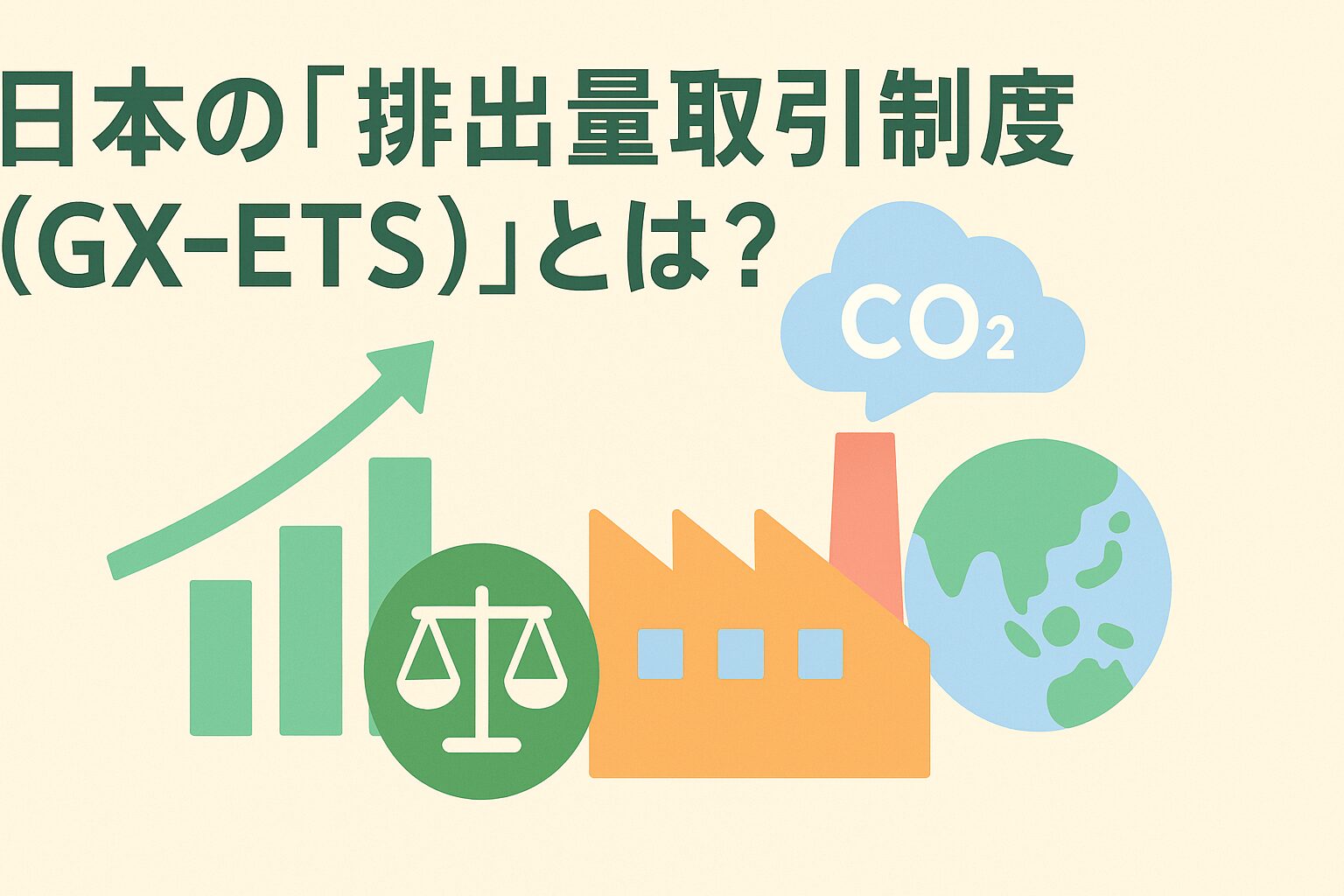
コメント