こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディア運営元であるFrankPRは、SDGsへの貢献が評価され、政府SDGs推進本部より「ジャパンSDGsアワード」外務大臣賞をいただいています。その専門的知見から、今回は日本の脱炭素政策の根幹をなす「GX-ETS」と、その国際的な立ち位置について、極めて重要な提言を解説します。
2026年度から本格稼働を目指す日本の新たな排出量取引制度「GX-ETS」。この制度設計が大詰めを迎える中、企業の環境活動を世界的に評価する英国の非政府組織(NGO)「CDP」のシェリー・マデーラCEOが、日本のCO2排出量算定基準について「国際基準との調和」を強く求めるインタビューが報じられました。
この提言は、日本の産業界がグローバル市場で生き抜くための「羅針盤」とも言える重要な内容です。なぜ国際基準との調和がそれほど重要なのか、そして日本企業が直面する課題とは何か。SDGsの視点を交えて深掘りしていきます。
- 本記事のポイント
- 日本の脱炭素の切り札「GX-ETS」とは?
- なぜ「CO2算定基準のズレ」が日本企業の国際競争力を脅かすのか。
- 見落とせない最大のCO2排出源「サプライチェーン(スコープ3)」の重要性。
- 日本が目指すべき、世界で評価される脱炭素政策のあり方。
まずは基本から:「GX-ETS」と「GHGプロトコル」とは?
本題に入る前に、重要なキーワードを簡単におさらいしましょう。
- GX-ETS (Green Transformation – Emission Trading Scheme):
日本版の「排出量取引制度」のこと。国が企業ごとにCO2排出量の上限(枠)を割り当て、枠を超えて排出する企業と、枠内に収まった企業との間で排出枠を売買できるようにする仕組みです。これにより、社会全体として効率的にCO2削減を進めることを目指します。これはSDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」を実現するための核心的な政策です。 - GHGプロトコル (Greenhouse Gas Protocol):
温室効果ガス(Greenhouse Gas)の排出量を計算・報告する際の、国際的なスタンダード(ルールブック)です。いわば、CO2排出量を測るための「世界共通の物差し」と考えると分かりやすいでしょう。
🌟 まとめ
日本のGX基準は2026年のGX-ETS本格稼働に向けて着実に整備が進んでおり、国際的な脱炭素認証基準も規制要求への移行が加速しています。
企業は自社の事業特性や目標に応じて適切な基準を選択し、段階的な実装により競争優位性を構築することが重要です。
💡 脱炭素化は義務的要求から戦略的機会へ。
早期の準備と継続的な改善により、持続可能な成長と社会価値創造を同時実現。
CDPが鳴らす警鐘:「基準のズレ」が日本企業の競争力を削ぐ
今回、CDPのマデーラCEOが指摘した核心は、「日本のGX-ETSで採用されるCO2算定ルールが、この世界共通の物差し(GHGプロトコル)とズレてしまうのではないか」という懸念です。
(CO2排出量の算定基準は)せめてほかの基準との調和を目指し、柔軟性と相互運用性を持たせるべきだ。
(中略)取引先が米国や英国など外国の企業で、日本政府が求めるデータと全く異なるものを求めてきたら、日本企業に負担がかかり競争上不利になる。
(出典: 日本経済新聞 2025/6/25)
これは、日本企業にとって死活問題になりかねません。
なぜ「国際基準との調和」が不可欠なのか?
想像してみてください。ある日本企業が、GX-ETSという「日本独自の物差し」でCO2排出量を計算して報告したとします。しかし、AppleやMicrosoftのようなグローバル企業から「私たちの取引先になるなら、世界標準のGHGプロトコルという物差しで測り直して報告してください」と言われたらどうなるでしょうか。
企業は、二度手間、三度手間のデータ算出作業を強いられ、余計なコストが発生します。これが「競争上の不利」の正体です。グローバルな取引が当たり前の現代において、日本だけが違うルールで動く「ガラパゴス化」は、企業の成長を阻害し、海外からの投資を遠ざける要因になりかねません。これは、SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」で目指す、強靭な産業基盤の構築とは逆行する事態です。
見落とされがちな最大の排出源「サプライチェーン」の罠
マデーラ氏が次に強調するのが、「サプライチェーン全体」での脱炭素化です。
多くのサプライチェーンの排出量は一企業が自ら管理する排出量の平均26倍になる。
これは衝撃的な数字です。自社の工場やオフィスで使うエネルギー(スコープ1, 2)をいくら削減しても、原材料の調達から、製品の輸送、顧客による使用、そして廃棄に至るまで(これらをまとめてスコープ3と呼びます)の排出量を無視していては、本当の意味での脱炭素は達成できません。
例えば、自動車メーカーであれば、鉄やアルミといった素材の製造時、無数の部品メーカーからの輸送時、そして最終的に顧客が車を運転して排出するCO2までがサプライチェーン排出に含まれます。このスコープ3への対応こそが、SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」の本質であり、企業の真の環境貢献度が問われる領域なのです。
CDP代表の提言から学ぶ、日本のGX政策が目指すべき道
では、日本はこの状況にどう対応すべきでしょうか。マデーラ氏の提言は、明確な方向性を示しています。
- 国際基準との調和と相互運用性の確保:
国内制度と国際標準(GHGプロトコル)の連携を最大限に図り、日本企業が二重の負担を強いられないようにする。 - サプライチェーン全体(スコープ3)を視野に入れた制度設計:
大企業だけでなく、その取引先である中小企業も巻き込み、サプライチェーン全体で脱炭素を進めるインセンティブ(動機付け)を与える。これはSDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」の実践そのものです。 - データ開示を「コスト」から「投資」へ:
企業が算出し開示した環境データが、新たな顧客獲得や金融機関からの投融資につながる仕組みを作る。これにより、データ開示は「やらされ仕事」から「企業価値向上のための戦略的投資」へと変わります。
まとめ:世界標準の物差しを持つことが、日本の持続可能な成長への鍵
CDP代表の提言は、単なる技術的な指摘ではありません。「日本の脱炭素への本気度は、世界からどう見られているのか」という、根源的な問いを私たちに突きつけています。
日本独自のルールに固執し、世界の潮流から取り残される「内向きな脱炭素」を進めるのか。それとも、国際社会と歩調を合わせ、世界から信頼され投資を呼び込む「外向きな脱炭素」を目指すのか。GX-ETSの制度設計は、今まさにその岐路に立たされています。
私たち企業人、そして一消費者としても、企業がどのような基準で環境情報を開示しているかに注目し、国際的な透明性を持つ企業を評価していく視点が、日本の持続可能な未来を築く上で不可欠と言えるでしょう。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
- 日本経済新聞「英CDP代表『日本のCO2算定、国際基準との調和を』」(2025/6/25)
- GX推進機構 公式サイト
- 環境省「サプライチェーン排出量算定について」
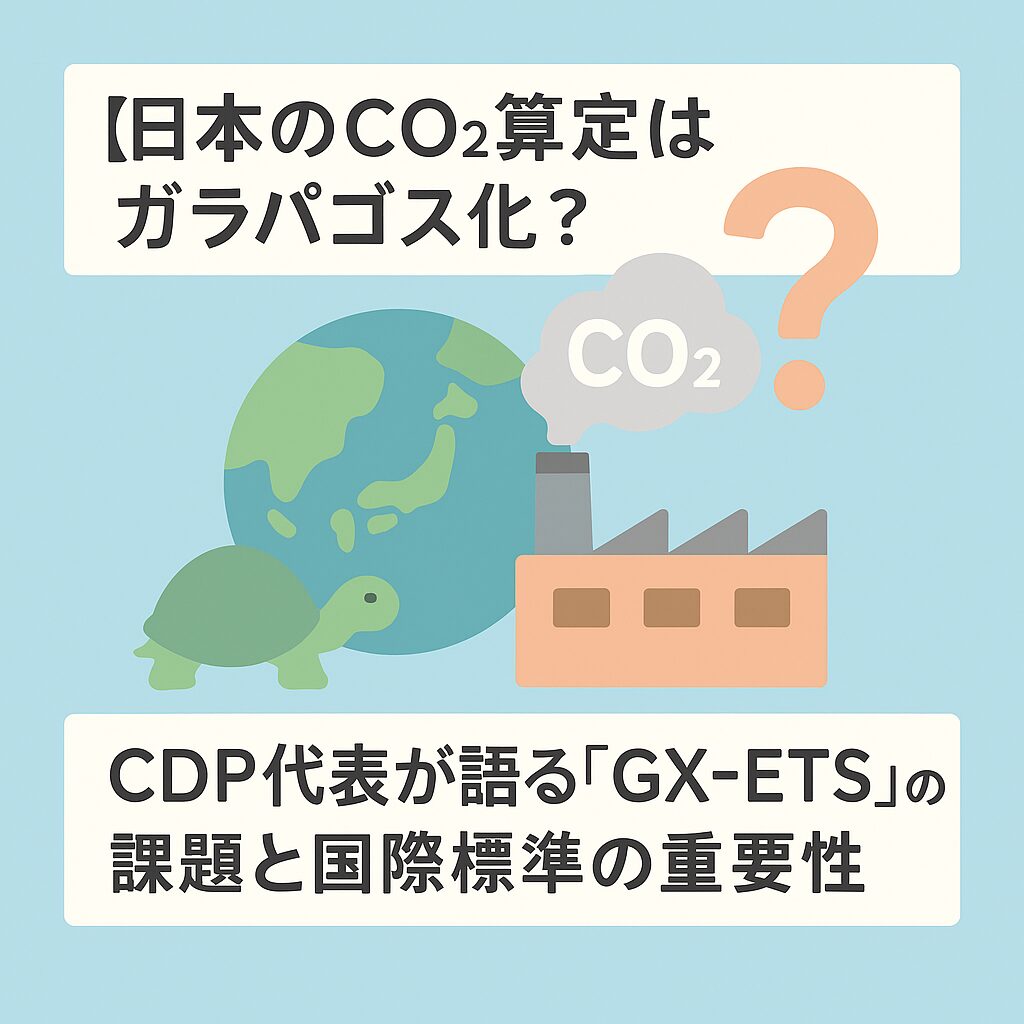
コメント