「来日外国人による犯罪が増加した」。
先日公表された警察白書のデータは、一部の政治家が主張する「治安の悪化」を裏付けるかのように報じられています。こうした声は、私たちの「不安」をかき立て、より厳しい対策や罰則を求める世論につながりがちです。
しかし、私たちはその数字をどう受け止めれば良いのでしょうか。一つのデータだけで結論を出す前に、少し立ち止まって、多角的な視点からこの問題を考えてみませんか。今回は、最新の犯罪統計と、犯罪不安に関する専門家の分析という、2つの異なる記事を読み解きながら、「真の安全」とは何かを公平な視点で探ります。
2つの「ファクト」を冷静に見つめる
まず、私たちが向き合うべき2つの事実を確認しましょう。
ファクト1:最新データは「増加」を示している
警察庁の令和6年版警察白書によると、2023年(令和5年)の来日外国人による刑法犯の検挙件数・人員は、共に前年より増加しました。特にベトナムや中国籍の検挙が全体の約6割を占めているという具体的な数字も示されています。これは、無視できない客観的な事実です。
ファクト2:「体感治安」と「実際の被害率」にはズレがある
一方で、政治学者の丸山泰弘氏は、長年のデータ分析から異なる側面を提示しています。法務省の調査によれば、人々が感じる「犯罪への不安」が高まった2000年代、実際の犯罪被害に遭った人の割合(被害率)は、中長期的に見れば減少傾向にありました。つまり、私たちの「不安感」と「実際の治安」は、必ずしも一致しないのです。
丸山氏は、こうした漠然とした不安が、エビデンスに基づかない厳罰化、いわゆる「ペナルポピュリズム」につながりやすいと警鐘を鳴らします。そして、「全体の数%に満たない外国人犯罪が多少増加・減少したところで日本全体の治安に影響を与えていたとは考えにくい」とも指摘しています。
数字の裏側にある「なぜ?」を考える(SDGsの視点)
「犯罪が増えた」という事実と、「不安と実態は違う」という事実。この2つを前にして、私たちが考えるべきは、「なぜ、犯罪が増えたのか?」という、数字の裏側にある背景です。
例えば、検挙数が多い特定の国籍の人々は、日本でどのような状況に置かれているのでしょうか。彼らが経済的に困窮していたり、社会的に孤立していたりする実態はないでしょうか。もしそうであれば、それは単に個人の問題ではなく、受け入れ国である日本の社会構造にも課題がある可能性を示唆しています。
これは、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」や目標16「平和と公正をすべての人に」にも深く関わる問題です。すべての人々が公正に扱われ、尊厳を持って暮らせる社会を築くことは、まわりまわって犯罪の抑止につながります。特定の集団を「危険だ」とラベリングし、排除するような政策は、根本的な解決から私たちを遠ざけてしまうかもしれません。
「不安」の解消から「真の安全」の構築へ
丸山氏が指摘するように、「不安」に基づいて行われる実態に伴わない政策は、外国人だけでなく、私たち日本人にとっても「生きづらさ」を助長する可能性があります。監視が強化され、些細なことで罰せられる社会は、本当に「安全」な社会と言えるでしょうか。
真の安全とは、特定のグループを排除することによってではなく、犯罪が起きにくい社会の土壌をつくることによって達成されるはずです。
「外国人犯罪が増加した」というデータは、私たちに課題を突きつけています。しかし、その答えを「取り締まり強化」や「厳罰化」だけに求めるのは、あまりにも短絡的です。私たちはこのデータを、外国人も含めた、この社会で暮らすすべての人が直面する課題を明らかにし、解決策を探るための「出発点」として捉えるべきではないでしょうか。
不安に流されるのではなく、ファクトに基づき、その背景にある社会のあり方を問い直すこと。それこそが、持続可能で、誰もが安心して暮らせる社会を築くための、唯一の道だと私は信じています。
ソース
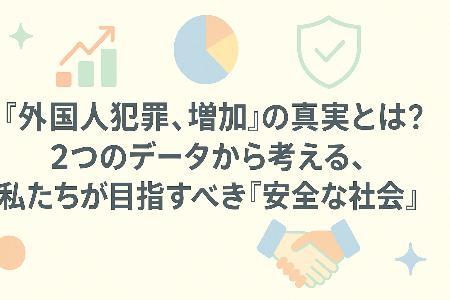
コメント