日本の脱炭素戦略の新たな鍵となるか。豊かな海の恵み「ブルーカーボン」に期待が高まる
脱炭素とSDGsの知恵袋の編集長、日野広大です。私たちの取り組みは、政府のSDGs推進本部からも評価(ジャパンSDGsアワード外務大臣賞)をいただいておりますが、その専門的知見を活かし、皆様に最新かつ重要なニュースを厳選してお届けします。
「石油元売り最大手のENEOSが、環境省と組んで海藻でCO2を吸収する」。一見すると意外な組み合わせに思えるこのニュース、実は日本のカーボンニュートラル達成に向けた、極めて重要な一手かもしれません。
この記事では、以下の点について、特に皆さんが気になるであろう「CO2を海底に貯蔵する仕組み」を中心に、専門家の視点から徹底的に解説します。
- ニュースの要点: 環境省とENEOSは何を目指すのか?
- そもそも「ブルーカーボン」とは? 森林だけじゃないCO2吸収源
- 【本題】海をCO2の貯蔵庫に。海藻を育てて深海に沈める「3ステップ」
- 専門家視点: この技術の本当のすごさと、乗り越えるべき課題
- なぜENEOSが? 石油会社の脱炭素戦略と今後の展望
ニュースの概要:国の「切り札」として期待される海の力
2025年5月20日、環境省は、海藻などが光合成で吸収した炭素「ブルーカーボン」を拡大するため、石油元売り最大手のENEOSに調査を委託したと発表しました。
ニュースのポイント(共同通信より)
- 目的: 海藻を沖合で大量に育て、光合成でCO2を吸収させた後、深海に沈めて「貯留」する技術の実現可能性を探る。
- 背景: 日本のCO2吸収源の約8割は森林だが、国土面積に限界がある。そのため、広大な海を活用した新たな吸収源の確保が急務となっている。
- 体制: ENEOS、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、港湾空港技術研究所という、産業界と研究機関のトップランナーが連携する。
この取り組みは、単なる環境保護活動ではありません。大気中からCO2を直接除去する「ネガティブエミッション技術」の一つとして、国の地球温暖化対策計画にも位置づけられている国家的なプロジェクトなのです。
そもそも「ブルーカーボン」とは?
「ブルーカーボン」とは、海草(アマモなど)や海藻(コンブ、ワカメなど)といった海洋生態系が、光合成によって海水に溶けたCO2を取り込み、体内に炭素として蓄えることを指します。
これまでCO2吸収源といえば森林(グリーンカーボン)が主役でしたが、海の吸収力も非常に高く、特にその「貯留期間の長さ」に大きな注目が集まっています。ブルーカーボンは、数百年から数千年という非常に長い期間、炭素を海底に閉じ込めておけるポテンシャルを持っています。
これは、SDGsの目標13(気候変動に具体的な対策を)と目標14(海の豊かさを守ろう)を同時に達成する、まさに一石二鳥の取り組みなのです。
【本題】海をCO2の貯蔵庫に。海藻を育てて深海に沈める「3ステップ」
今回のプロジェクトの核心は、「育てて、沈める」というシンプルなようで奥深いアプローチです。ここでは、ユーザー様からのご要望にお応えし、そのメカニズムを詳しく解説します。

ステップ1:光合成でCO2を吸収(炭素の固定化)
まず、ワカメやコンブといった大型の海藻を、沿岸部や沖合の海面に設置した施設で大規模に養殖します。海藻は太陽の光を浴びて光合成を行い、大気から海水に溶け込んだCO2を吸収し、自身の体(葉や茎)を作るための有機炭素として固定していきます。海藻は成長が非常に速く、まさに「海の畑」でCO2をどんどん吸収してくれるイメージです。
ステップ2:成長した海藻を「深海」へ(炭素の輸送)
十分に成長し、体内に炭素をたっぷり蓄えた海藻を、船などで水深1,000メートルを超えるような「深海」まで運び、沈めます。なぜ、ただ海底に沈めるのではなく「深海」なのでしょうか?ここに、この技術の最大のポイントがあります。
ステップ3:低温・低酸素の環境で「長期貯留」(炭素の隔離)
深海は、私たちが知る浅い海とは全く異なる世界です。
- 超低温: 水温は常に数度以下に保たれています。
- 低酸素: 生物の活動が少なく、酸素濃度が極めて低い状態です。
- 高圧: 深い水深による高い圧力がかかっています。
この「低温・低酸素・高圧」という環境が、天然のタイムカプセルの役割を果たします。通常、生物の死骸はバクテリアなどによってすぐに分解され、炭素は再びCO2として大気や海水中に戻ってしまいます。
しかし、深海ではバクテリアの活動が極端に抑制されるため、沈められた海藻の分解スピードが非常に遅くなります。その結果、海藻が体内に固定した炭素は、分解されてCO2に戻ることなく、有機物の塊のまま数百年から数千年という長期間にわたって海底に堆積し続けるのです。
これが、大気中のCO2を半永久的に隔離する「深海貯留」のメカニズムです。
専門家視点:この技術の本当のすごさと、乗り越えるべき課題
この「外洋大型藻類ブルーカーボン」と呼ばれる技術は、非常に大きな可能性を秘めています。
<可能性>
- 国土の限界を超えられる: 四方を海に囲まれた日本にとって、陸地の森林だけに頼らない新たなCO2吸収源を創出できます。
- 高い吸収効率: 成長の速い海藻を使うことで、効率的に炭素を固定化できます。
- 新たな産業創出: 藻場の造成・管理や、吸収したCO2を取引する「Jブルークレジット」制度などを通じて、新たな雇用やビジネスが生まれる可能性があります。
<課題>
- コスト: 大規模な養殖施設の建設や、海藻を沖合から深海へ運ぶためのコストが大きな課題です。
- 生態系への影響: 大量の海藻を特定の海域に沈めることが、深海の生態系に予期せぬ影響を与えないか、慎重な調査と評価が必要です。
- 効果の測定: どれだけの量のCO2が、どれくらいの期間、確実に貯留されているのかを科学的に測定・証明する手法の確立が求められます。
今回の環境省とENEOSの調査は、まさにこれらの課題をクリアし、技術を社会実装するための第一歩と言えるでしょう。
まとめ:国の未来を左右する海のポテンシャル
今回のニュースは、エネルギー企業であるENEOSが、自社の脱炭素化(Scope1, 2)だけでなく、大気中のCO2を削減する「ネガティブエミッション」という領域にまで踏み込んだことを示す象徴的な出来事です。
私たちも、このブルーカーボンのような革新的な取り組みに関心を持ち、その動向を見守っていくことが重要です。豊かな海を守る活動(海岸の清掃など)に参加することも、間接的にブルーカーボン生態系を支えることに繋がります。
日本の脱炭素化の未来は、この青い海のポテンシャルをいかに引き出せるかにかかっているのかもしれません。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料: 共同通信、環境省、経済産業省、産業技術総合研究所の公開資料
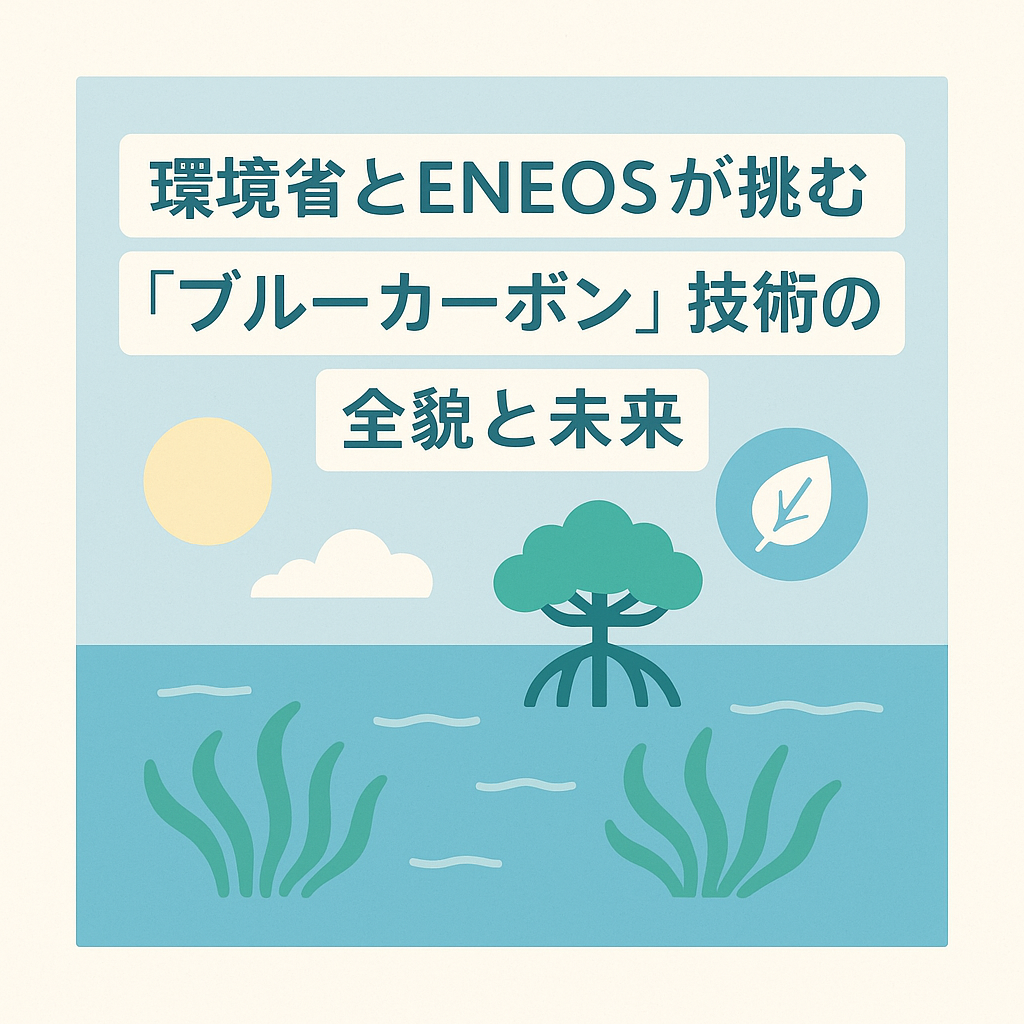
コメント