こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディアは、SDGsへの貢献が評価され、政府SDGs推進本部から「ジャパンSDGsアワード」で外務大臣賞をいただいたFrankPRが運営しています。この記事はコーヒーが好物である、弊社CEOである松尾の強いおすすめで書かせていただいております。
私たちが日々楽しむ一杯のコーヒー。その裏側で、気候変動が引き起こす深刻な危機「2050年問題」が進行していることをご存じでしょうか。この危機に対し、フードテックの最前線では「ビーンレス(豆なし)コーヒー」という革新的な技術が次々と生まれています。
今回は、この代替コーヒーがもたらす希望と、同時に私たちが向き合うべき「不都合な真実」を、SDGsの視点から深掘りしていきます。
この記事でわかること
- 多くのコーヒー好きが知らない「2050年問題」の深刻さ
- ビーンレスコーヒーとは?植物由来から細胞培養までの最新技術
- 技術革新がもたらす光と影:コーヒー農家が直面する新たな脅威
- 真の持続可能なコーヒーのために、私たち消費者ができること
迫りくる危機:コーヒー愛好家が知るべき「2050年問題」とは
「2050年問題」とは、気候変動の影響で、2050年までにコーヒー栽培に適した土地が世界で半減してしまうという衝撃的な予測です。これは国際熱帯農業センター(CIAT)などの研究機関が警鐘を鳴らしているもので、決して遠い未来の話ではありません。
- 気温上昇と異常気象:繊細なコーヒーの木は、わずかな気温の変化にも弱く、生産量が激減します。
- 病害の拡大:気温上昇は、さび病などの病害虫の発生を助長します。
- アラビカ種の絶滅危機:特に高品質で人気の高いアラビカ種は環境変化に弱く、このままでは絶滅する可能性も指摘されています。
私たちが愛する「こだわりの一杯」が、近い将来、飲めなくなってしまうかもしれないのです。この危機的状況が、フードテックによるイノベーションを加速させています。
テクノロジーが生む希望:注目の代替・ビーンレスコーヒー技術
コーヒー豆を一切使わず、あるいは全く新しい方法でコーヒーの味や香りを再現する。そんなSFのような技術が、今まさに現実のものとなっています。
1. 植物由来から細胞培養まで:最前線のスタートアップ
- atomo coffee(米国): デーツの種子やチコリの根など、数十種類の植物を分子レベルで分析・再構築し、コーヒー粉末を開発。廃棄されるデーツの種子をアップサイクルするなど、環境負荷削減も徹底しています(SDGs 12:つくる責任 つかう責任)。
- Koppie(ベルギー): コーヒー豆以外の植物性原料(単一品種)を特殊な発酵・焙煎技術で加工し、本物のコーヒー豆のような形状(ホールビーン)を再現。従来のコーヒーと同じように扱えるのが特徴です。
- Northern Wonder(オランダ): 「熱帯原料ゼロ」を掲げ、コーヒーベルト地帯の原料に依存しないサステナブルなコーヒーを開発。
- Another Food(シンガポール): コーヒー豆の細胞をバイオリアクターで培養。従来の農業の20倍の速さで収穫可能とされ、水や土地の使用量も大幅に削減できる可能性があります。
これらの技術は、気候変動の影響を受けずに安定的にコーヒーを供給できる可能性を秘めており、SDGs 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の優れた実践例と言えます。
技術革新の「不都合な真実」:見過ごされるコーヒー農家の苦境
しかし、この技術革新を手放しで喜ぶことはできません。そこには、SDGsの根幹である「誰一人取り残さない」という理念に反する、大きな課題が潜んでいます。
それは、代替コーヒーが普及すればするほど、コーヒーベルト地帯の小規模農家の生活が脅かされるという問題です。
気候変動の最も深刻な被害を受けているのは、他ならぬ生産国の農家たちです。彼らが収入の危機に瀕しているなかで、消費国である先進国が「もう豆は要らない」とばかりに代替コーヒーに移行してしまえば、彼らの貧困はさらに深刻化してしまいます。これは、SDGs 1「貧困をなくそう」、SDGs 8「働きがいも経済成長も」、そして先進国と途上国の格差を問うSDGs 10「人や国の不平等をなくそう」の観点から、決して見過ごせない問題です。
技術によって先進国の消費者の選択肢は守られても、生産者の生活が破壊されるのであれば、それは「2050年問題」の真の解決とは言えないのです。
真の解決策とは?「代替」と「再生」の両輪で築く持続可能なコーヒーの未来
では、私たちはどうすればいいのでしょうか。答えは、二者択一ではありません。「代替技術」と、既存の農業を強くする「再生」の両輪で未来を考える必要があります。
1. 環境再生型(リジェネラティブ)農業というもう一つの答え
リジェネラティブ農業とは、土壌をただ消費するのではなく、より豊かにしながら作物を育てる農法です。化学肥料や農薬への依存を減らし、土壌の生物多様性を高めることで、気候変動に強いしなやかな農地を作ります。
ネスレなどの企業は、コーヒー農家へのリジェネラティブ農業への移行支援を積極的に行っています。ある調査では、この農法に移行した農家は収入が平均62%増加し、温室効果ガス排出量も削減できるという結果も出ています。これは、農家の生活を守りながら、気候変動対策(SDGs 13)にも貢献する、非常に有望な解決策です。
2. 私たち消費者にできること:賢い選択が未来を変える
技術開発や企業の取り組みを後押しするのは、私たち消費者の選択です。
- コーヒーの背景を知る:自分が飲むコーヒーがどこから来たのか、どのような農法で作られているのかに関心を持ちましょう。
- 認証を選ぶ:生産者の生活や環境に配慮した「フェアトレード認証」や「レインフォレスト・アライアンス認証」などの商品を選ぶことは、具体的な支援に繋がります。
- 「リジェネラティブ」を応援する:環境再生型農業に取り組むブランドを意識的に選ぶことも、新しい流れを加速させます。
まとめ:一杯のコーヒーから考える、技術と倫理のバランス
ビーンレスコーヒーは、コーヒーの未来を拓く希望の技術です。しかし、その技術革新が新たな不平等を生まないよう、私たちは常にその光と影の両面を見つめる必要があります。
真のサステナビリティとは、「代替」という技術革新と、「再生」という農業支援、そしてそれらを支える「倫理的な消費」が一体となって初めて実現します。
私たちFrankPRは、「脱炭素とSDGsの知恵袋」として、技術の進歩を追いながらも、その恩恵が公平に行き渡る社会の実現に向けた情報発信を続けていきます。
あなたの一杯のコーヒーが、生産者にとっても、地球にとっても、幸せな一杯であり続ける未来のために。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料: 元記事「ビーンレスコーヒーは「2050年問題」を解決できるか」(WIRED)
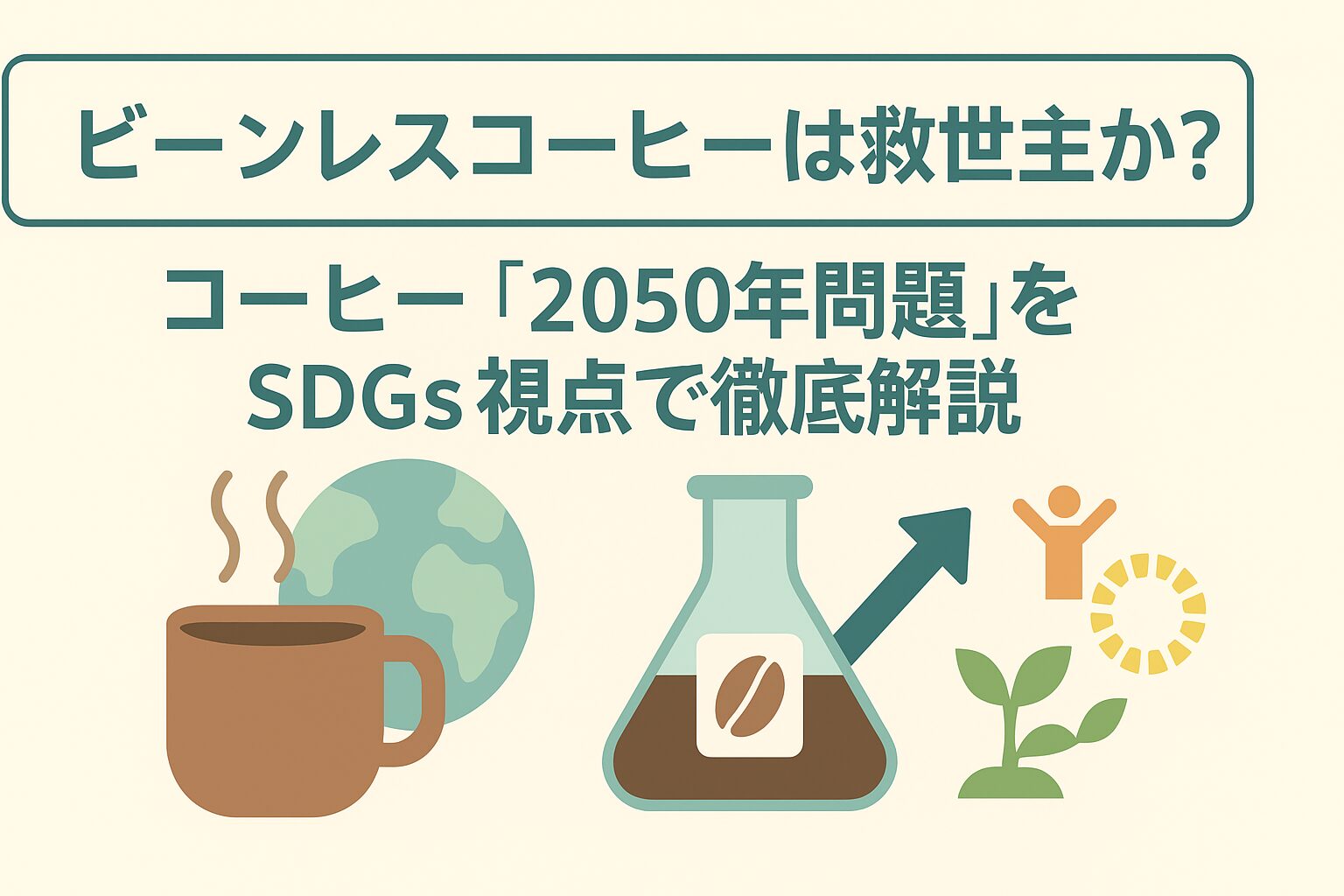
コメント