こんにちは、「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。
秋の行楽シーズンですが、皆さんはどこかへ旅行されましたか? 最近、「観光地は外国人ばかりで、混雑していて宿泊費も高い」と感じることはありませんか?
本日(10月25日)の日本経済新聞に、まさにその実態を示す衝撃的なニュースが掲載されました。2025年1月〜7月において、なんと日本人の国内宿泊者数が全体の7割超にあたる35の都道府県で前年より減少したというのです。
インバウンド(訪日外国人)の活況に沸く裏で起きている「日本人観光客離れ」。これは単なる旅行トレンドの変化ではなく、【用語解説】SDGsとは?17のゴールと169のターゲットを徹底解説! が目指す「持続可能な観光」のあり方に対し、大きな課題を突きつけています。
京都だけじゃない日本人観光客離れ 東京など35都道府県で宿泊者減少
こんな人におすすめです
- 「旅行したいけど、高いし混んでる」と感じている方
- オーバーツーリズム(観光公害)の問題に関心がある方
- インバウンド増加を手放しで喜べない地域住民の方
- 「サステナブル・ツーリズム(持続可能な観光)」について知りたい方
「京都だけじゃない」深刻な日本人観光客離れ
今回のニュースで明らかになったのは、一部の地域だけの問題ではない、という点です。
35都道府県で減少、東京・京都は10%超
観光庁の調査によると、2025年1〜7月の日本人延べ宿泊者数は、全体で前年同期比4%減の約2.6億人泊でした。
特に深刻なのが大都市です。オーバーツーリズムが問題視される京都府や東京都は、減少率が10%を超えています。また、能登半島地震の影響が残る石川県では26%減。島根県も、大阪・関西万博の影響で関西からの旅行者が減り、11%減となっています。
原因は「インバウンド混雑」と「宿泊費の高騰」
なぜ、これほどまでに国内旅行が減っているのでしょうか。
記事では、複数の要因が指摘されています。
- コロナ禍の支援策終了: 「GoToトラベル」のような手厚いキャンペーンが終わった反動。
- 物価高騰: 宿泊費だけでなく、あらゆる物価が上がり、旅行マインドが冷え込んでいる。
- インバウンドによる混雑と高騰: 最大の要因とも言えるのがこれです。外国人観光客が増え、観光地は混雑し、ホテル代も高騰。日本人が国内旅行を敬遠する大きな理由になっています。
- 海外旅行へのシフト: 為替が比較的落ち着き、国内旅行の割高感から海外旅行を選ぶ人も増えています。
なぜこれがSDGsにとって重要なのか?
「外国人が来てくれて経済が潤うなら、良いことじゃないか」と思うかもしれません。しかし、SDGsの視点で見ると、この「日本人観光客離れ」は、持続可能性の赤信号です。
SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」の危機
[Image: SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」のアイコン]
インバウンド客で溢れかえるオーバーツーリズムは、観光地の文化遺産や自然だけでなく、何よりそこに住む人々の生活を脅かします。交通機関の麻痺、ゴミ問題、騒音……。
日本人観光客までもが「あそこはもう行きたくない」と敬遠し始めたという事実は、その地域が「住み続けたい」はおろか、「訪れたい」場所でさえなくなりつつある証拠です。これは、サステナビリティの都市計画: 11-3. 包摂的かつ持続可能な都市化の促進 が目指す姿とは逆行しています。
SDGs目標8「働きがいも経済成長も」の持続可能性
SDGs目標8には「持続可能な観光業を促進する」というターゲットがあります(8.9)。
インバウンド需要だけに依存する観光業は、非常に脆いものです。為替の変動、国際情勢、あるいは新たな感染症一つで、あっという間に需要が消え去るリスクを抱えています。
安定した国内客にそっぽを向かれた状態は、長期的に見て「持続可能な経済成長」とは言えません。石川県のホテルのように「欧州客が増えたからトントン」 というのは、短期的な安堵に過ぎない可能性があります。
「観光の二極化」が示すSDGs目標10「不平等」
記事では「万博などに局所的に人が集まる一方、それ以外は減って二極化が進んでいる」 と分析されています。
大阪(万博)や奈良、三重など西日本の一部は宿泊者が増えている一方、多くの地域が取り残されている。この「観光の二極化」は、地域間の経済格差、すなわちSDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」で解消すべき「不平等」を助長する懸念があります。
私たちの消費行動の変化:「メリハリ消費」とSDGs
[Image: 旅行(減少)とコンテンツ配信(増加)の消費動向を示すシンプルなグラフ]
興味深いのは、日本人が娯楽にお金を使わなくなったわけではない、という点です。
旅行への支出が減る一方で、「外食」や「コンテンツ配信」への支出は増加傾向にあります。
これは「メリハリ消費」と呼ばれ、コストパフォーマンスを厳しく見極める消費行動の表れです。これは、【用語解説】サステナブル消費とは?SDGsの観点から解説 の考え方にも通じます。
裏を返せば、今の国内旅行は「混雑・高騰」というコストに見合う「価値」を提供できていない、と消費者に判断されているのです。
今後の国内旅行に求められる「価値」とは何でしょうか。それは、【用語解説】エシカル消費とは?初心者向けに意味や事例を詳しく解説! の視点、すなわち「混雑していない快適さ」や「その地域に本当に貢献できる体験」といった、質的な満足度なのかもしれません。
私たちにできること:日野広大の視点
この大きな課題に対し、私たち個人、そして地域や企業は何ができるでしょうか。
1. 個人レベル:「時期」と「場所」をずらす旅
私たち旅行者にもできるアクションがあります。それは、「時期」と「場所」を意識的にずらすことです。
- 時期をずらす: 誰もが集中するピークシーズンを避け、平日に休みを取るなどオフシーズンを選ぶ。
- 場所をずらす: 有名な観光地(京都、東京など)だけでなく、「観光の二極化」で取り残されているかもしれない、まだ知られていない地域の魅力を発見しに行く。
これは混雑緩和(オーバーツーリズム対策)に貢献するだけでなく、地域の不平等をなくすことにもつながる、立派なSDGsアクションです。
2. 地域・企業レベル:「価格」から「価値」への転換
観光地やホテルは、「安売り」や「客数」を追う発想から転換すべき時です。
- 「価値」の提供: 宿泊費が高くても納得できる「質」の高い体験(例:静かな環境、地域文化との深い交流、環境配慮型のアメニティ)を提供する。
- データ活用: 記事にもあった京都商工会議所とソフトバンク、長崎大学の連携 のように、人流データを分析し、混雑を平準化する施策を打つ。
インバウンド客も、国内客も、そして何より地域住民も満足できる観光地経営。それこそが本物の【用語解説】サステナビリティ経営とは?持続可能な社会に向けた企業の取り組み です。
まとめ:観光業が「誰一人取り残さない」ために
インバウンドの活況は、日本経済にとって大きなチャンスです。しかし、その影で日本人観光客や、なにより地域で暮らす人々が「取り残されて」いないでしょうか。
【用語解説】SDGsとは?17のゴールと169のターゲットを徹底解説! の基本理念「誰一人取り残さない」に立ち返り、すべての人にとって持続可能な観光のあり方を、社会全体で再設計する時期に来ていると、強く感じます。
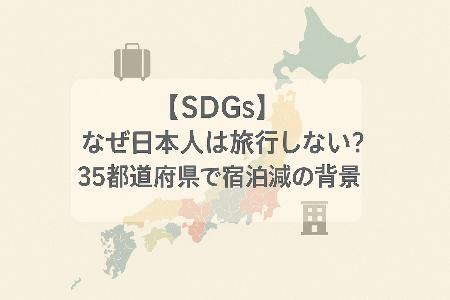
コメント