こんな人にオススメです
- 日本の人口減少問題と私たちの未来について関心がある方
- SDGsが、実は身近な暮らしの課題とつながっていることを知りたい方
- 多様性のある社会(DE&I)の実現に向けて、自分に何ができるか考えたい方
- 子どもたちの教育や未来のために、今からできることを探している方
「日本の人口が減っている」と聞いても、なんだか遠い話のように感じるかもしれませんね。でも、実はこの5年間での人口の減少数は、世界で2番目に多いというデータもあるんです。この変化は、私たちの暮らしにどんな影響を与えるのでしょうか?今回のニュースは、そんな未来を考える上でとても大切なヒントを、SDGsの視点から教えてくれますよ。
(出典:朝日新聞SDGs ACTION!, 2025.08.29)
SDGsニュースの要約
総務省の発表によると日本の人口は減り続けていますが、実はこの5年間の減少数は、ロシアによる侵攻があったウクライナに次いで世界で2番目に多い約266万人にも上るという衝撃的なデータがあります。しかも、日本人の減少数が外国人の増加数を上回っているのが特徴です。この記事では、こうした状況を踏まえ、SDGs(持続可能な開発目標)の視点から日本が考えるべき3つの重要なポイントを挙げています。1つ目は、多様性を受け入れ、お互いを認め合う「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」を学ぶこと。2つ目は、人口が減る地域でも暮らし続けられるよう、移動手段を確保し、太陽光発電のような小規模で地域ごとに管理できるインフラを増やすこと。そして3つ目は、子どものうちから社会に参加する機会を増やし、若い世代の声が未来の社会づくりに活かされるようにすることです。これは、私たちの未来の暮らしを考える上で、とても大切な視点と言えるでしょう。
SDGsニュースのポイント
今回のニュース、私たちの未来を考える上で大切なポイントがたくさん詰まっています。日野編集長の視点で、特に重要だと感じた点を分かりやすくまとめてみました。
- 世界で2番目に人口が減っている国、ニッポン: この5年間で日本の人口は約266万人も減少しました。これは戦争の影響があるウクライナに次いで世界で2番目に多い数字なんです。毎年、大きな市が一つなくなるくらいのペースだと考えると、その影響の大きさが想像できますね。
- 外国人は増えているのに…: 人口減少の大きな特徴は、日本に住む外国人の数は増えているのに、それを上回るペースで日本人の数が減っていることです。これは、これからの日本社会が、ますます多様な文化や背景を持つ人々とともに成り立っていくことを示しています。
- ポイント① DE&Iを学ぼう!: 社会の多様化が進む中で、ダイバーシティ&インクルージョン(DE&I)、つまり多様性を受け入れ、誰もが公平に参加できる社会づくりが不可欠になります。「みんな違って、みんないい」を本当に実現するための学びが、私たち一人ひとりに求められていますね。
- 「包摂性」ってなんだろう?: DE&Iの中でも特に大切なのが「インクルージョン(包摂性)」。これは、ただ一緒にいるだけでなく、お互いの違いを認め合い、尊重し合う心のことです。世代や文化の違いを乗り越えるための重要なカギになります。
- ポイント② インフラを見直す時が来た: 人が減っていく中で、大きな道路や電気網を今まで通り維持するのは難しくなっていきます。これからは、もっと小回りがきいて、持続可能なインフラが求められます。
- 地域の「足」を守る工夫: 「バス路線が廃止になった」「買い物が不便になった」…そんな未来にしないために、大型インフラに頼らない移動手段の確保が重要です。これはまさにSDGs 11「住み続けられるまちづくりを」につながる大切な視点です。
- エネルギーも「地産地消」へ: 例えば、地域にある小さな川で電気をつくる小水力発電や、みんなの家の屋根で太陽光発電を行うような「自律分散型」の仕組みが注目されています。これは再生可能エネルギーの普及にもつながり、まさに一石二鳥ですね。
- ポイント③ 子どもの声が未来をつくる: 子どもの数が減ると、選挙などで若い世代の声が届きにくくなる可能性があります。でも、未来の社会の主役は子どもたちです。
- 未来の主役の意見を政策に: 子どものうちから「自分も社会の一員だ」と感じられるように、地域のルール作りなどに参加する機会を増やすことがとても大切です。
- 「聴いてもらえている」が社会の満足度を上げる: 子どもや若者が「自分たちの意見がちゃんと聴いてもらえている」と感じられる社会は、結果的にみんなにとって満足度の高い、より良い社会になるはずです。これはSDGs 16「平和と公正をすべての人に」が目指す姿そのものと言えるでしょう。
SDGsニュースを考察
「人口減少」と聞くと、なんだかネガティブなイメージを持ってしまいがちですよね。でも、今回のニュースは、これを「私たちの社会が新しく生まれ変わるチャンス」と捉えるきっかけを与えてくれているように感じます。
ここがポイントです。人口減少社会は、これまでの「当たり前」を見直す絶好の機会なんです。
まず、DE&Iの視点。これからますます多様な背景を持つ人々が、私たちの隣人になります。これは、新しい文化や価値観に触れ、社会全体が豊かになる大きなチャンスです。大切なのは、お互いの違いを「壁」ではなく「彩り」として楽しむ心ではないでしょうか。これはSDGs 10「人や国の不平等をなくそう」の実現にも直結します。
次に、インフラの問題。これまでは「大きく、たくさん」作ることが豊かさの象徴でしたが、これからは「賢く、効率的に」使う時代です。例えば、ICT技術を活用して効率的な交通網やエネルギー供給網を築くスマートシティのような考え方は、まさに人口減少社会のモデルケースになるでしょう。コンパクトで、環境に優しく、誰もが暮らしやすいまちづくり。想像するだけでワクワクしませんか?
そして何より重要なのが、未来の世代へのバトンです。子どもの数が少なくなるからこそ、一人ひとりの声を大切に聴き、彼らが希望を持って社会に参加できる仕組みを作ることが、私たち大人の責任です。子どもたちの柔軟な発想が、私たちが思いもよらなかったような素晴らしい未来を拓いてくれるかもしれません。
私たちにできること
「そんな大きな話、自分には関係ない…」なんて思わないでくださいね。この変化の時代だからこそ、私たち一人ひとりの小さな一歩が大きな変化につながります。今日からできることから始めてみませんか?
- 地域の国際交流イベントに参加してみる: まずは、ご近所に住む外国の方々と話すきっかけを作ってみましょう。お互いの文化を知ることは、DE&Iの第一歩です。
- 新しい移動サービスを使ってみる: お住まいの地域にシェアリングエコノミーを活用したカーシェアや、デマンド交通はありませんか?積極的に利用することで、持続可能な地域の「足」を支えることにつながります。
- エネルギーの選び方を変えてみる: 自宅の電気を再生可能エネルギー由来のプランに切り替えることも、自律分散型の社会を応援するアクションです。
- 子どもと社会について話してみる: 「どんなまちに住みたい?」そんな簡単な問いかけからで構いません。家庭で子どもの意見に耳を傾けることが、彼らが社会に参加する意識を育みます。
- 地域の産品を選んで買う: 地域のお店で買い物をすることも、その地域の経済を支え、住み続けられるまちづくりにつながる立派なエシカル消費です。
人口減少は、決して暗い未来への一本道ではありません。私たちがどう向き合い、どう行動するかで、より豊かで持続可能な社会を築くためのターニングポイントになり得ると、私は信じています。
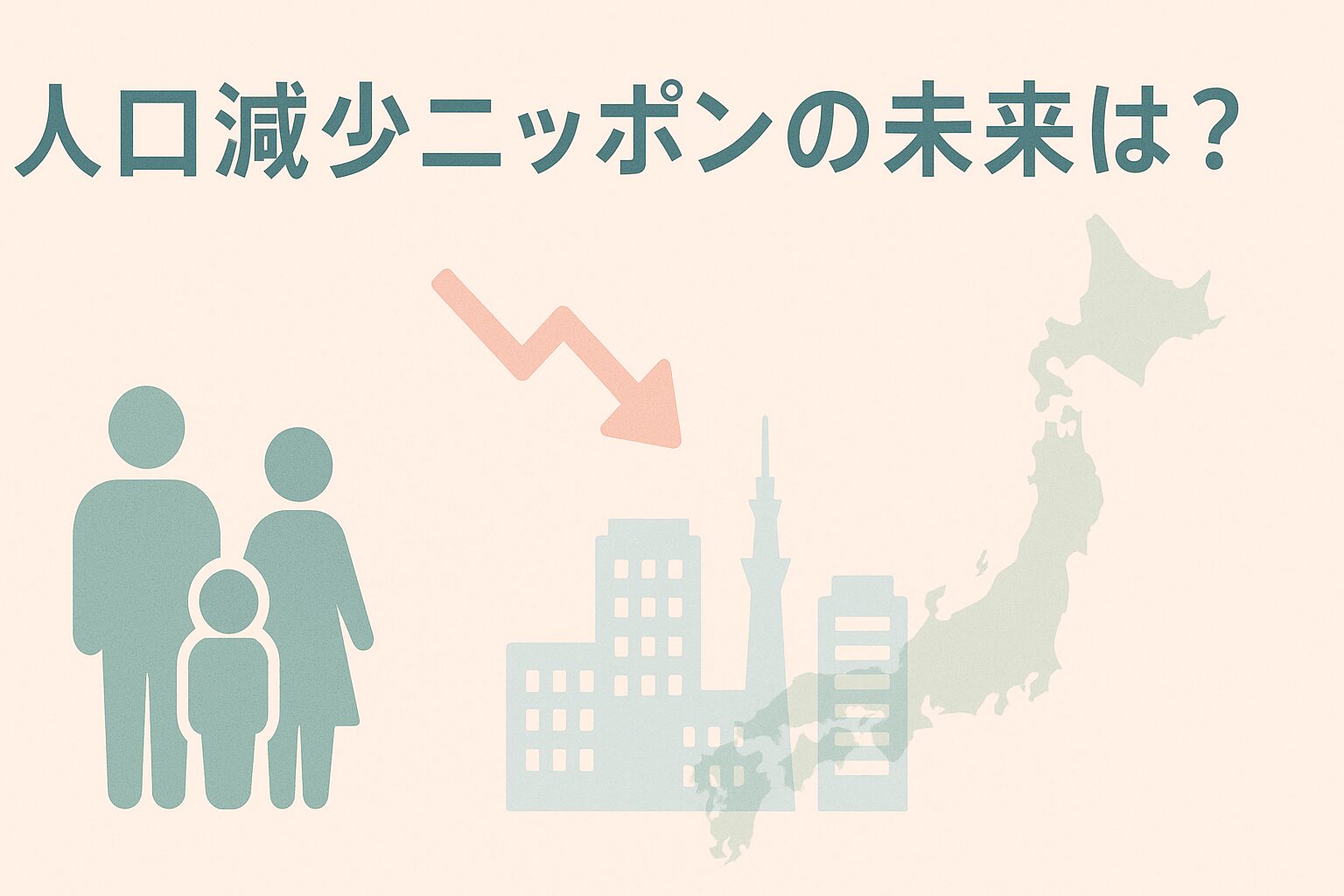
コメント