こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちの運営母体であるFrankPRは、SDGsへの貢献が評価され、政府のSDGs推進本部から「ジャパンSDGsアワード」の外務大臣賞を受賞しました。その専門的知見を活かし、SDGsの理想と現実を鋭く、そして分かりやすく解説します。
2030年の目標達成まで残り5年。SDGs採択から10年が経ち、言葉の認知度は飛躍的に高まりました。しかし、帝国データバンクが発表した衝撃的な調査結果が、日本のSDGs推進に暗い影を落としています。
この記事では、以下の核心に迫ります。
- データが示す「SDGs積極企業の減少」という現実
- なぜ大企業と中小企業で「SDGs格差」が生まれるのか?
- 「ブームの終わり」を乗り越え、本質的な取り組みへ進むための処方箋
- 「誰一人取り残さない」ために、各企業が今すぐできること
帝国データバンク調査が示す「SDGsのリアル」- 推進にブレーキか?
Forbes JAPANでも報じられた通り、今回の調査結果は、これまでの楽観的なムードに警鐘を鳴らすものです。
出典: SDGsの2030年目標に暗雲、大企業と中小企業で二極化か – Forbes JAPAN (元記事の想定)
調査元: 帝国データバンク「SDGsに関する企業の意識調査」
「積極的な企業」が初の減少、その背景にあるもの
調査によると、SDGsに「取り組んでいる」または「取り組みたい」と考える『積極的な企業』の割合は53.3%。これは、調査開始以来、初めて前年を下回るという深刻な結果です。
内訳を見ると、「取り組んでいる」企業は30.2%と過去最高を記録した一方で、「取り組みたい」と意欲を見せていた企業が減少しています。これは、意欲はあっても実際のアクションに移せない企業や、一度は意欲を見せたものの、取り組みを断念してしまった企業が増えていることを示唆しており、「SDGs疲れ」ともいえる状況が透けて見えます。
データで見る「大企業」と「中小企業」の深刻な格差
この停滞ムードをさらに深刻にしているのが、企業規模による取り組みの二極化です。
- 大企業: 71.1%が積極的
- 中小企業: 50.2%が積極的
- 小規模企業: 40.8%が積極的
大企業では7割以上が積極的なのに対し、小規模企業では4割程度に留まります。SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念とは裏腹に、日本経済を支える中小・小規模企業が置き去りにされかねない現実が、数字となって表れています。
なぜ中小企業でSDGsは進まないのか?現場から聞こえる3つの本音
なぜ、これほどの格差が生まれてしまうのでしょうか。調査で寄せられた声から、中小企業が直面する3つの大きな壁が見えてきます。
理由1:「日々の経営で余裕がない」という現実
「現状では当社に余裕がない」「ハードルが高い」。これは最も多く聞かれる声です。日々の資金繰りや人材確保に追われる中で、SDGsという新たなテーマに人や時間、コストを割くことが難しいという切実な事情があります。
理由2:「メリットが不明確」という壁
「取り組むことによる明確なメリットが不明」。SDGsが企業イメージや従業員のモチベーション向上に繋がるという効果は示されていますが、それが直接的な売上や利益にどう結びつくのか見えにくい、という声も根強いです。
理由3:「理念と現実のギャップ」への戸惑い
「理念ばかりが先行し、日本の既存の考え方や習慣と乖離がある」。SDGsを「海外から来た、意識の高いスローガン」と捉えてしまい、自社の事業との繋がりを見出せずにいるケースも少なくありません。
【編集長視点】これは「ブームの終わり」ではなく「本質が問われる時代」の始まり
この調査結果を、単なる「SDGsブームの終焉」と結論づけるのは早計です。私は、SDGsが「流行」から「経営のスタンダード」へと移行する過程で起きる、必然的な踊り場だと捉えています。ここからが、企業の真価が問われる時代の始まりです。
「意識せず貢献」している活動こそが宝の山
興味深いことに、調査では「取り組んでいない」と回答した企業の中に、無意識にSDGsに貢献しているケースが多数見られました。例えば、
- 地域の清掃活動(ゴール11:住み続けられるまちづくりを)
- 廃棄物削減の努力(ゴール12:つくる責任 つかう責任)
- 従業員の健康管理や資格取得支援(ゴール3, 4, 8)
- 女性が働きやすい職場環境づくり(ゴール5:ジェンダー平等を実現しよう)
これらはすべて立派なSDGs活動です。まずは自社の「当たり前」の取り組みが、どのSDGs目標に繋がるのかを「翻訳」し、可視化することから始めるべきです。
最重要目標「働きがい」は中小企業の生命線
企業が最も注力している目標のトップが「働きがいも経済成長も(ゴール8)」であったことは、非常に示唆に富んでいます。特に人手不足が深刻な中小企業にとって、従業員が働きがいを感じ、定着してくれることは、企業の存続に直結する最重要課題です。SDGsは、この課題を解決するための強力なツールとなり得ます。
「誰一人取り残さない」ために今、できること
2030年の目標達成に向け、この二極化を放置するわけにはいきません。それぞれの立場でできることがあります。
中小企業ができるスモールステップ
まずは「SDGs」という言葉に気負わず、自社の事業の強みや日々の活動を見つめ直すことから始めましょう。そして、それをSDGsの17のゴールのどれかに紐づけてみてください。新たな補助金申請や、取引先へのアピール、採用活動でのPRに繋がる可能性があります。
大企業・金融機関に求められる役割
サプライチェーンの要である大企業は、中小企業にSDGs対応を一方的に求めるのではなく、ノウハウの共有や共同での勉強会開催といった「伴走型支援」が不可欠です。金融機関も、単に評価するだけでなく、SDGsへの取り組みを促すようなコンサルティング機能や金融商品を提供することが期待されます。
政府・自治体に期待される支援策
中小企業が具体的なメリットを実感できるような、より踏み込んだ補助金制度や、成功事例の分かりやすい共有が求められます。SDGsに取り組むことが、明確に「得をする」仕組みづくりが急務です。
まとめ
今回の調査は、日本のSDGs推進が正念場を迎えていることを示しました。
- 企業のSDGsへの取り組み意欲が調査開始以来、初めて減少に転じた。
- 大企業と中小・小規模企業の間で、深刻な「SDGs格差」が生まれている。
- 原因は「余裕・メリット・実感」の不足にある。
- しかし、これは「本質」が問われる時代の幕開けであり、自社の活動を見つめ直す好機でもある。
SDGsは、遠い国の目標ではなく、自社の持続的な成長を実現するための経営哲学です。この踊り場を乗り越え、再び加速できるか。日本の未来は、中小企業一社一社の次の一歩にかかっています。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料: Forbes JAPAN、帝国データバンク「SDGsに関する企業の意識調査」
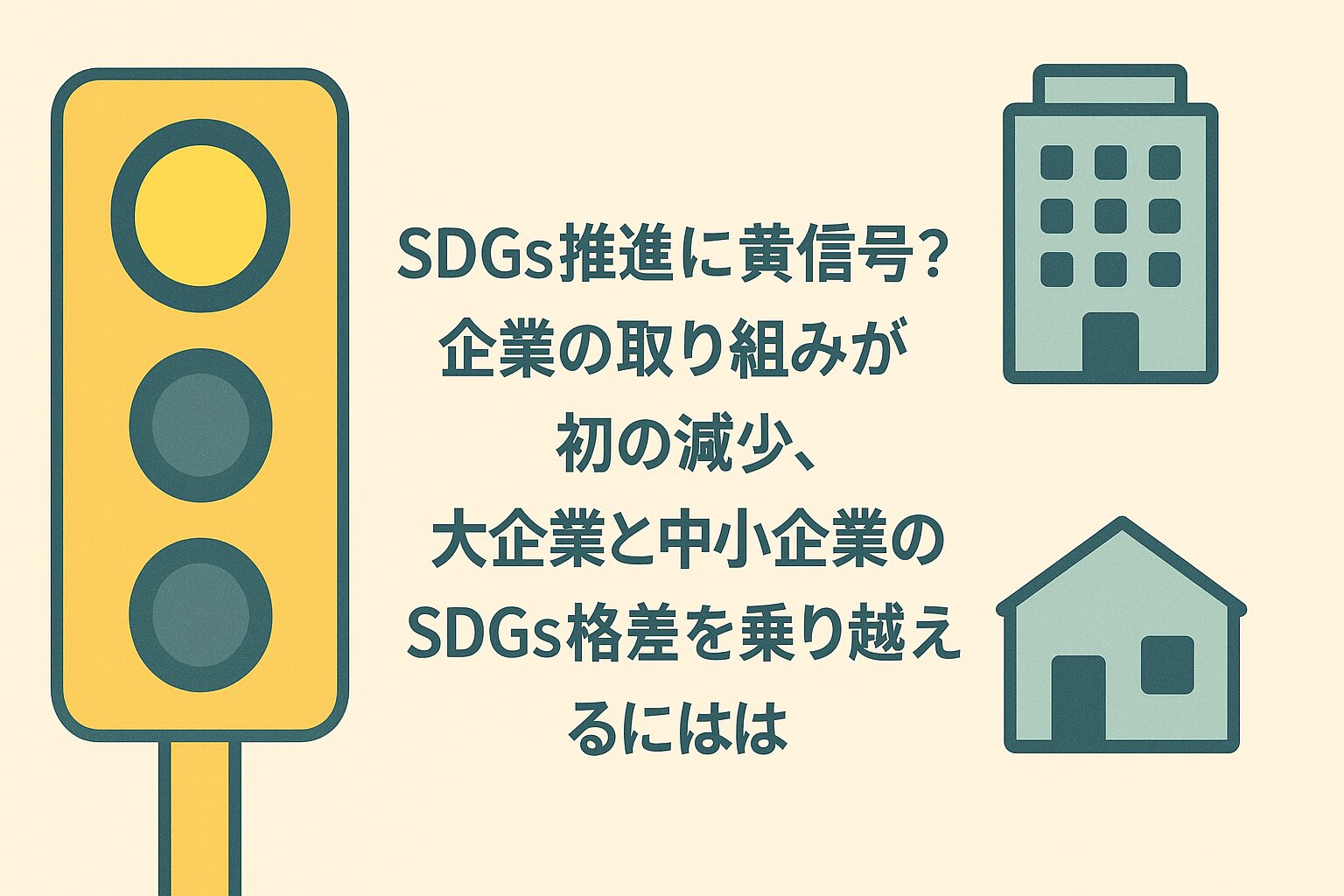
コメント