こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディアは、SDGsへの貢献が評価され、政府SDGs推進本部から「ジャパンSDGsアワード」の外務大臣賞をいただいたFrankPRが運営しています。今回は、私たちの健康と地球の未来に深く関わる「食」についての重要なニュースを、専門家の視点から解説します。
近年の研究で、手軽で安価な「超加工食品(Ultra-Processed Foods, UPFs)」が、私たちの健康に深刻な影響を及ぼす可能性が次々と指摘されています。最新の包括的なレビューでは、その関連が32もの健康問題に及ぶことが示されました。この記事では、この衝撃的な事実を深掘りし、特に問題視される「コーンシロップ」の害にも触れながら、SDGsの観点から私たちが何をすべきかを考えていきます。
この記事でわかること
- 最新研究が明らかにした超加工食品の健康リスク
- なぜ超加工食品は身体に悪いのか?添加物と「コーンシロップ」の問題点
- 食の問題がSDGs(特に健康、飢餓、持続可能な生産)とどう繋がるか
- 明日から実践できる、健康と地球を守るためのアクション
「便利」の裏に潜む健康リスク:最新研究が示す超加工食品の脅威
先日、英国医師会雑誌(BMJ)に掲載された、約1000万人ものデータを分析した大規模な研究レビューは、世界に衝撃を与えました。それは、超加工食品の摂取が、心臓病、がん、2型糖尿病、精神疾患など、実に32項目もの健康上の問題と直接的・間接的に関連していることを突き止めたものです。
参照ニュース: Ultra-processed foods linked to 32 harmful effects on health, review finds (BBC News)
この研究が示す特に深刻なリスクは以下の通りです。
- あらゆる原因による死亡リスク:最大21%増加
- 心臓関連の疾患による死亡リスク:最大50%増加
- 不安や一般的な精神障害のリスク:最大48~53%増加
- 2型糖尿病のリスク:12%増加
超加工食品とは、単に「加工された食品」ではありません。工業的な過程で、天然素材が分解され、着色料、香料、乳化剤、甘味料といった添加物を加えて成形された、「工業製品に近い食品」と考えるべきものです。
【超加工食品の具体例】
- 菓子パン、量産されたパン
- 多くのシリアル、プロテインバー
- 炭酸飲料、加糖ジュース
- インスタント麺、冷凍ピザなどの調理済み食品
- チキンナゲットなどの成形肉
これらの食品は、安価で保存が効き、すぐに食べられるという利便性から、私たちの食生活に深く浸透しています。しかし、その「便利さ」と引き換えに、私たちは健康という大きな代償を払っているのかもしれません。
なぜ超加工食品は体に悪いのか?コーンシロップという「甘い罠」
では、なぜ超加工食品はこれほどまでに健康リスクを高めるのでしょうか。理由は複合的ですが、大きく分けて2つの問題点があります。
1. 工業的製法が奪う栄養と加える添加物
超加工食品は、製造過程でビタミンやミネラル、食物繊維といった重要な栄養素が失われがちです。その一方で、味や食感、保存性を高めるために、過剰な糖分、塩分、不健康な脂肪、そして多数の食品添加物が加えられます。
これらの添加物の中には、腸内環境を乱したり、体内で炎症を引き起こしたりする可能性が指摘されているものも少なくありません。本来の食材が持つ栄養バランスが崩れ、体にとって不自然な物質を摂取し続けることが、様々な疾患の引き金になると考えられています。
2. 特に注意したい「異性化糖(コーンシロップ)」の健康への影響
超加工食品の「甘さ」の正体として、特に注意が必要なのが「異性化糖(高果糖コーンシロップ、HFCS)」です。これは、トウモロコシのでんぷんを原料に、酵素を使って人工的に作り出された液状の糖です。
【コーンシロップ(異性化糖)の問題点】
- 安価で加工しやすい:砂糖よりも安いため、清涼飲料水や菓子、加工食品に非常に広く使われています。原材料表示で「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」と書かれているものがこれにあたります。
- 血糖値を急上昇させやすい:特に液体で摂取すると体への吸収が速く、血糖値を急激に上昇させ、インスリンの過剰分泌を招きます。これが繰り返されると、肥満や2型糖尿病のリスクを著しく高めます。
- 肝臓への負担:異性化糖に含まれる「果糖(フルクトース)」は、主に肝臓で代謝されます。過剰に摂取すると、肝臓で中性脂肪に変換されやすく、脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患, NAFLD)の原因となります。
- 依存性:強い甘みは満足感をもたらしますが、同時に脳の報酬系を刺激し、もっと欲しくなるという依存性を生む可能性があります。
この「甘い罠」は、消費者が気づかぬうちに糖分を過剰摂取させ、生活習慣病のリスクを忍び寄らせるのです。
食の問題は地球の課題へ:超加工食品とSDGsの深い関係
超加工食品の問題は、個人の健康にとどまりません。それは、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」とも深く結びついています。
目標3「すべての人に健康と福祉を」への直接的な挑戦
超加工食品の蔓延は、非感染性疾患(NCDs)を世界的に増加させ、SDGs目標3の達成を直接的に脅かしています。健康的な食生活を送ることが経済的・地理的に困難な人々ほど超加工食品に頼らざるを得ないという「健康格差」の問題も深刻化させています。
目標2「飢餓をゼロに」と目標12「つくる責任 つかう責任」の視点
安価な超加工食品はカロリーを手軽に摂取できますが、栄養価は乏しく、微量栄養素が不足する「隠れ飢餓」を引き起こすことがあります。
さらに、脱炭素の観点からも問題は大きいのです。
- 原料生産の環境負荷:コーンシロップの原料となるトウモロコシのように、単一作物を大規模に栽培する「モノカルチャー農業」は、化学肥料や農薬を大量に必要とし、土壌を疲弊させ、生物多様性を損ないます(目標15:陸の豊かさも守ろう)。
- 複雑なサプライチェーン:世界中から原料を調達し、巨大な工場で加工・包装し、再び世界中に輸送する超加工食品のサプライチェーンは、大量のエネルギーを消費し、多くの温室効果ガスを排出します(目標13:気候変動に具体的な対策を)。
- 大量の包装ごみ:プラスチックなどの過剰な包装は、海洋プラスチック問題(目標14:海の豊かさを守ろう)や廃棄物問題(目標12)を深刻化させます。
つまり、超加工食品に依存する食料システムは、人の健康だけでなく、地球の健康をも蝕む、持続可能性の低いシステムなのです。
私たちの食卓から始めるアクションプラン
この大きな問題に対して、私たちは何ができるのでしょうか。悲観的になる必要はありません。日々の小さな選択が、自分自身の健康と地球の未来を変える力になります。
【個人でできること】
- 食品の裏側を見る習慣を:買い物の際に、原材料表示を確認しましょう。「果糖ぶどう糖液糖」や、知らないカタカナの添加物が多く並んでいたら、それは超加工食品のサインです。
- 加工度の低い食品を選ぶ:できるだけ、食材そのものの形が分かるもの(野菜、果物、肉、魚、豆類など)を選び、自分で調理することを楽しみましょう。
- 「本物の味」を知る:加工食品の強い味に慣れると、素材本来の繊細な味が分からなくなってしまいます。出汁のうま味や、野菜の甘みなど、自然な味わいを大切にする食生活を心がけましょう。
【社会全体で取り組むべきこと】
- 企業:消費者の健康と地球環境に配慮した、持続可能で栄養価の高い製品開発への転換が求められます。
- 政府:国民が健康的な食品を選びやすいよう、分かりやすい栄養表示(警告ラベルなど)、子どもを対象とした広告の規制、公共施設での超加工食品の販売制限といった政策の導入が急務です。
まとめ:賢い選択で、自分と地球の未来を守る
今回ご紹介したニュースは、私たちの便利な食生活が、健康と地球環境という見えないコストの上に成り立っている可能性を強く示唆しています。
超加工食品を完全に排除するのは難しいかもしれません。しかし、そのリスクを正しく理解し、少しずつでも摂取を減らしていくことは可能です。
私たちFrankPRは、「脱炭素とSDGsの知恵袋」として、今後もこうした食と持続可能性に関する情報を発信し、企業や個人の皆様がより良い選択をするためのお手伝いをしていきます。
あなたの次の一回の食事が、あなた自身の健康を守り、ひいては地球の未来を良くするための一歩となるのです。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大 参考資料:
- BBC News: Ultra-processed foods linked to 32 harmful effects on health, review finds
- BMJ: Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses
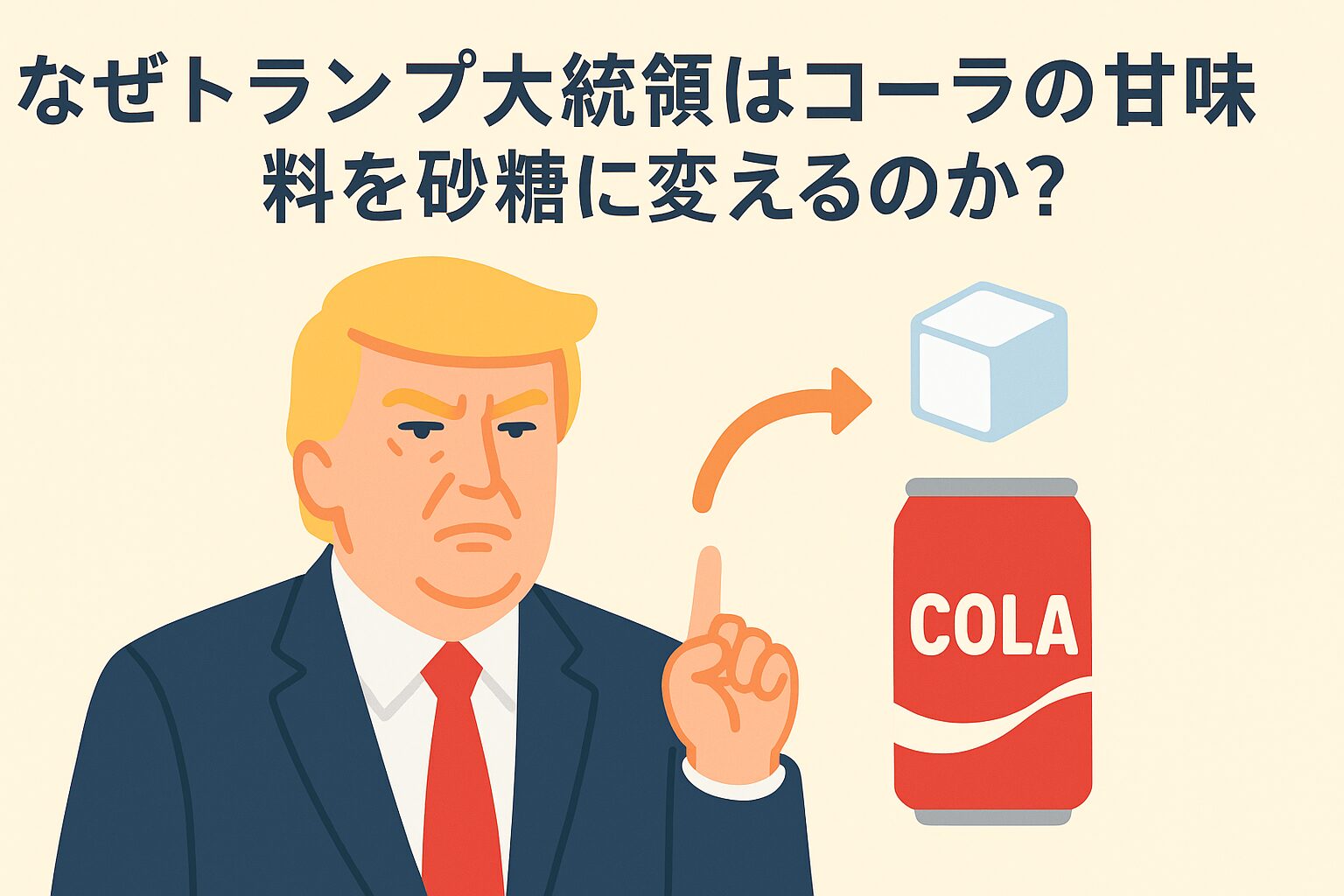
コメント