皆さん、こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。私たちのメディアは、SDGs達成に向けた企業の取り組みが評価され、政府SDGs推進本部からジャパンSDGsアワード(外務大臣賞)を受賞したFrankPR株式会社が運営しています。その専門性を活かし、今回は多くの企業が課題を感じている「新卒採用」、特にZ世代と呼ばれる若者たちの就職活動とSDGsの深い関わりについて、最新の調査結果を基に解説します。
この記事のポイント
- 新卒採用市場の現状:6割以上の企業が採用目標未達。
- Z世代は「SDGsネイティブ」:9割以上がSDGsの学習経験あり。
- 最重要関心事はSDGs目標4「質の高い教育をみんなに」:背景に教育格差への問題意識と社会への不安。
- SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」も重要関心事:SNSの影響も?
- 企業のSDGsへの取り組みが採用力を左右する時代へ。
- 希望勤続年数で異なる学生ニーズと、企業が取るべきアプローチとは?
なぜSDGs?9割以上が学習経験あり、Z世代の就活におけるSDGs意識
「就職白書2025」によると、実に6割以上の企業が新卒採用で予定人数を確保できていないという厳しい現実があります。では、どうすれば企業は採用力を上げられるのでしょうか?その鍵を握るのが、今の大学生・大学院生、いわゆるZ世代の価値観であり、特にSDGsへの意識の高さです。
「SDGsシューカツ解体白書」が示すZ世代のリアル
今回注目するのは、SoZo株式会社が法政大学・関西学院大学の学生と共同で行った意識調査「【Z世代】SDGsシューカツ解体白書」の結果です。(参考:元記事リンク Yahoo!ニュース)
この調査によると、現役大学生・大学院生の9割以上(男性90.4%、女性95.6%)が「SDGsについて学習したことがある」と回答しています。小学校から高校、そして大学へと、彼らは教育課程の中で繰り返しSDGsに触れており、まさに「SDGsネイティブ世代」と呼べる存在です。
SDGs学習経験と企業選びの関係性
これだけSDGsが浸透しているということは、企業が採用活動においてSDGsへの取り組みを語ることが、学生との重要な接点となり得ることを意味します。環境問題だけでなく、貧困、教育、ジェンダー、働きがいなど、SDGsの17のゴールは非常に多岐にわたります。自社の事業や取り組みがどのゴールに貢献しているのかを理解し、学生に分かりやすく伝えることが、企業の魅力を高める上で有効と言えるでしょう。
就活生が最重視するSDGs目標は「教育」:その背景にある不安とは
驚くべきことに、同調査でSDGsの17目標のうち学生が最も関心を持っているのは、3年連続で目標4「質の高い教育をみんなに」でした。さらに、「働く上で福利厚生や環境整備としてポジティブに受け取る目標」としても、「社員、アルバイト、契約社員など全員への質の高い研修・教育サポート」が同じく3年連続1位となっています。
教育格差への問題意識と「質の高い研修」への期待
なぜ彼らはこれほどまでに「教育」に関心を持つのでしょうか?調査からは、「奨学金など教育費の問題」や「地域や収入による教育格差」といった、社会的な課題への強い問題意識がうかがえます。特に教育格差は、学生自身が経験したり、身近で見聞きしたりする中で、将来への不安に繋がっている可能性があります。
失敗したくないZ世代と企業の教育サポート
この教育格差への問題意識は、企業選びにおける「質の高い研修・教育サポート」への期待に直結しています。記事中の学生の声にもあるように、「社会に出てからは正解がない」「失敗したくない」という不安感が、Z世代には少なからず存在します。
身近な例で考えてみましょう。新しいゲームを始めるとき、最初に丁寧なチュートリアルがあると安心して進められますよね? それと同じように、学生たちは社会という新しいステージに進むにあたり、企業が提供する最初の「チュートリアル」=研修・教育サポートがしっかりしていることを求めているのです。入社後のキャリア形成やワークライフバランスにも影響すると直感的に感じているのかもしれません。
企業としては、単に研修があるというだけでなく、その内容の質、継続性、多様な働き方(契約社員など)への対応といった点を具体的にアピールすることが、学生の不安を解消し、安心感を与えることに繋がります。
「ジェンダー平等」への高い関心:SNS時代の不安と企業への視線
「教育」に次いで、特に女子学生から毎年高い関心を集めているのが**目標5「ジェンダー平等を実現しよう」**です。調査では、何らかのジェンダー不平等を感じたことがある学生が男性でも65.4%、女性では77.1%と高い水準でした。
SNSが助長する?ジェンダー不平等への問題意識
その背景の一つとして挙げられているのが、SNSの影響です。SNS上では、残念ながら性差別的な発言や、特定の性別役割を押し付けるような意見、育児中の女性や育休を取得する男性への批判などが見受けられます。企業がジェンダーに関する配慮を欠いた発信をして「炎上」するケースも後を絶ちません。こうした情報に日常的に触れることで、学生たちは社会におけるジェンダー不平等への不安を募らせている可能性があります。
採用におけるジェンダー配慮と情報開示の重要性
この不安は、就職活動においても「この会社は大丈夫だろうか?」という視線に繋がります。企業側も採用広報や面接での言葉選びには従来以上に注意が必要ですが、さらに一歩進んで、具体的な制度や実績を示すことが重要です。
- 女性管理職比率や男女の賃金格差の開示
- 育児・介護休業制度の取得実績(男女別)
- 多様な働き方を支援する制度(フレックスタイム、リモートワークなど)
- ジェンダーに関する研修の実施状況
こうした情報を積極的に開示し、ジェンダー平等に真剣に取り組む姿勢を示すことが、特に女子学生や多様な価値観を持つ学生からの信頼を得て、志望度を高める鍵となるでしょう。
企業のSDGs取り組みが採用力を左右する時代【専門家解説】
これまでの調査結果から明らかなように、現代の就職活動において、企業のSDGsへの取り組みは、学生が企業を選ぶ上で無視できない要素となっています。
ワークライフバランス、仕事内容、そしてSDGs
もちろん、「ワークライフバランス」や「サービス・商品への好意/将来性」、「やりたい仕事(募集職種)ができるか」といった要素も依然として重要です。しかし、これらに加えて、その企業が社会や環境に対してどのような価値を提供しようとしているのか(=SDGsへの貢献)が、新たな判断軸として加わっているのです。
私たちFrankPRが企業のSDGs情報発信を支援する中でも、学生向けの説明会などで、自社の取り組みとSDGsの関連性を分かりやすく伝えることの重要性を実感しています。これは単なるイメージアップ戦略ではなく、学生の価値観に合致し、共感を呼ぶための本質的なコミュニケーションと言えるでしょう。
希望勤続年数で異なる?学生のニーズに合わせたアピール戦略
さらに興味深いのは、学生が希望する勤続年数によって、企業に求めるものが異なる傾向が見られる点です。
- 「3年以内転職/起業」希望層: 入社後すぐに成長できる、第一線で活躍できる環境を重視する傾向。「まずはこの会社でスキルを磨きたい」という意欲の表れかもしれません。企業としては、若手への権限委譲や挑戦できる風土をアピールするのが効果的でしょう。
- 「10年以上同じ会社/終身雇用」希望層: 給与の高さや「社会的に意義のあるサービスに携わりたい」という意向が強まる傾向。長く働くことを見据え、安定した待遇と、社会貢献実感を求めていると考えられます。企業としては、安定した経営基盤や福利厚生、そして自社の事業が社会課題の解決にどう繋がっているかを強調すると響きやすいでしょう。
このように、「Z世代」と一括りにせず、多様な価値観やキャリアプランを持つ学生一人ひとりに合わせて、伝えるべきメッセージを調整していく視点が求められます。
まとめ:SDGsを軸にZ世代と向き合う、これからの新卒採用
今回の調査結果は、企業の新卒採用担当者にとって多くの示唆を与えてくれます。SDGsネイティブであるZ世代は、社会や環境に対する問題意識が高く、働くことを通じてポジティブな影響を与えたいと考えている層が少なくありません。
企業が採用力を高めるためには、SDGsへの取り組みを単なる「流行り」や「CSR活動」として捉えるのではなく、経営戦略や事業活動そのものに組み込み、それを学生に誠実に、具体的に伝えていくことが不可欠です。
特に、「質の高い教育(研修)」や「ジェンダー平等」といった学生の関心が高いテーマについて、自社がどのような課題認識を持ち、どのような具体的な取り組みを行っているのかを示すことが、共感と信頼を得るための重要な鍵となります。
あなたの会社は、未来を担うZ世代の価値観に、しっかりと向き合えているでしょうか? SDGsという共通言語を通じて、学生とのより良い対話を始めてみませんか。
さらに詳しく知るために
- リクルート 就職みらい研究所: https://shushokumirai.recruit.co.jp/
- SoZo株式会社(調査実施企業): https://www.google.com/search?q=https://sozo-inc.com/
- 外務省「JAPAN SDGs Action Platform」: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/
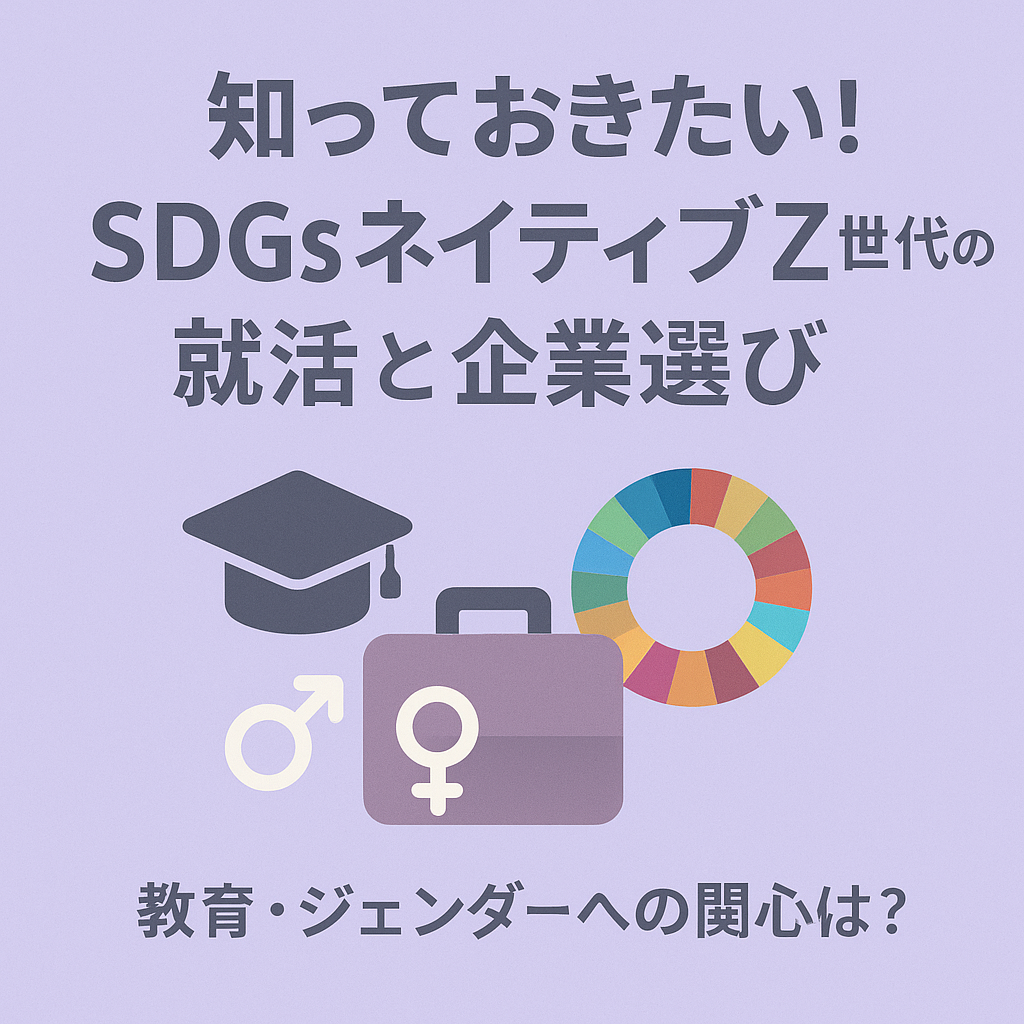
コメント