こんにちは。「脱炭素とSDGsの知恵袋」編集長の日野広大です。当メディアは、ジャパンSDGsアワードで外務大臣賞を受賞した企業の知見を活かし、国内外の最新動向を厳選してお届けしています。
2025年8月、日本が世界に誇る釧路湿原をめぐり、大きな声が上がりました。アルピニストの野口健さんの呼びかけに、モデルの冨永愛さん、タレントのつるの剛士さんといった著名人が次々と賛同し、湿原周辺で進むメガソーラー建設に「待った」をかけたのです。
「なぜ貴重な生態系のある場所にメガソーラーを?」
この素朴で、しかし本質的な問いは、今、多くの人々の共感を呼んでいます。脱炭素社会の実現に不可欠なはずの太陽光発電が、なぜこれほどまでに批判されるのか。今回はこの問題を、SDGsが抱える「光」と「影」の側面から、専門的に、そして分かりやすく解説していきます。
この記事のポイント
- 釧路湿原で今、何が起きているのか?
- 専門家が指摘する「SDGsのジレンマ」とは?
- なぜ自然豊かな場所が狙われるのか?その背景
- 私たちが目指すべき、真に持続可能なエネルギー社会の姿
ニュースの概要:著名人が繋ぐ「釧路湿原を守れ」の声
発端は、俳優・モデルの冨永愛さんがX(旧ツイッター)に投稿した「なんで貴重な生態系のある釧路湿原にメガソーラー建設しなきゃならないのか誰か教えて欲しい」という問いかけでした。これにアルピニストの野口健さんが応じ、「一緒にアクションを起こしませんか」と現地視察を呼びかけると、瞬く間に大きな反響を呼びました。
タレントのつるの剛士さん、ミュージシャンの世良公則さん、実業家の前澤友作さんなど、各界の著名人が次々と懸念を表明。SNSを通じて「釧路湿原のメガソーラー問題」は、一気に国民的な関心事となったのです。
問題となっているのは、ラムサール条約にも登録されている国際的に重要な湿地、釧路湿原の周辺です。平坦で日照量が多いという理由から、大規模な太陽光発電所(メガソーラー)の建設が相次いでいますが、これが貴重な生態系を破壊するのではないかと、強い懸念が示されています。
専門的視点:これは「SDGsのジレンマ」である
この問題を単なる「環境破壊か、クリーンエネルギーか」という二元論で捉えるのは早計です。これは、私たちが目指すSDGs(持続可能な開発目標)の、まさに目標どうしが衝突する「ジレンマ」の典型例なのです。
【光】気候変動対策という大義(SDGs 7, 13)

alt属性: SDGsの目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」と目標13「気候変動に具体的な対策を」のロゴ
言うまでもなく、太陽光発電はSDGs 7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)やSDGs 13(気候変動に具体的な対策を)を達成するための重要な切り札です。化石燃料から脱却し、地球温暖化を食い止めるために、再生可能エネルギーの導入を急ぐことは世界共通の課題です。
世良公則さんが指摘するように、この推進を支えている一因が、私たちの電気料金に含まれる「再エネ賦課金」です。国民全体で再生可能エネルギーを支え、脱炭素を進める。この大きな流れ自体は、決して間違ってはいません。
【影】失われる陸の豊かさ(SDGs 15, 11)

alt属性: 釧路湿原に生息するタンチョウ
一方で、どんなにクリーンなエネルギーでも、どこに作るかを間違えれば、取り返しのつかない環境破壊を引き起こします。釧路湿原は、タンチョウやイヌワシなど希少な生物の宝庫であり、SDGs 15(陸の豊かさも守ろう)やSDGs 11(住み続けられるまちづくりを)における「世界の文化遺産及び自然遺産を保護し、保全する」というターゲットに直結する場所です。
貴重な自然を大規模に伐採・造成してパネルを敷き詰めれば、その土地の生態系は破壊され、保水力が失われて防災機能が低下する恐れもあります。気候変動対策のために、生物多様性や地域の安全を犠牲にしては、本末転倒です。
なぜ問題は起きるのか?「ゾーニング」不在の課題
では、なぜこのような貴重な自然が開発の対象となってしまうのでしょうか。
背景には、再生可能エネルギー施設の建設場所を適切に定める「ゾーニング(土地利用のすみ分け)」の議論が、法整備として十分に追いついていない現状があります。事業採算性だけを優先すると、平坦で地価が安く、送電線に近い土地、つまり釧路湿原周辺のような場所が候補に上がりやすくなるのです。
環境省も「再生可能エネルギー導入に当たっての景観・環境等の保全のあり方」についてガイドラインを示していますが、法的な拘束力は弱く、事業者の判断に委ねられているのが実情です。
私たちが目指すべき道:対立から「共生」へ
この問題の解決策は、太陽光発電を全否定することではありません。自然と共生する形での、賢いエネルギー導入へと舵を切ることです。
- 適地への誘導とゾーニングの法制化
国や自治体が主導し、環境への影響が少ない「促進区域」と、原則として開発を抑制すべき「保全区域」を明確に区分けする法整備が急務です。 - 既存インフラの徹底活用
これ以上自然を破壊するのではなく、建物の屋根や壁、駐車場、ため池の水上、あるいは農業と両立するソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)など、すでに人の手が加わった場所を最大限に活用するべきです。 - 私たち市民ができること
まずはこの問題に関心を持つことが第一歩です。そして、自分が契約する電力会社が、どのような電源から電気を買っているのかを調べてみるのも良いでしょう。環境や社会への配慮を重視する電力会社を選ぶことも、私たちにできる具体的なアクションです。
まとめ:著名人の声は、国民的議論の始まり
野口健さんや冨永愛さんたちの声は、単なるメガソーラー反対運動ではありません。それは、「私たちの目指す脱炭素社会は、本当に持続可能な姿をしているか?」という、国民全体への問いかけです。
クリーンエネルギーという「光」の側面だけを見て突き進むのではなく、その「影」にも目を向け、どうすればその影を最小化できるのか。今回の問題をきっかけに、社会全体で対話し、より良い答えを見つけ出すこと。それこそが、真のSDGs達成への道筋だと、私は信じています。
執筆:脱炭素とSDGsの知恵袋 編集長 日野広大
参考資料:
【メタディスクリプション案】
冨永愛さん、野口健さんらが警鐘を鳴らす釧路湿原メガソーラー問題。なぜ反対の声が強まるのか?脱炭素と自然保護というSDGsのジレンマを専門家が解説。私たちがとるべき真に持続可能な道を探ります。
【OGP文案】
【編集長解説】釧路湿原の自然が危ない?メガソーラー建設に冨永愛さんら著名人が反対の声を上げる理由とは。クリーンエネルギー推進の裏で失われるものを、SDGsの視点から深く掘り下げます。
【パーマリンク】
https://franksdgs.com/sdgs-blog/kushiro-wetland-megasolar-sdgs-dilemma
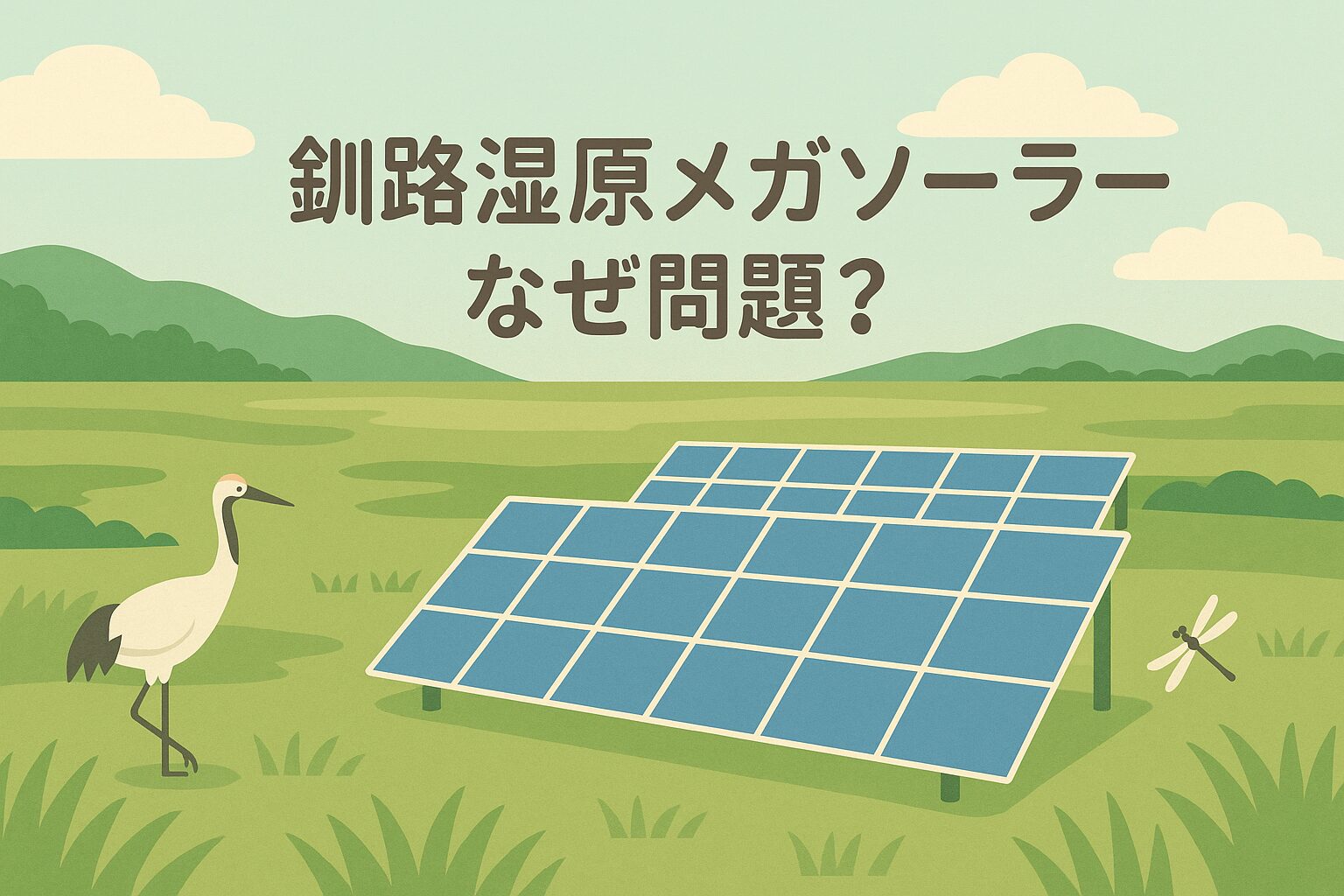
コメント